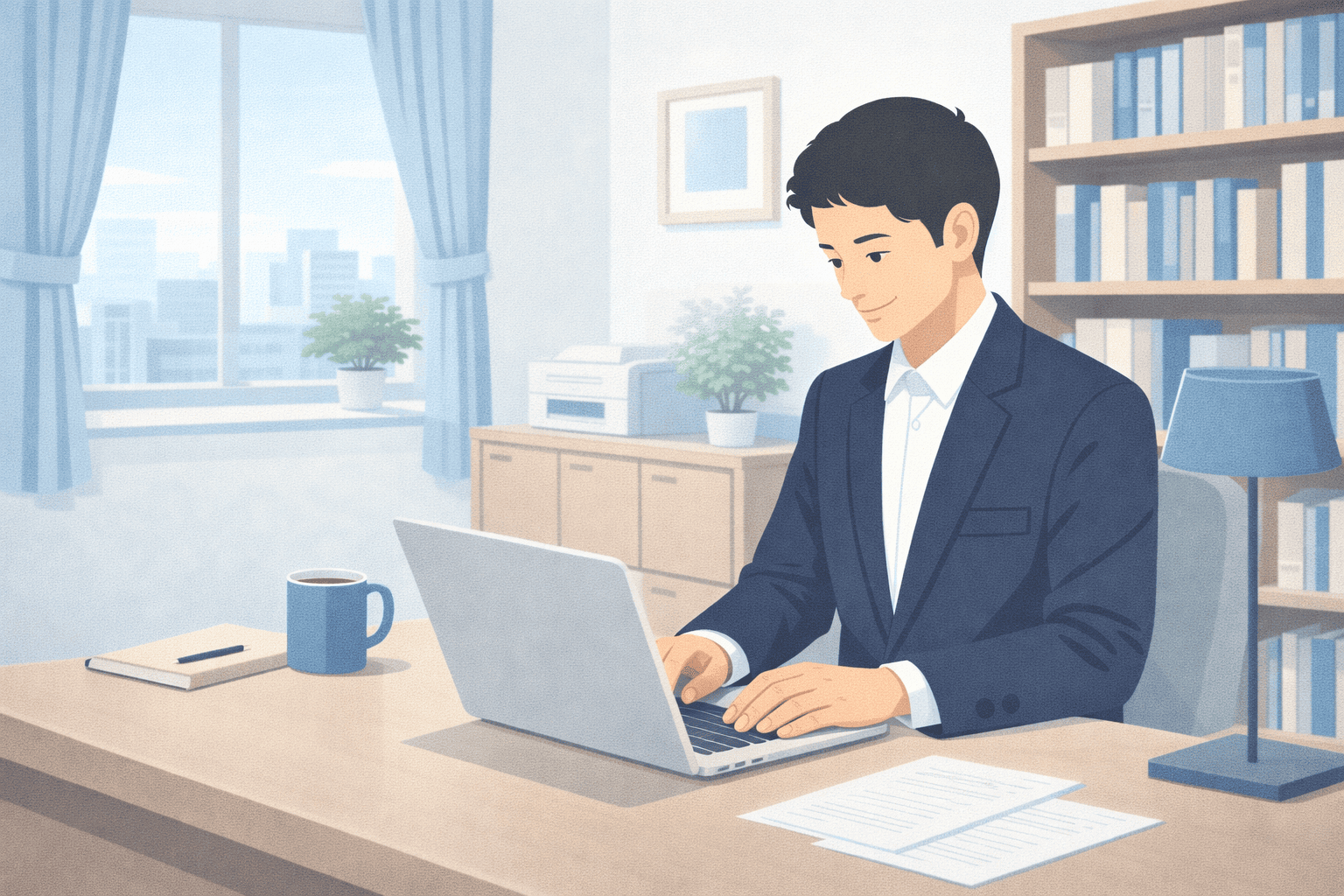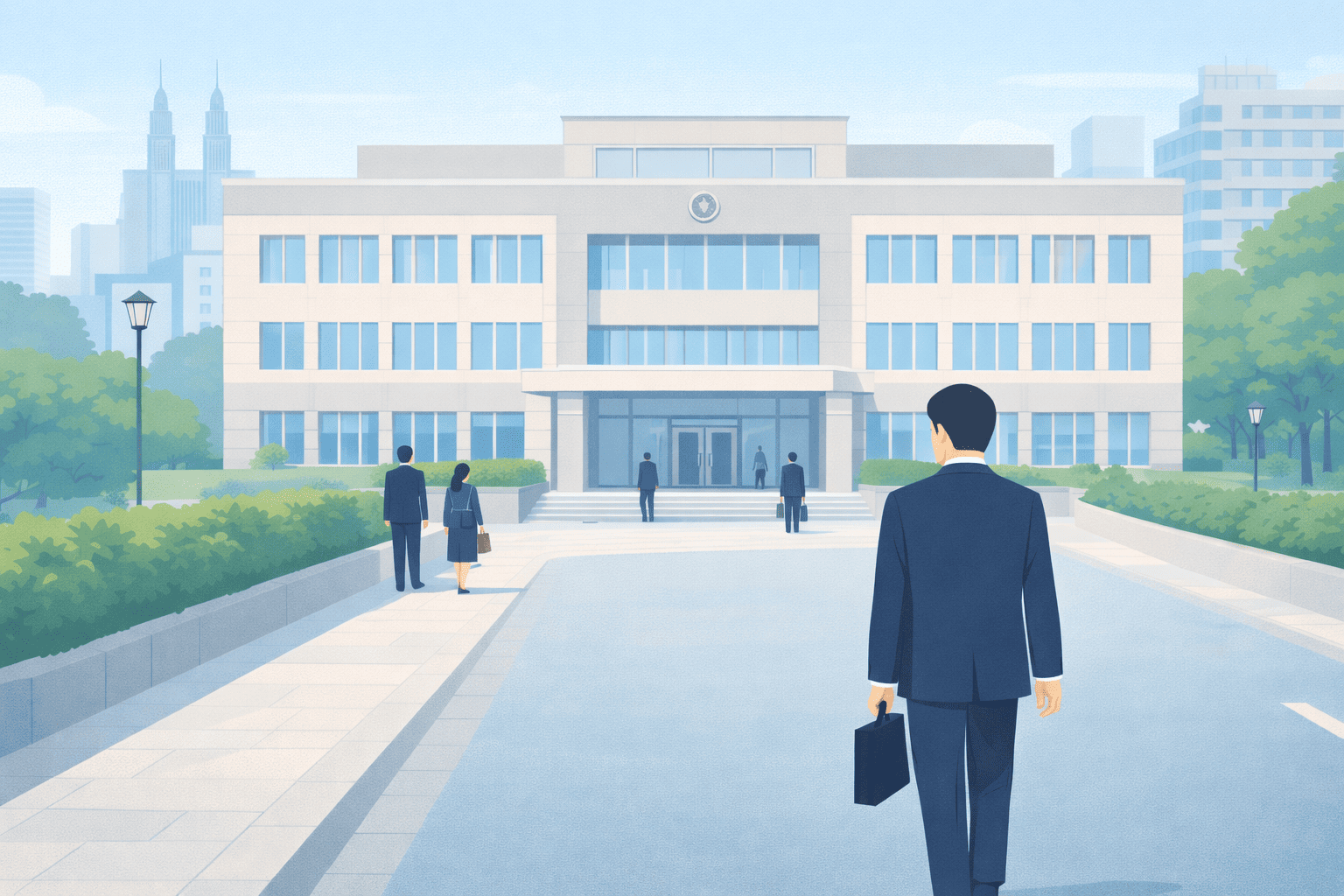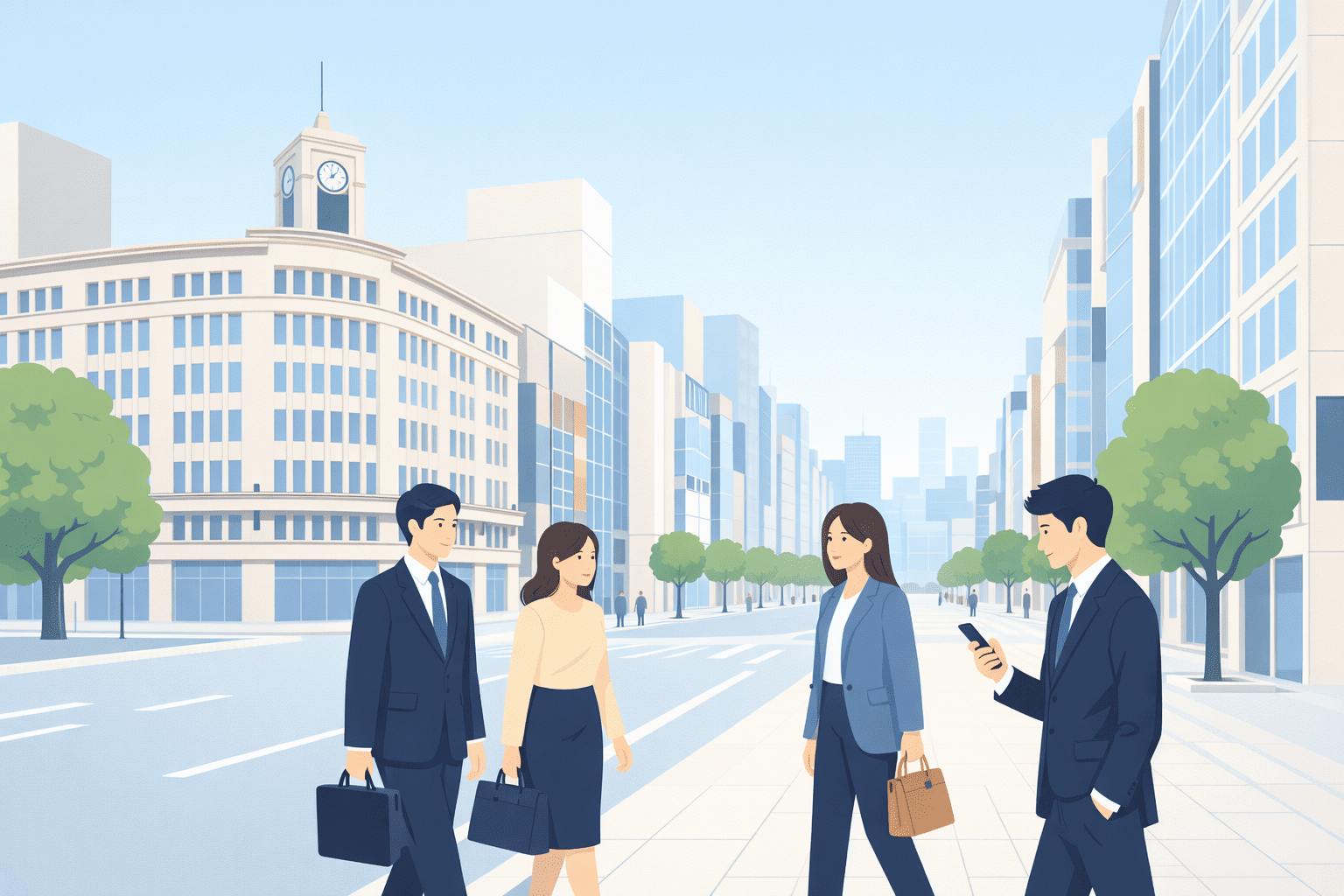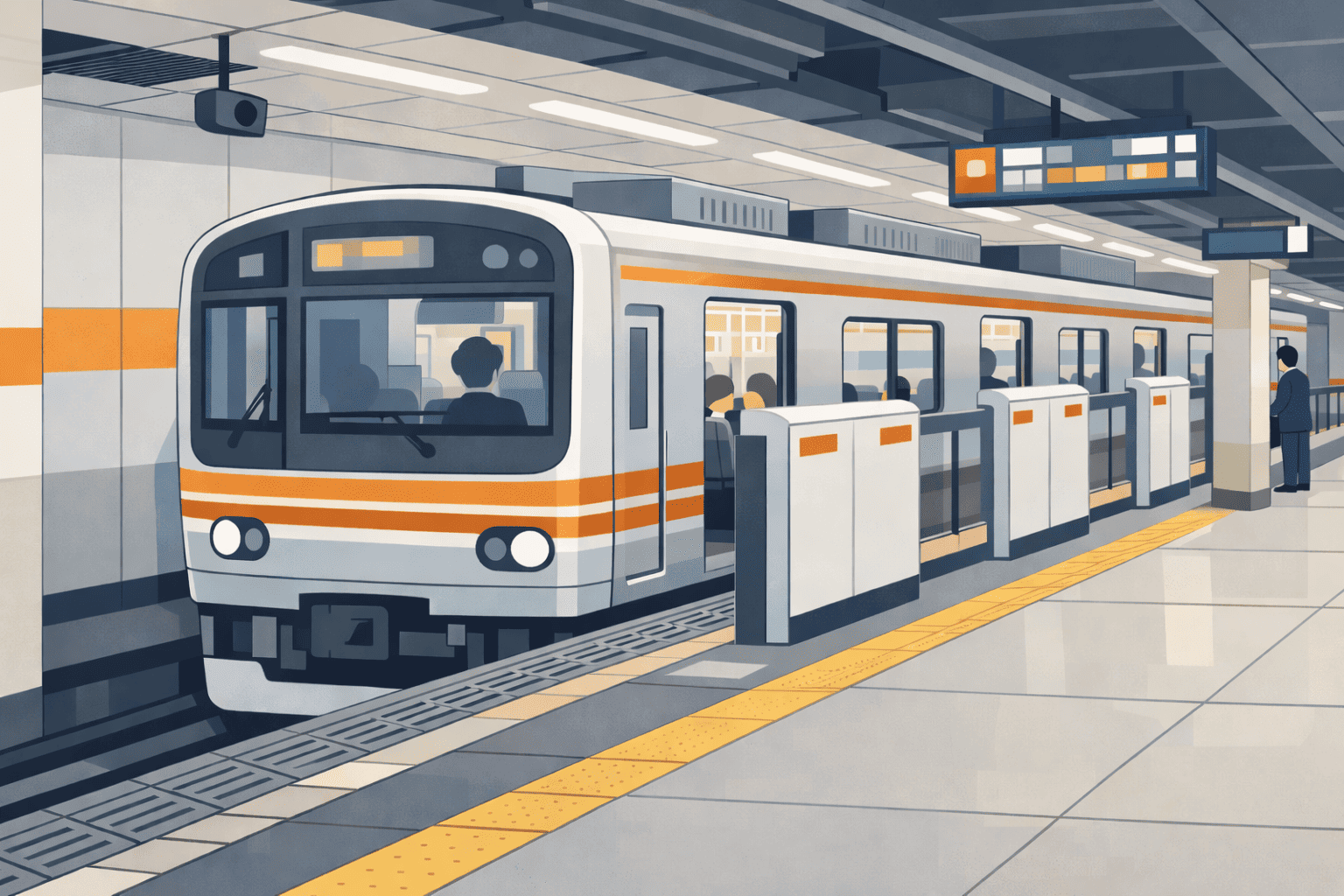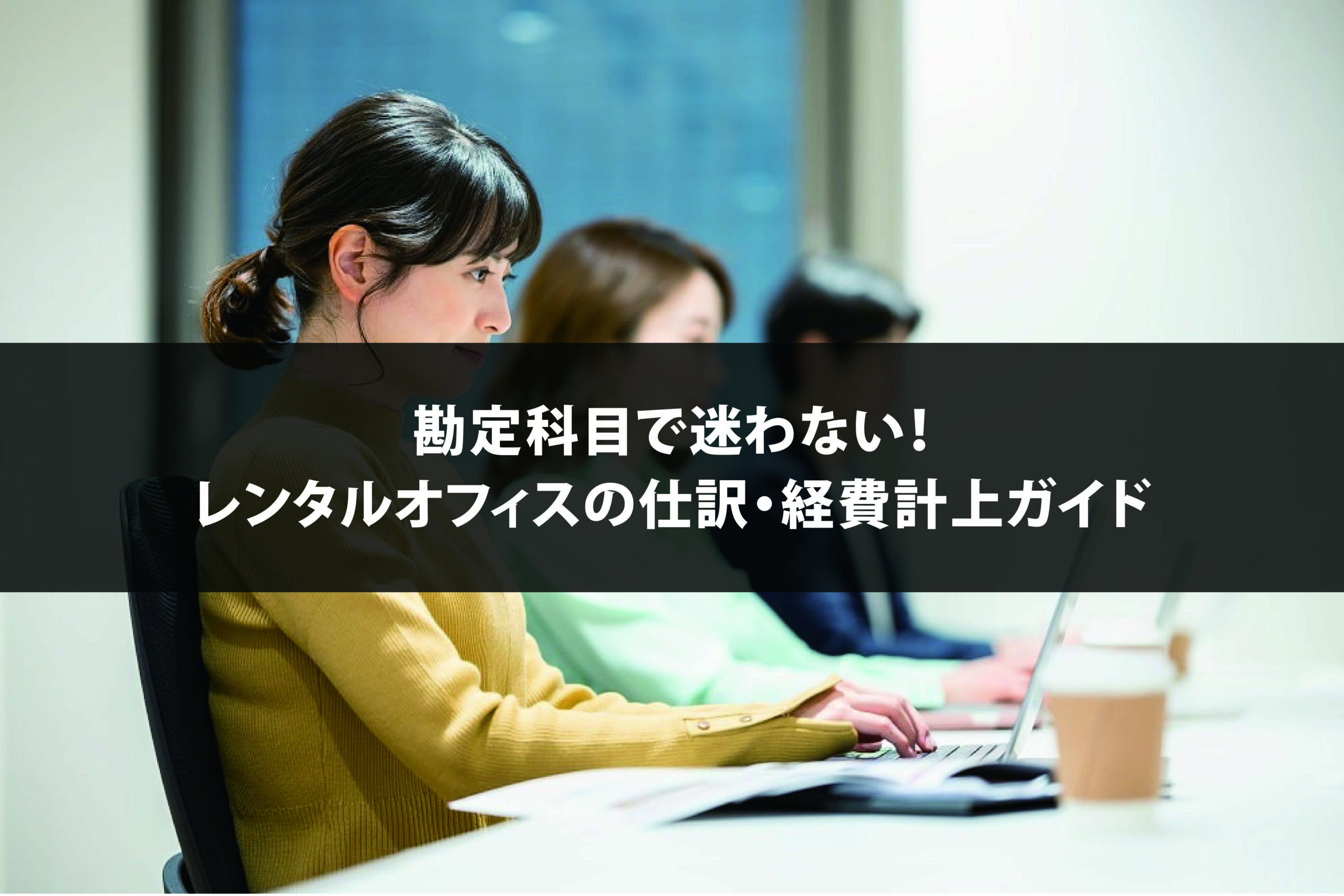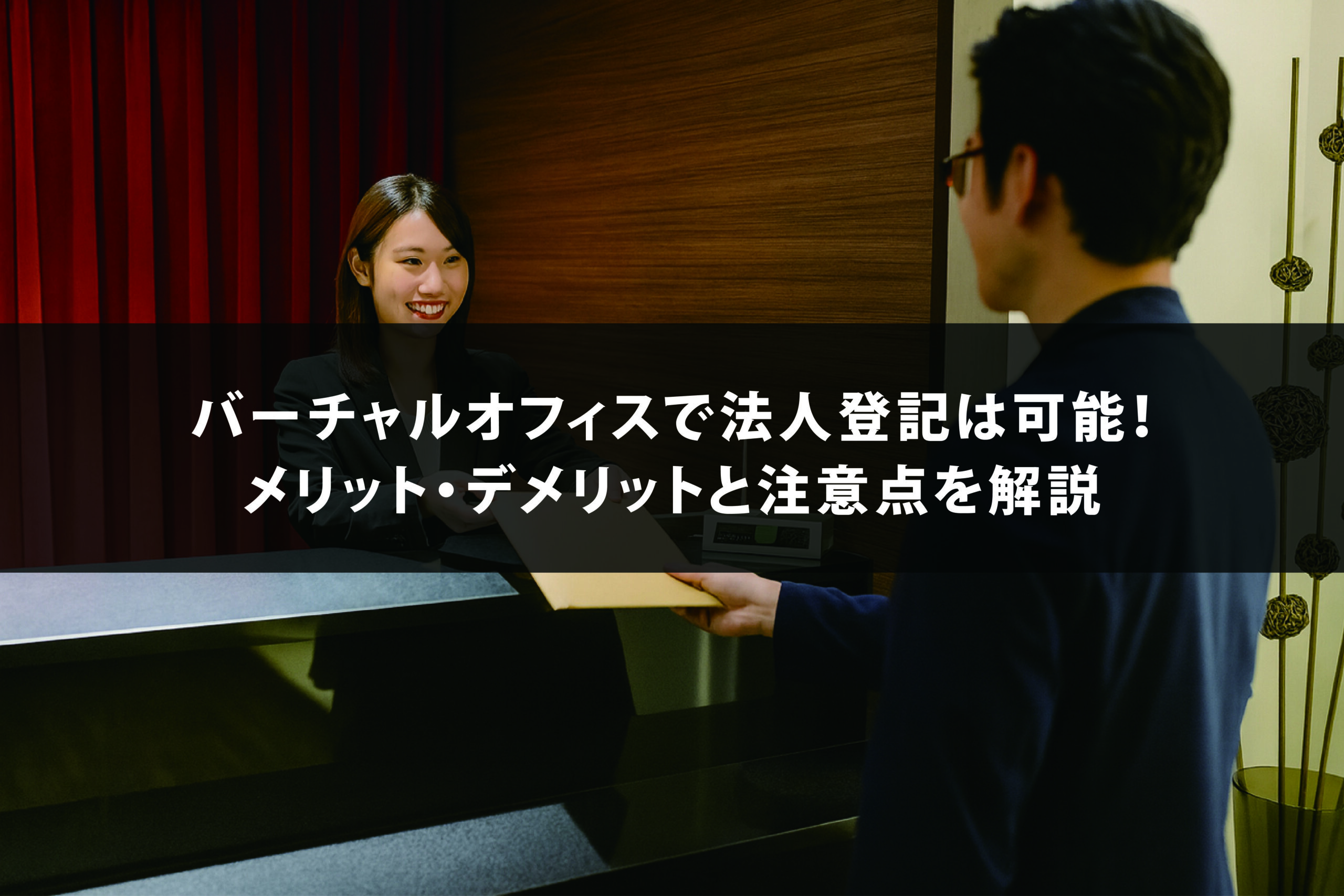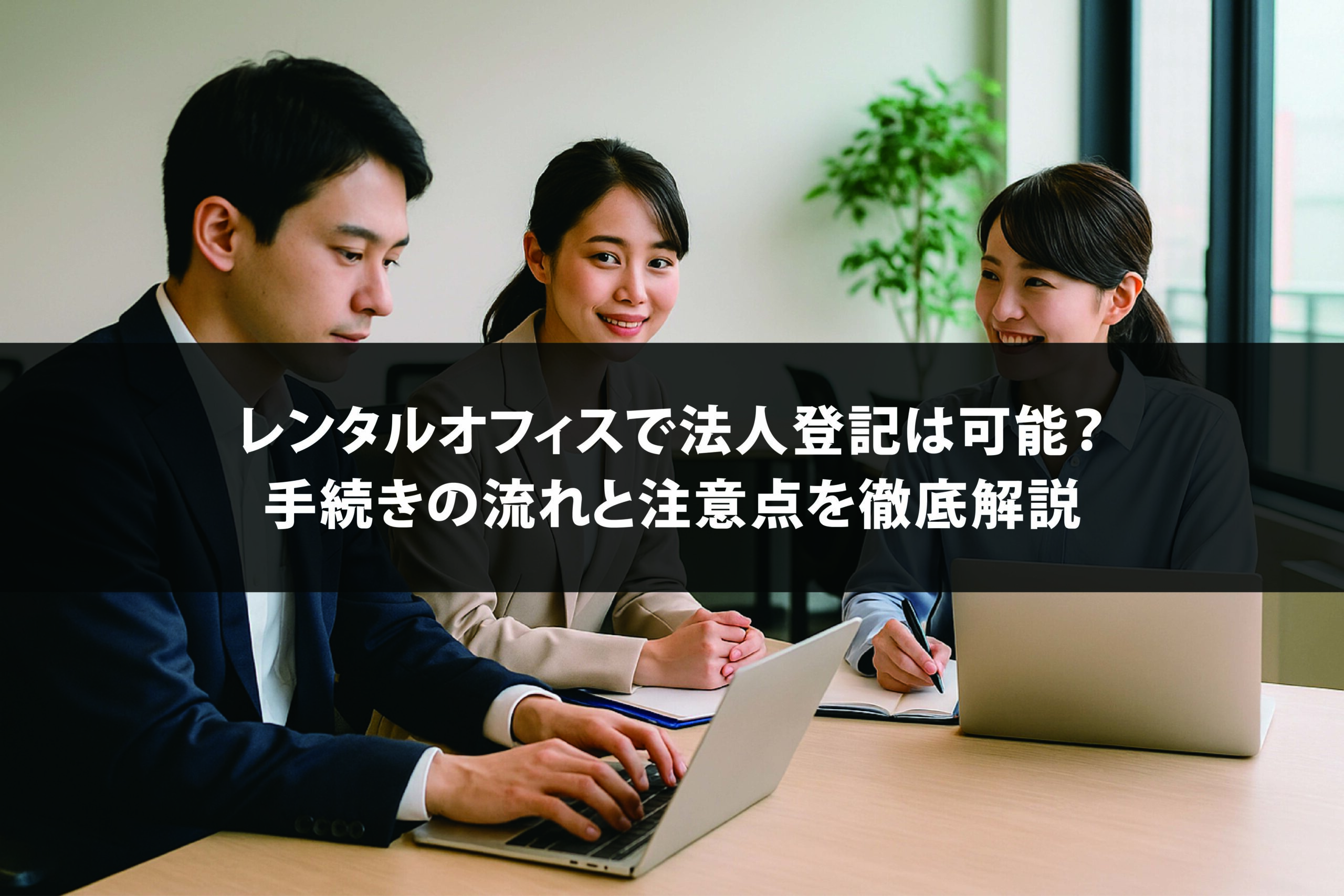コワーキングスペース費用の勘定科目ガイド|経費処理・仕訳・消費税まで徹底解説
2025年8月21日
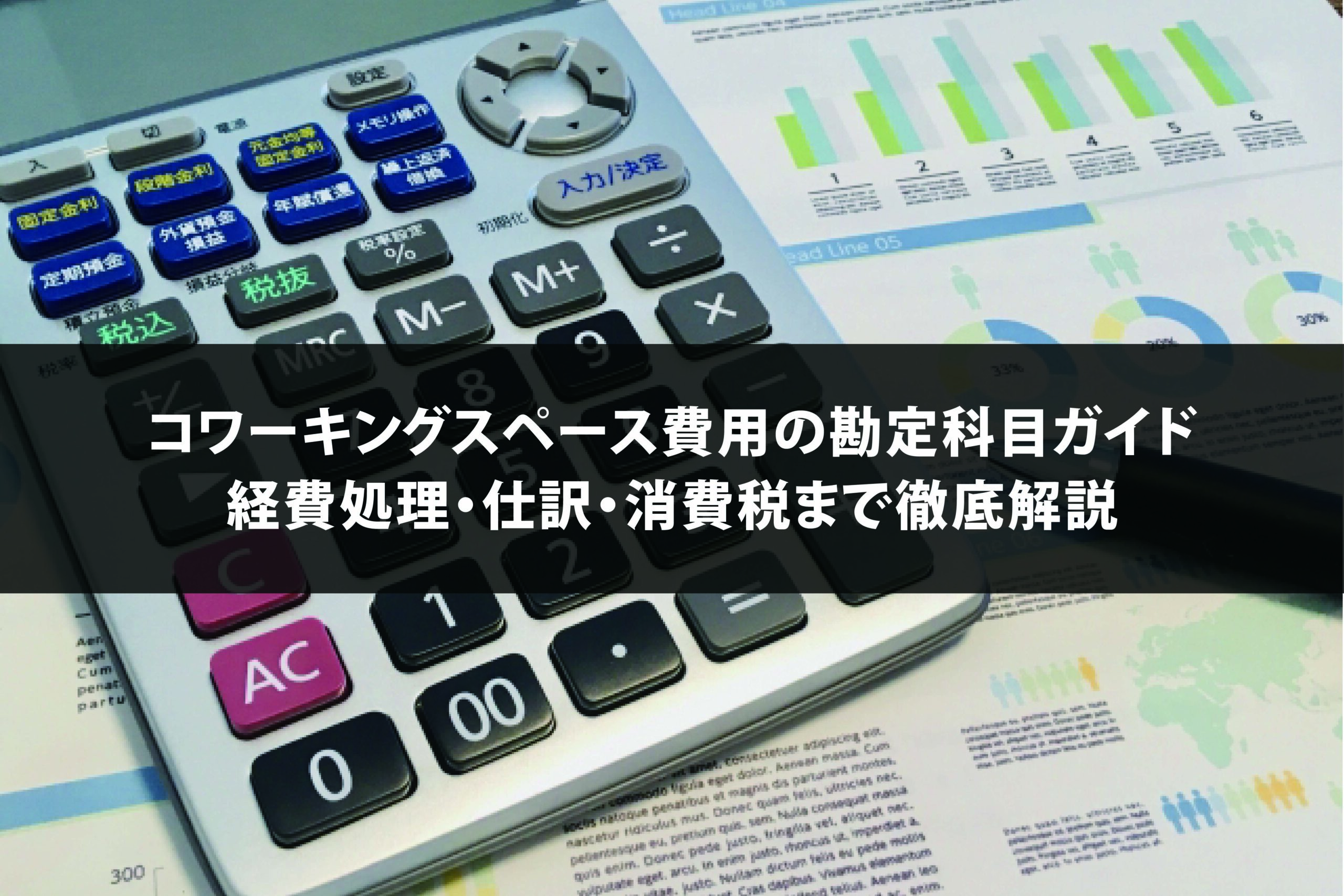
コワーキングスペースを利用している個人事業主やフリーランス、経理担当者の方からよくある疑問が「この費用はどの勘定科目で処理すればいいのか?」というものです。
月額利用料やドロップイン料金だけでなく、会議室の利用料や郵便転送サービスなど、コワーキングスペースにはさまざまな費用項目が発生します。
適切な勘定科目で仕訳をしないと、税務調査での指摘や経費否認のリスクにつながる可能性もあります。また、消費税の課税・非課税区分を誤ると、申告や控除に影響するケースもあるため注意が必要です。
本記事では、コワーキングスペースにかかる費用を正しく経費計上するために、基本的な勘定科目の考え方・仕訳例・消費税の扱い・注意点までを徹底的に解説します。
目次
コワーキングスペースの費用は経費になる?基本の勘定科目と考え方
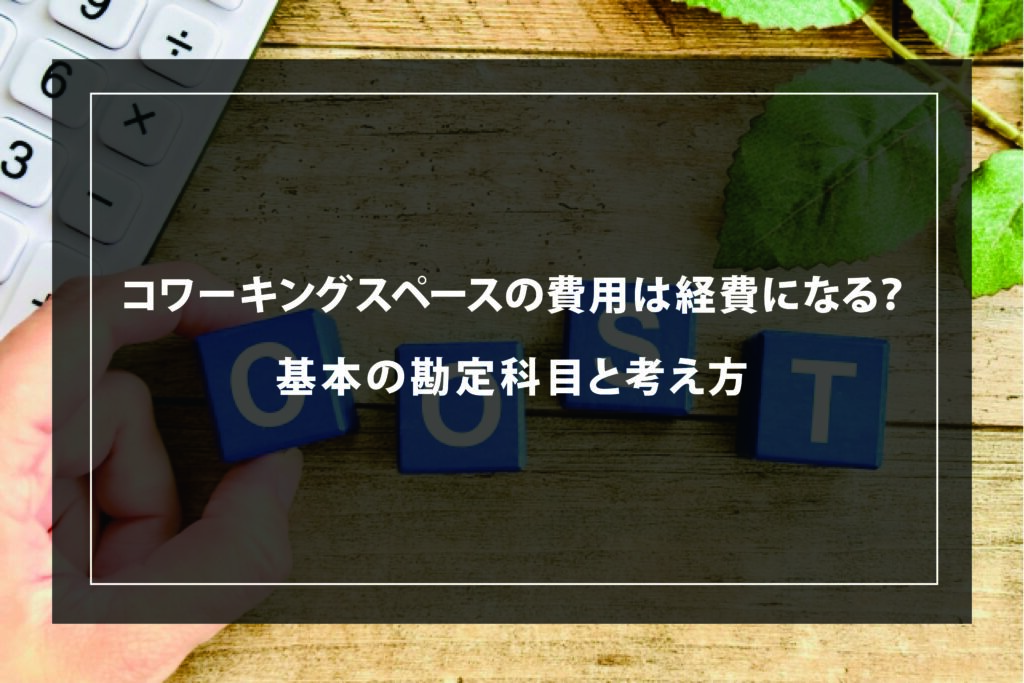
コワーキングスペースの利用料は基本的に経費計上できますが、利用目的によって勘定科目は異なります。
例えば、個室契約は「地代家賃」、フリー席は「賃借料」、会議室は「会議費」といった具合です。
科目選択は税務処理の一貫性にも関わるため、最初にルールを決めて継続することが重要です。ここでは、よく使われる勘定科目と判断の考え方を整理します。
よく使われる勘定科目(地代家賃/賃借料/会議費/旅費交通費など)
コワーキングスペースの利用料は、経費として計上することが可能です。
主に使用される勘定科目は以下のとおりです:
・地代家賃:オフィスを「不動産」として借りている性質が強い場合(個室契約など)
・賃借料:設備やサービス込みで利用している場合(フリー席や時間貸し)
・会議費:クライアントとの打ち合わせで会議室を利用した場合
・旅費交通費:出張先などで一時的にドロップイン利用した場合
用途別の判断基準(常設利用/ドロップイン/会議室利用)
勘定科目は「どう使ったか」によって変わります。
・常設利用(個室・固定席):継続的に使う拠点であれば「地代家賃」または「賃借料」
・ドロップイン利用:移動中や出張時の一時利用であれば「旅費交通費」
・会議室利用:取引先との打ち合わせ目的なら「会議費」
・自分だけの作業利用で短時間:仕訳の簡便性を考慮して「賃借料」で処理する場合もあります
勘定科目の違いが与える税務的インパクトとは?
「地代家賃」と「賃借料」はどちらを使っても経費計上は可能ですが、一度決めたら継続して同じ勘定科目で処理する必要があります。会計処理がブレると、税務調査時に「経費の一貫性」に疑問を持たれる可能性があるためです。
また、「会議費」や「旅費交通費」として計上すると費用性が認められやすい一方で、金額が大きい場合は用途の説明を求められることもあります。
会計上の原則と「継続適用」の考え方
会計処理では「継続適用」が基本原則とされています。つまり、同じ種類の支出は毎期同じ勘定科目で処理することが求められます。
例えば、1年目は「賃借料」、2年目は「地代家賃」と使い分けてしまうと不自然な処理と判断されかねません。契約内容や利用実態に応じて、最初に勘定科目を決め、以降は継続して処理することが信頼性ある帳簿づくりにつながります。
個人事業主がコワーキングスペースを経費計上する場合
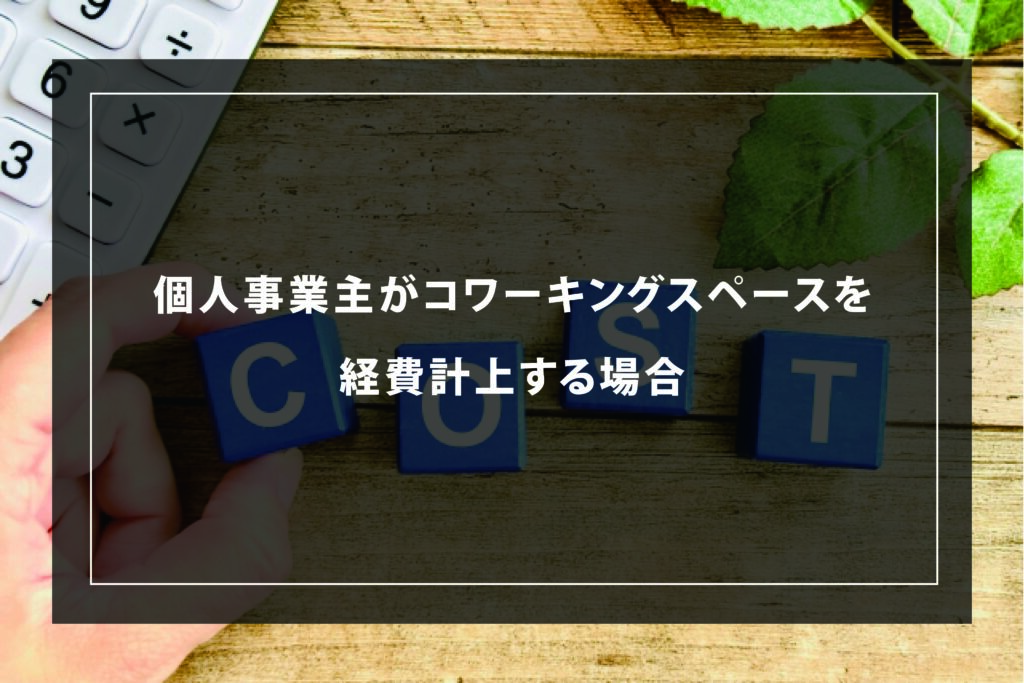
フリーランスや個人事業主にとって、コワーキングスペースの利用料は「事業に必要な支出」として経費計上できます。
しかし、契約形態や使い方によって勘定科目の選び方が異なり、さらに自宅との併用時には「家事按分」が必要になるなど、処理方法に迷いやすいポイントも多いのが実情です。
勘定科目の選び方(地代家賃/雑費/通信費など)
コワーキングスペースの利用料は、事業に必要な支出であれば経費にできます。
・地代家賃:専有の個室を契約している場合
・賃借料:フリー席や設備込みの契約形態
・雑費:少額の一時利用(ドロップインなど)
・通信費:インターネット回線使用料を別途支払う場合 どの勘定科目にするかは契約形態や利用実態に応じて判断します。
家事按分の考え方と注意点
自宅兼事務所として利用している場合、光熱費や通信費と同様に「家事按分」が必要です。
例えば、1日の作業のうち6時間を事業利用、2時間を私的利用に充てている場合、75%を経費計上できます。
ただし、按分割合は合理的な基準(時間・面積・使用実態など)で算定し、根拠を残すことが重要です。税務調査時には説明できる資料を準備しておきましょう。
確定申告の際の記載例(freee/弥生など)
クラウド会計ソフトでは、入力画面から勘定科目を選択するだけで仕訳が完了します。
・freee:「支出」→「勘定科目を地代家賃に設定」→「備考にコワーキングスペース利用料と記載」
・弥生会計オンライン:「経費入力」→「地代家賃/賃借料を選択」→「摘要欄に施設名を入力」 仕訳を一度設定すれば、自動で学習され、次回以降は入力がスムーズになります。
会計アプリやクラウド会計での入力実務
コワーキングスペースの利用料は、銀行引き落としやカード決済が多いため、クラウド会計との連携で自動仕訳化が便利です。
ただし、自動連携だけでは「どの勘定科目にするか」まで完全に正しくは判断されません。初回に正しい勘定科目を登録しておき、以降は「学習機能」を活用すると入力の手間を大幅に削減できます。
法人がコワーキングスペースを利用する場合の会計処理
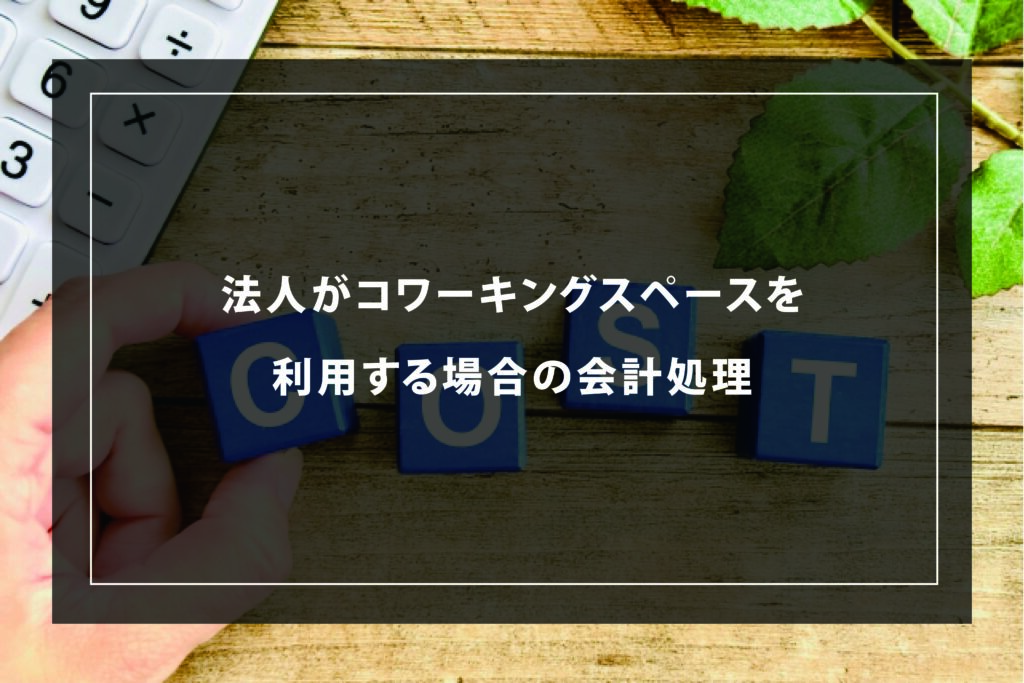
法人がコワーキングスペースを利用するケースは増えていますが、会計処理は個人事業主とは異なり注意が必要です。
契約内容や利用者が役員か従業員かによって、勘定科目を「賃借料」「福利厚生費」などに分ける必要があります。
勘定科目の基本方針(賃借料/福利厚生費など)
法人がコワーキングスペースを契約する場合、基本的には「賃借料」または「地代家賃」で処理します。
ただし、従業員がリモート勤務時に利用するなど福利厚生的な性質が強い場合は「福利厚生費」で処理することも可能です。契約内容や利用実態に応じて、最も適切な科目を選びましょう。
利用者が役員か従業員かで変わる処理方法
利用者が役員の場合、その支出が「役員個人のため」と判断されると経費性を否認される可能性があります。役員利用でも業務上必要性が明確に示せる場合は「賃借料」処理が可能ですが、証拠資料(利用目的や会議記録など)を残しておくと安心です。
一方、従業員の利用であれば業務に必要な支出と認められやすく、「賃借料」または「福利厚生費」での処理が一般的です。
賃貸オフィスとの違いと処理分けの注意点
通常の賃貸オフィス契約は「不動産賃貸借契約」として取り扱うため「地代家賃」で処理します。これに対し、コワーキングスペースは「サービス利用契約」としての性質が強く、机・ネット・受付などが一体化しているため「賃借料」処理が多く見られます。
契約書や請求書の記載内容によっても判断が変わるため、契約内容をよく確認して勘定科目を統一することが重要です。
チーム/部署単位で使う場合の配賦方法の工夫
複数人で利用する場合、経費を部門別に按分する必要が出てきます。
例えば:
・営業部が月10回利用、開発部が月5回利用 → 利用頻度に応じて配賦
・役職別に利用枠を設定している → 利用人数で均等配分 クラウド会計や管理表で利用状況を記録し、合理的な基準で費用を配賦すると経理処理がスムーズになります。
コワーキングスペースと消費税・インボイス制度の実務対応
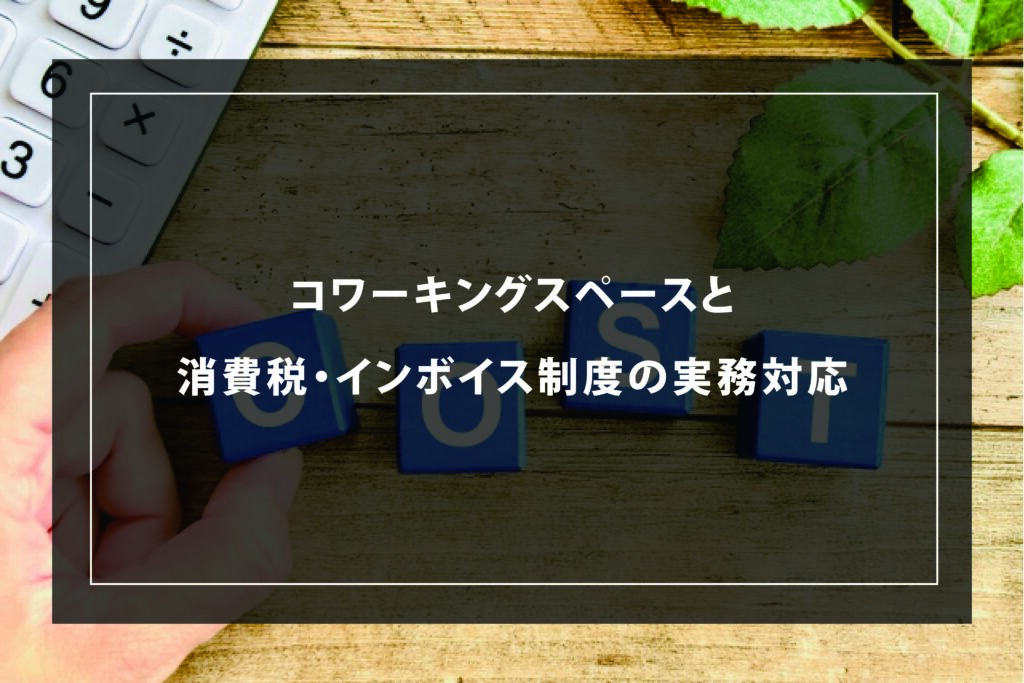
コワーキングスペースの利用料は原則として消費税の課税対象です。
また、2023年開始のインボイス制度により、仕入税額控除を受けるには適格請求書の保存が必須となりました。
課税対象と非課税(会議費との違いなど)
コワーキングスペースの利用料は、基本的に 消費税の課税対象 です。
例えば月額利用料や時間貸し利用料は「サービスの提供」とみなされるため課税されます。一方で、会議室利用を「会議費」として処理する場合も内容は同じく課税対象です。
注意すべきなのは、敷金や保証金など返還される預け金は不課税 という点です。
軽減税率の対象になることはある?
コワーキングスペースの利用料やオプションサービスは、軽減税率の対象外です。
ただし、施設内で提供されるドリンクや軽食が「持ち帰り可能な飲食物」として提供される場合、その部分だけ軽減税率(8%)が適用される可能性があります。もっとも、多くの施設ではサービス全体をまとめて課税(10%)しているケースが大半です。
インボイス対応している施設かの確認ポイント
2023年10月からのインボイス制度により、仕入税額控除を受けるためには 適格請求書発行事業者 からの請求書が必要です。
契約前に以下を確認しましょう:
・請求書に「適格請求書発行事業者登録番号」が記載されているか
・領収書・請求書が電子データでも保存できるか
・利用明細(会議室利用などオプションも含む)が分かれて記載されるか
仕入税額控除のための要件と保存書類
法人・個人事業主が仕入税額控除を受けるには、インボイス(適格請求書)の保存 が必須です。
保存方法としては紙だけでなく、電子帳簿保存法に対応したクラウド会計ソフトやスキャナ保存も可能です。
また、摘要欄に「コワーキングスペース利用料」など具体的な利用内容を記載しておくと安心です。税務調査時にスムーズに説明できます。
勘定科目の選定・仕訳で迷ったときの判断基準と実例
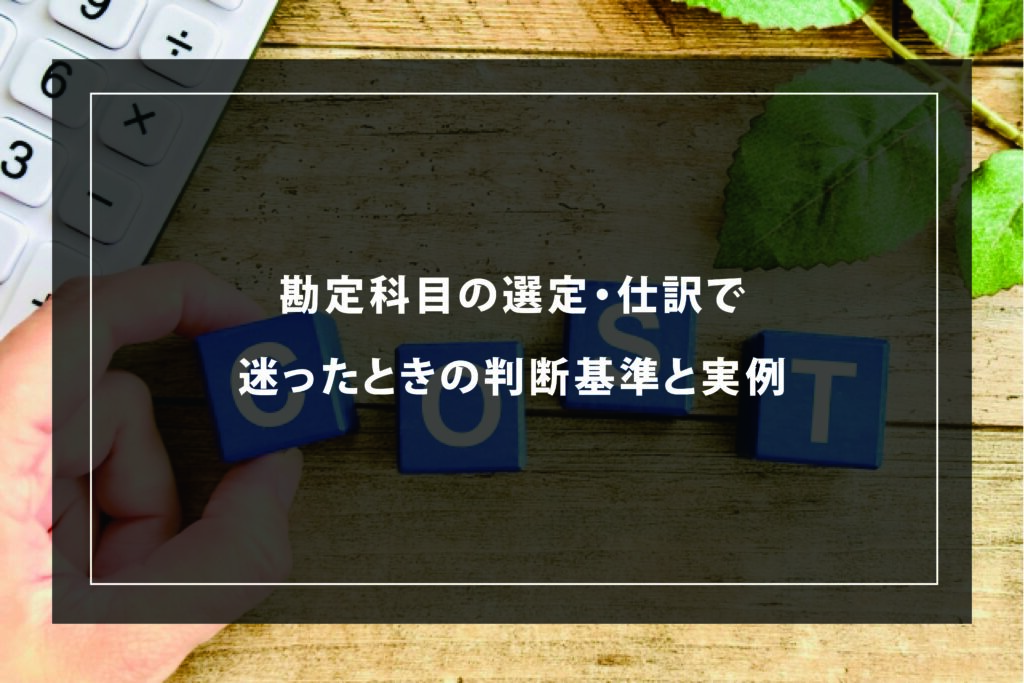
コワーキングスペースの費用は、契約形態や利用目的によって仕訳方法が変わります。
「地代家賃?それとも賃借料?」と迷ったときのために、会計士や税理士がよく使う処理例や業種別の判断基準を整理しました。
会計士・税理士がよく使う処理例
実務上、会計士や税理士はコワーキングスペースの利用料を「賃借料」または「地代家賃」で処理するケースが多いです。
・フリー席やサービス込み契約 → 「賃借料」
・個室契約など不動産要素が強い場合 → 「地代家賃」 少額のドロップインは「雑費」、会議室のみの利用は「会議費」とすることもあります。基本は契約書・請求書の性質に合わせて判断します。
利用目的別の仕訳例一覧
・月額利用料 30,000円をカード払い 借方:賃借料 30,000円 貸方:未払金(カード) 30,000円
・出張先でのドロップイン利用 2,000円を現金払い 借方:旅費交通費 2,000円 貸方:現金 2,000円
・クライアントとの打ち合わせで会議室を5,000円利用 借方:会議費 5,000円 貸方:普通預金 5,000円
業種別の分類例(士業/IT/フリーランスなど)
・士業(行政書士・税理士など):来客対応のため「地代家賃」処理が多い
・IT系フリーランス:自分の作業場所として利用するため「賃借料」処理が一般的
・クリエイター:ドロップインや短期利用も多く「雑費」処理にする場合あり 業種によって利用形態が異なるため、用途に応じて使い分ける柔軟さが求められます。
税務署・会計ソフトのヘルプページを活用しよう
判断に迷ったときは、税務署への問い合わせや、freee・弥生などクラウド会計ソフトのヘルプページを参照するのが安心です。
ソフトのヘルプには「コワーキングスペースは賃借料として処理」といった具体例が掲載されている場合もあり、実務判断のヒントになります。
まとめ|自社に合った勘定科目を選んで正しく経費処理しよう
コワーキングスペースの利用料は、契約形態や用途に応じて「地代家賃」「賃借料」「会議費」「雑費」など複数の勘定科目で処理できます。大切なのは、一度決めたら継続して同じ処理を続けることです。会計処理の一貫性があれば、税務調査でも不自然と見なされにくく、安心して経費にできます。
また、インボイス制度の開始により、仕入税額控除を受けるには適格請求書の保存が欠かせません。契約前に「インボイス対応施設か」「明細が発行されるか」を確認しておきましょう。
迷ったときは会計ソフトのヘルプや税理士への相談を活用することも有効です。正しい勘定科目を選び、適切に仕訳を行うことで、コワーキングスペースを安心して経費計上でき、事業運営の効率化にもつながります。
nexのTHE HUBシリーズは、東京・神奈川・名古屋・京都・大阪など、全国80拠点以上でコワーキングスペースを展開中。
気になるエリアに拠点があるか、ぜひ探してみてください。

writing by:nex株式会社 事業企画室
nexでは、レンタルオフィス・コワーキングスペース・バーチャルオフィスに関する情報を、コラム記事を通じてわかりやすく発信しています。
自社サービスに限らず、これから働き方を見直したい方・新しい拠点を検討している方に役立つ業界情報をお届けしていきます。