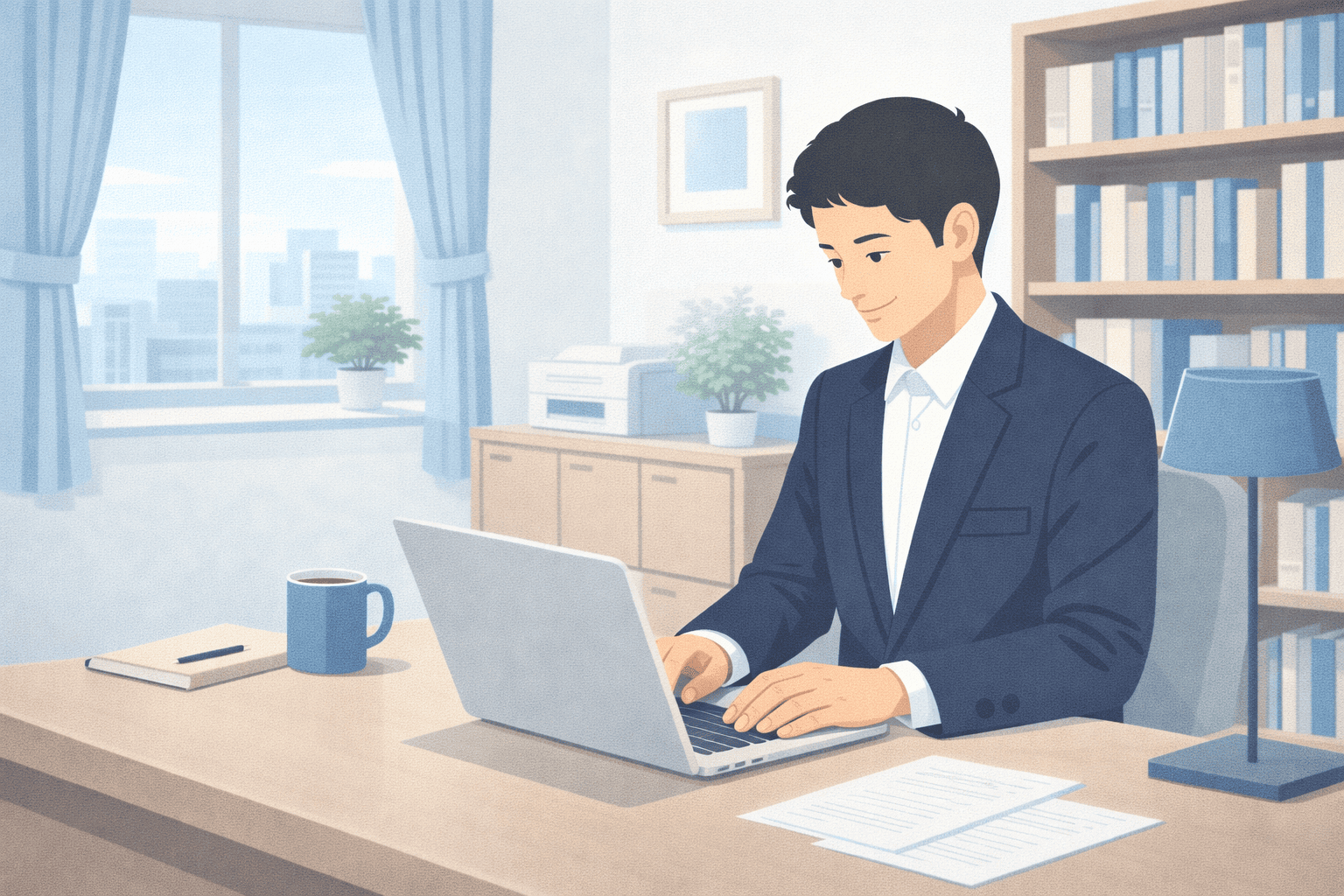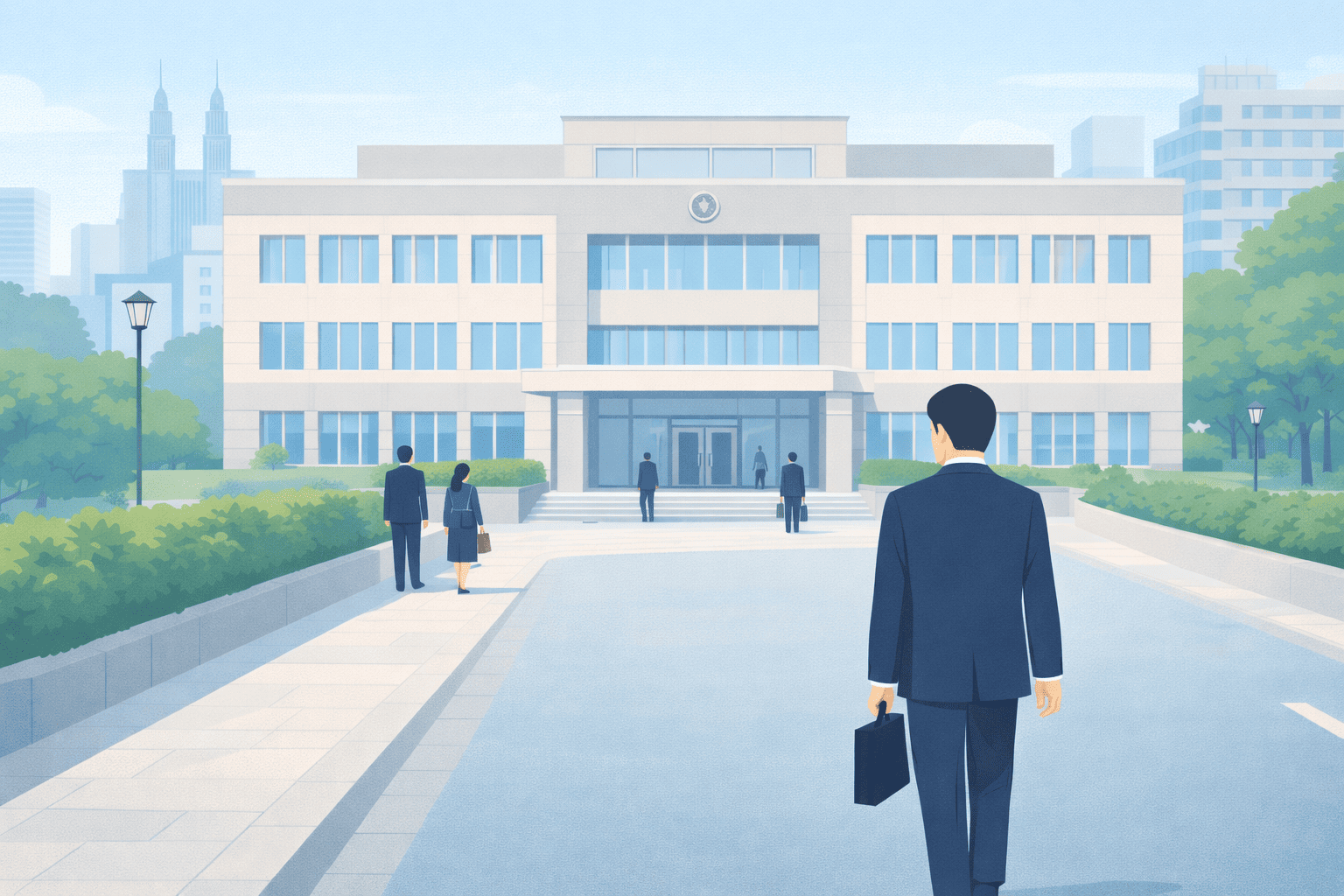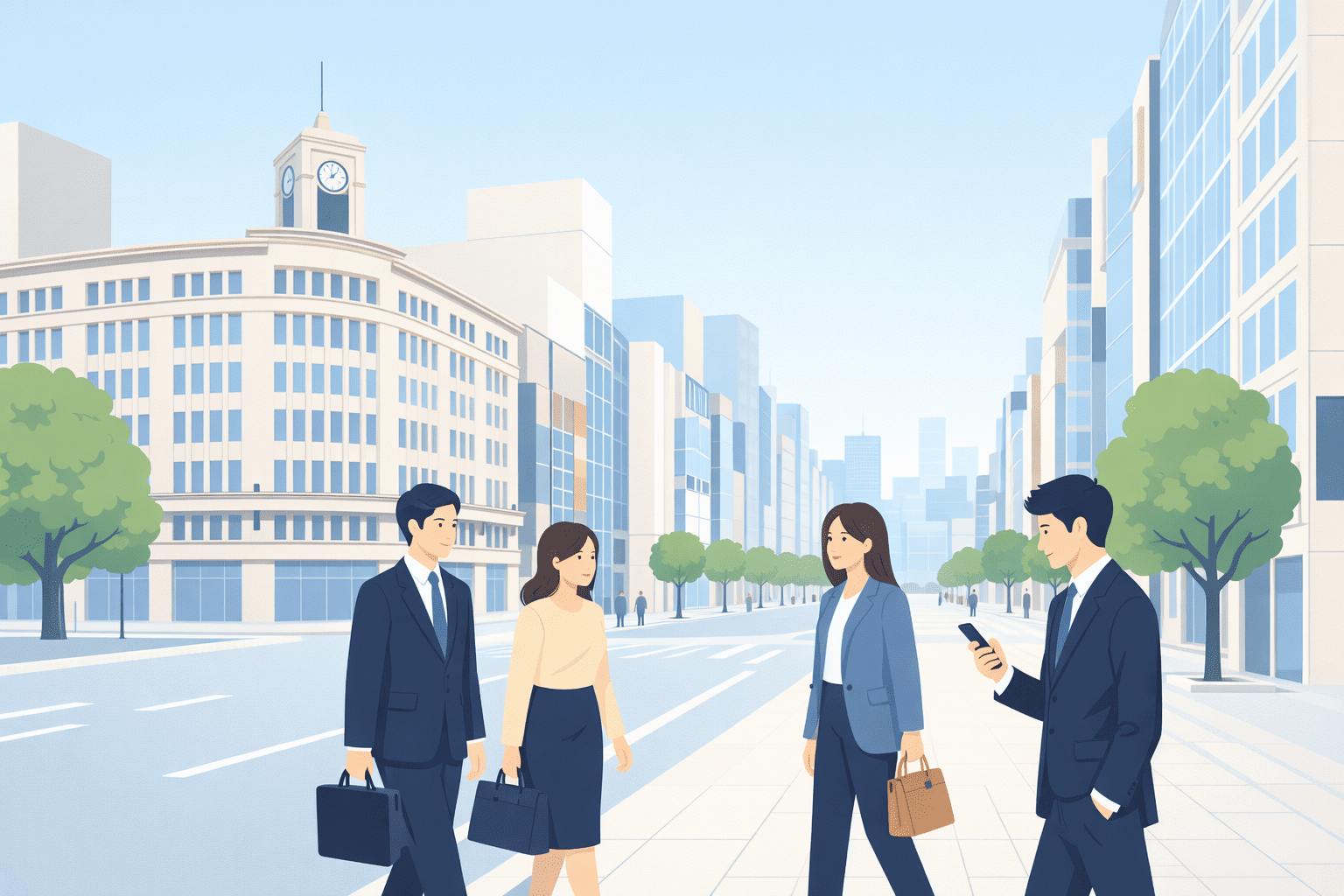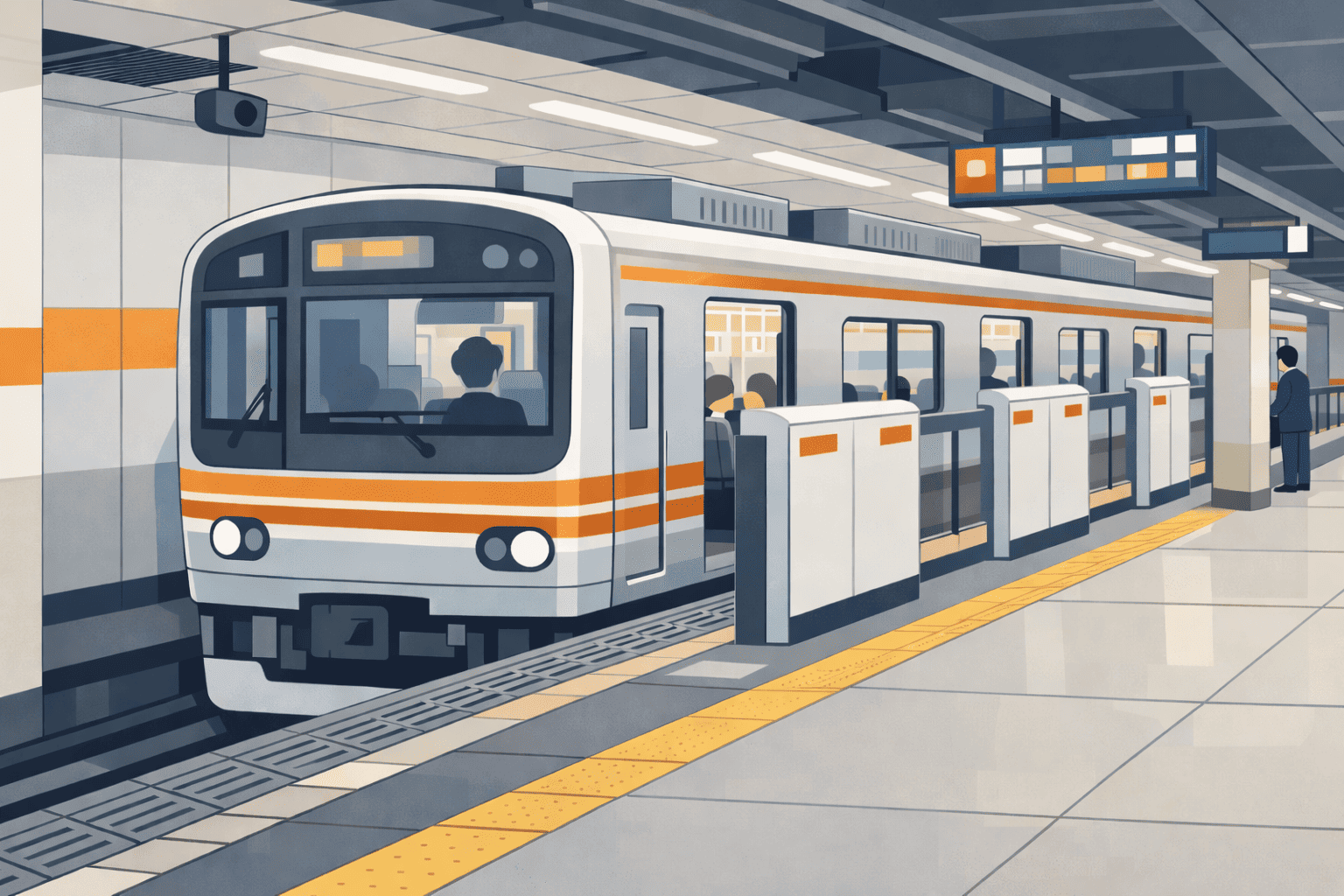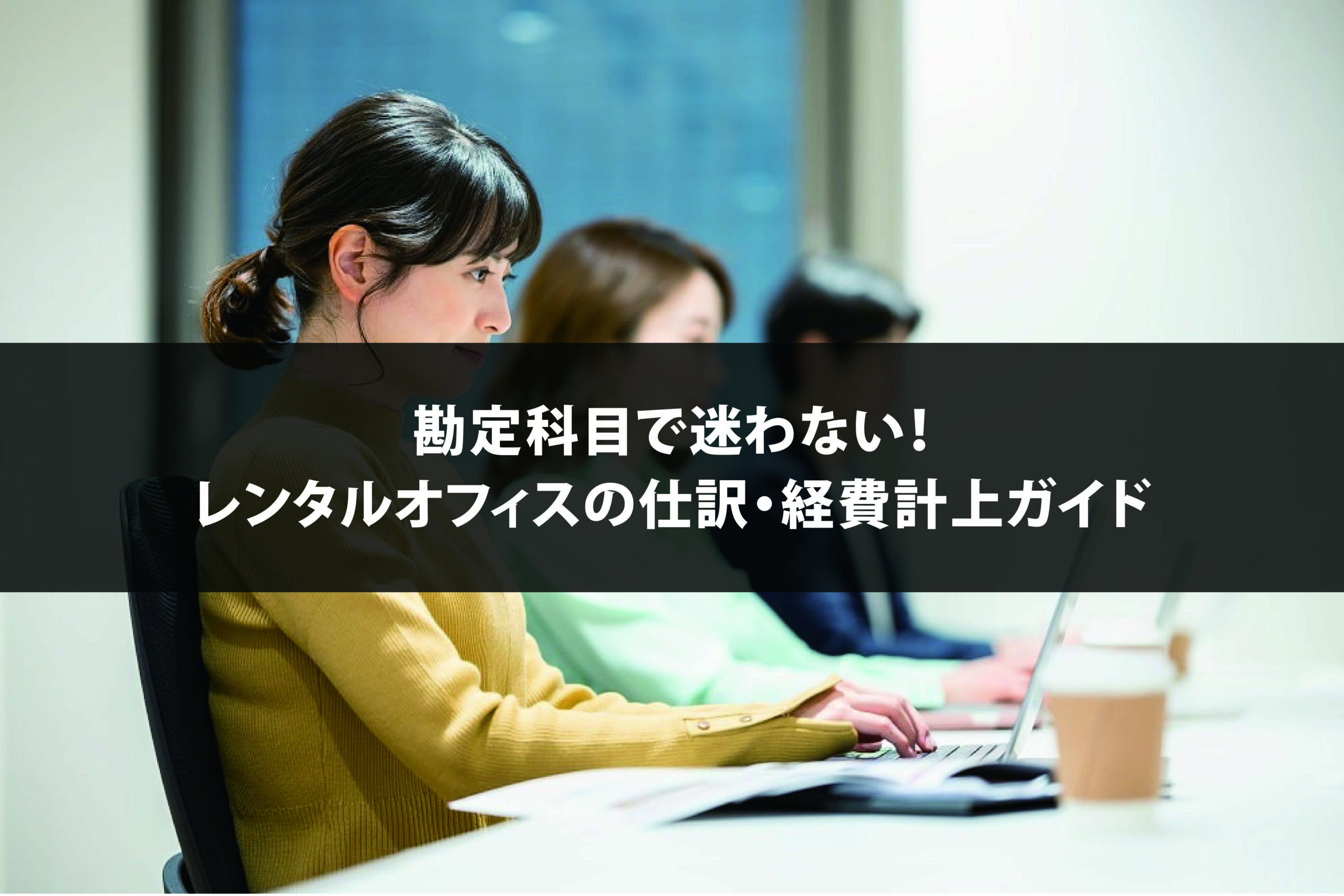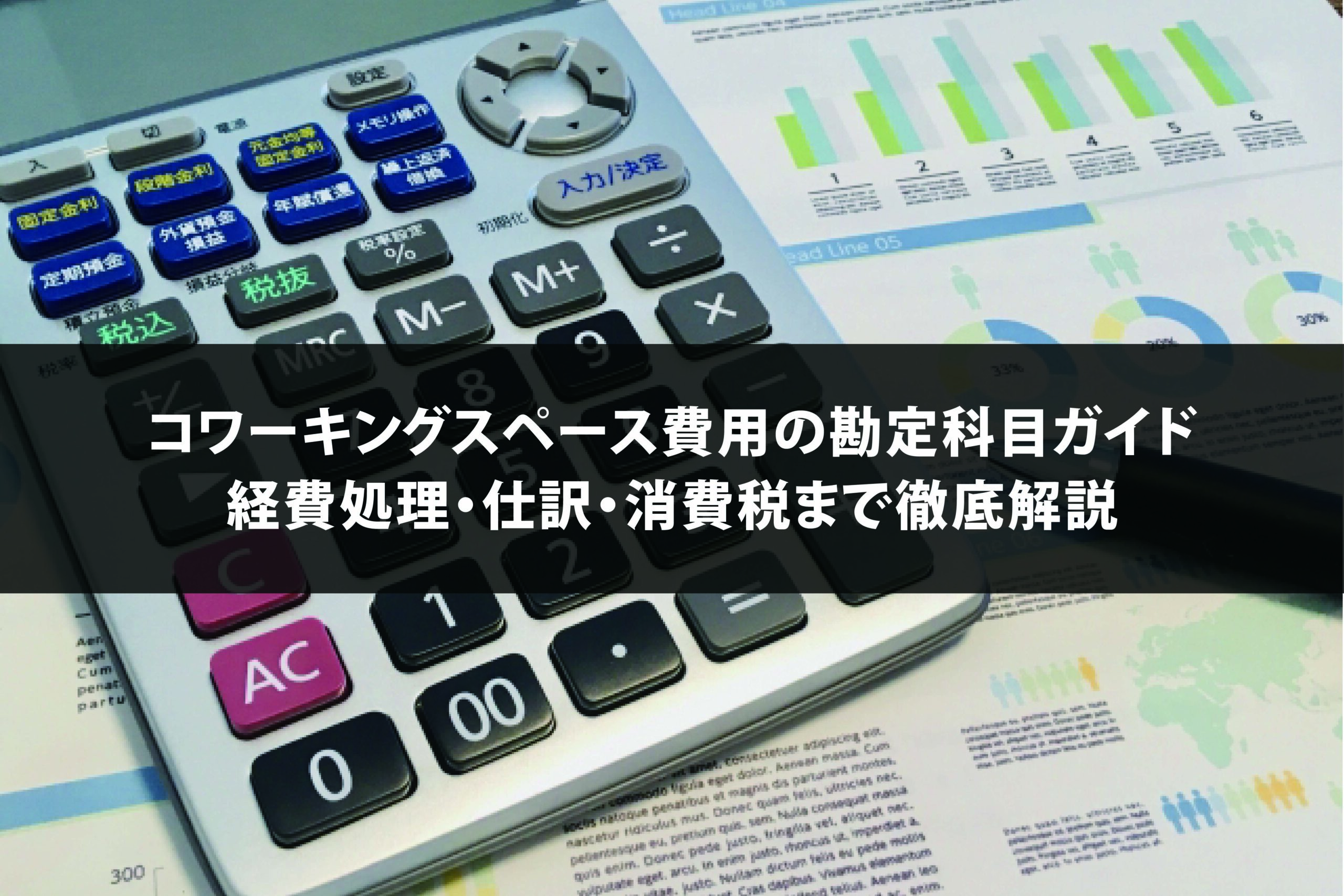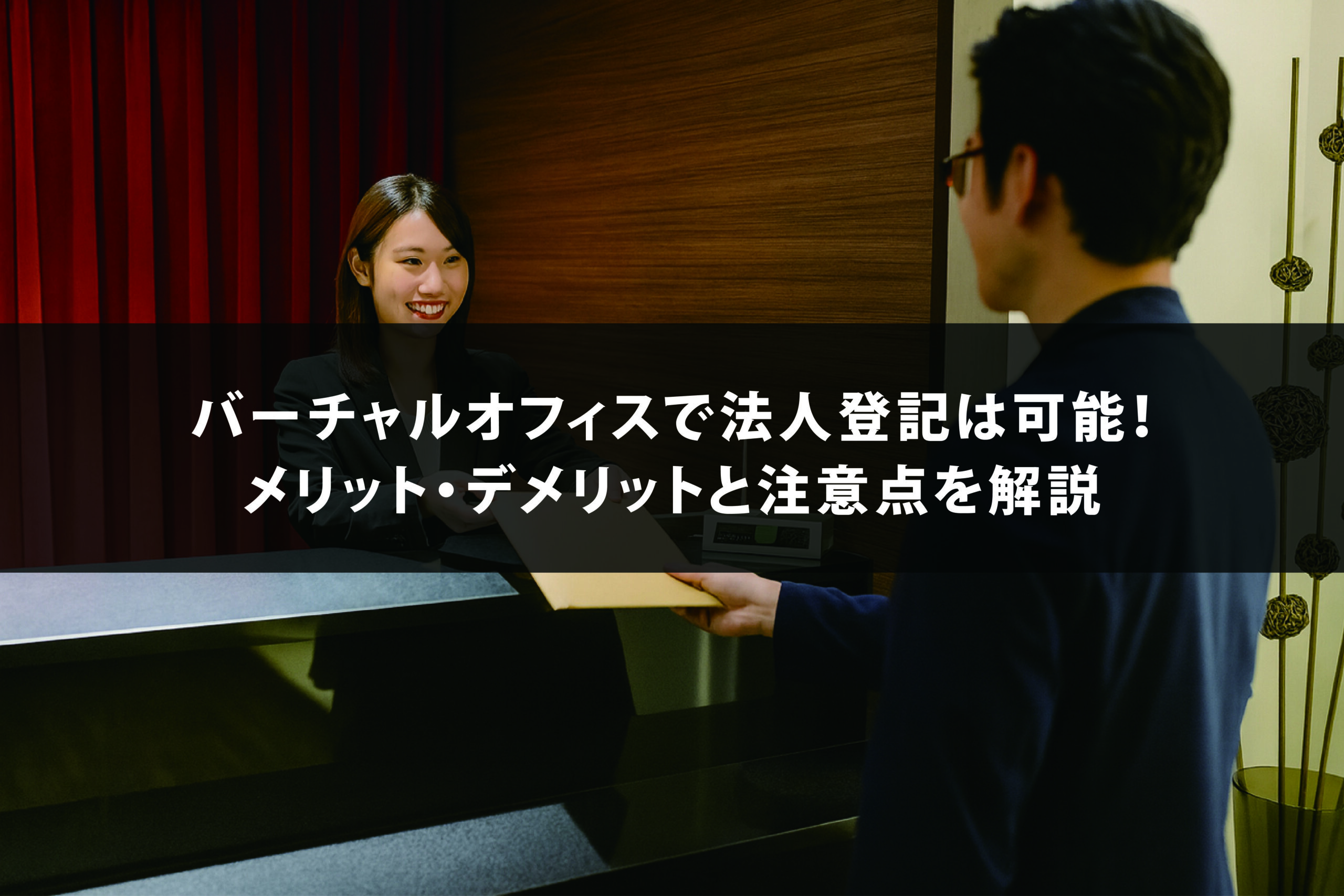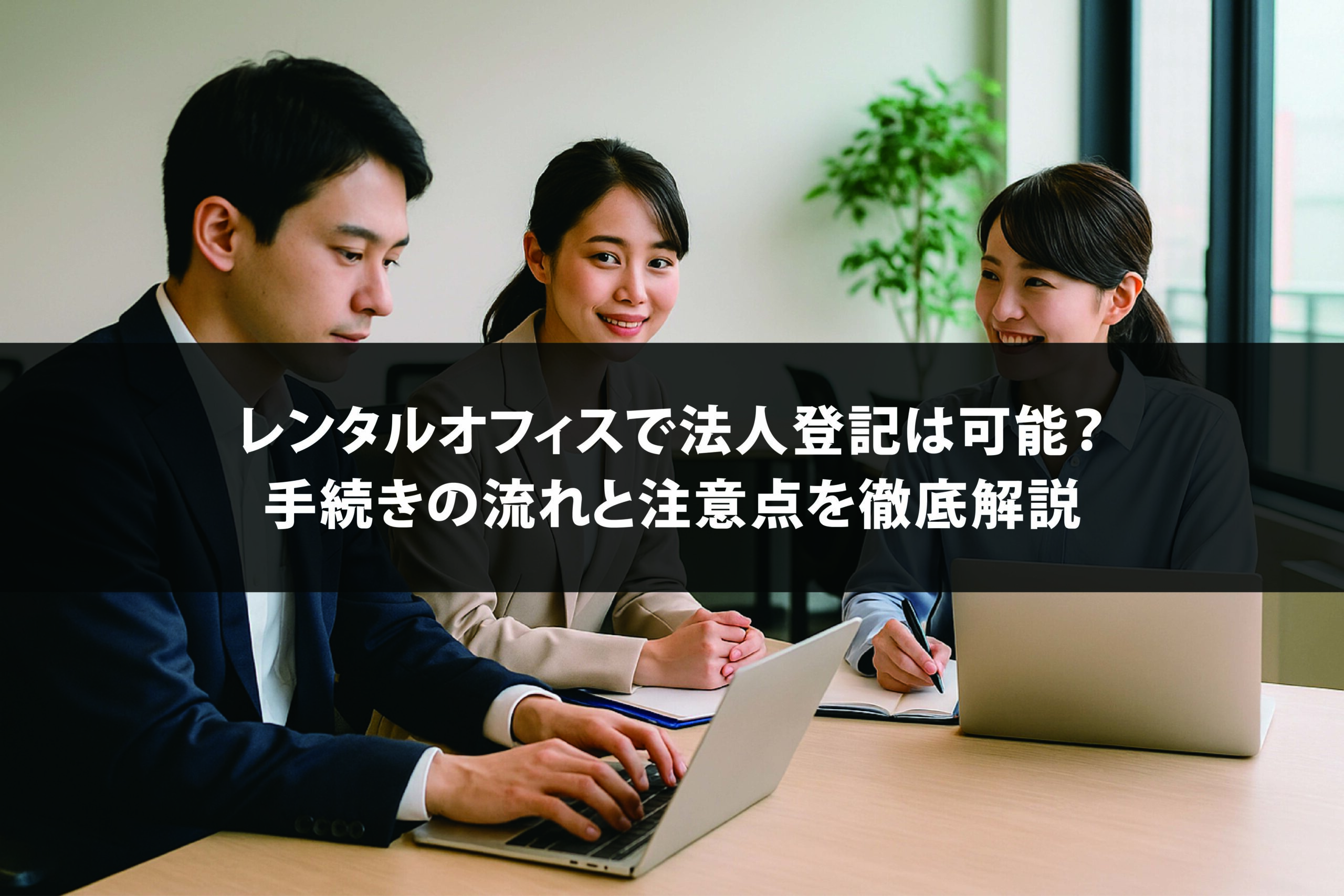スタートアップの第一歩に!バーチャルオフィスのメリットと選び方ガイド
2025年9月10日
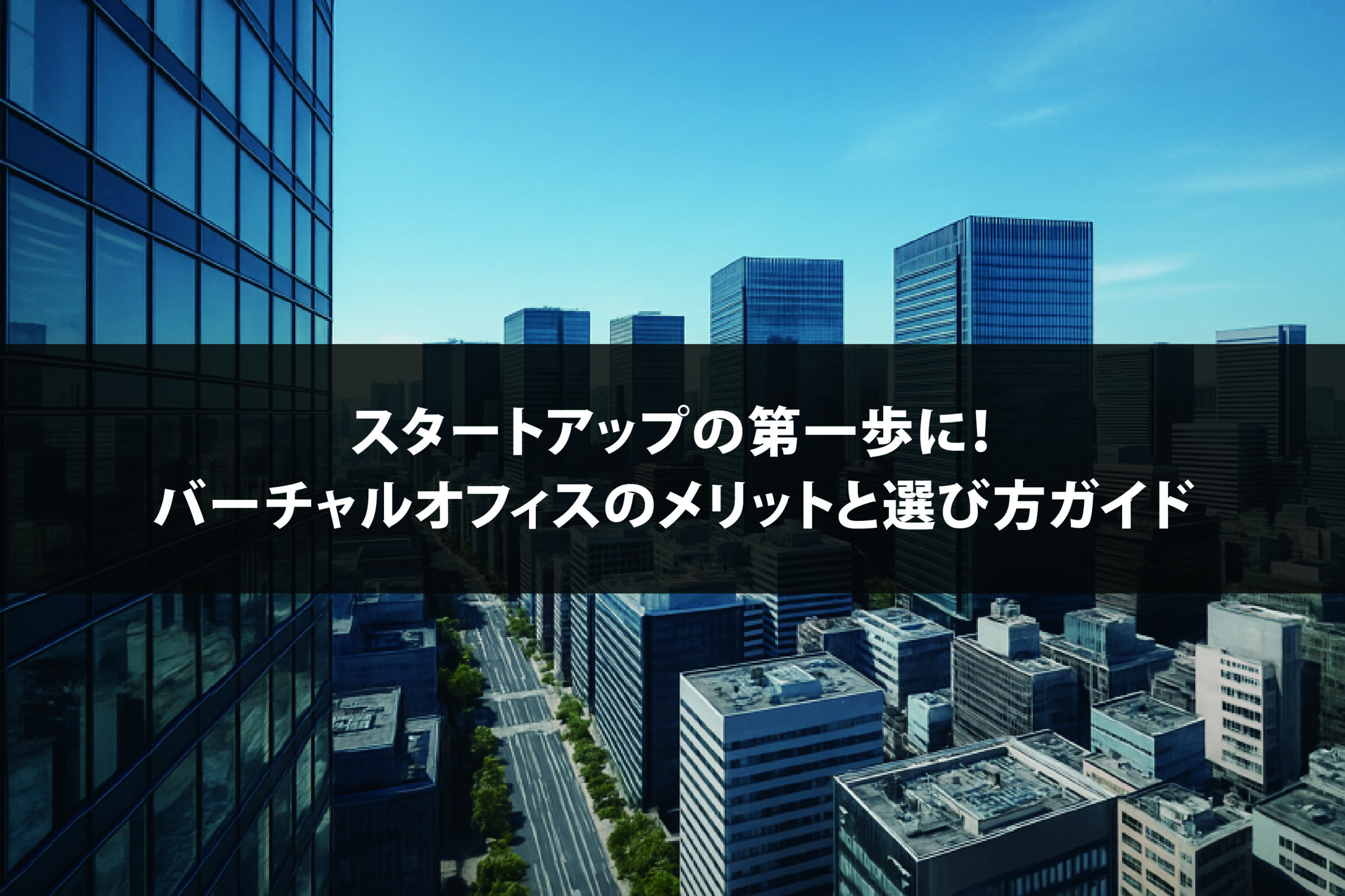
スタートアップとして事業を始めるとき、「どこにオフィスを構えるか」は信頼性やコストに直結する重要なポイントです。中でも注目されているのが、コストを抑えながら一等地の住所を活用できる「バーチャルオフィス」という選択肢。登記や郵便対応など、必要な機能だけを備えたこの仕組みは、柔軟性と機動力が求められる起業初期にぴったりです。本記事では、バーチャルオフィスの基本から、メリット・注意点・選び方までをわかりやすく解説します。
目次
バーチャルオフィスとは?その基本を理解する
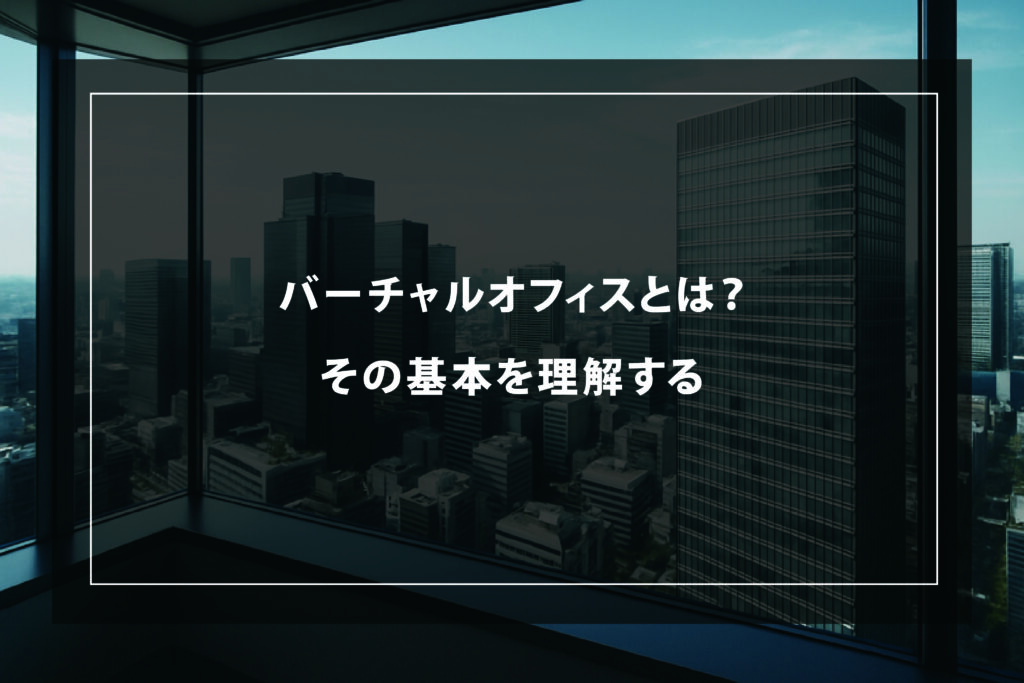
スタートアップや個人事業主にとって、ビジネス用の住所をどう確保するかは、信用にもコストにも関わる重要なテーマです。ここでは、まず「バーチャルオフィスとは何か?」という基本的な理解から、活用の背景や種類、注意点までを整理していきます。
バーチャルオフィスと通常のオフィスの違い
バーチャルオフィスは、実際のオフィススペースを持たずに、事業用の「住所」や「連絡先」を借りるサービスです。
通常のオフィスのように物理的なワークスペースを使用するのではなく、以下のような機能に特化しています:
・法人登記に使える住所の提供
・郵便物の受け取り・転送サービス
・固定電話番号や電話代行
・会議室の時間貸し(施設による)
いわば「物理的な場所がないオフィス」であり、リモート中心の働き方や、出張・訪問型ビジネスと非常に相性が良い形態です。
バーチャルオフィスの普及が進む背景
バーチャルオフィスは、コロナ禍や働き方改革の影響で需要が急増しました。
特にスタートアップや副業での起業、ノマドワーク、地方在住者の都市登記ニーズなど、「固定の拠点がなくても事業は成り立つ」という認識の広がりが背景にあります。
また、以下のようなトレンドも普及を後押ししています:
・初期費用や固定費の削減を重視する起業家の増加
・法人登記のためだけに高額なオフィス契約を避けたい層の拡大
・郵便や電話など、“住所+α”の機能を手軽に外注したいニーズの高まり
これらの背景から、バーチャルオフィスはスタートアップの“第一歩”として選ばれる機会が増えているのです。
バーチャルオフィスのサービスの種類と選び方
バーチャルオフィスとひとくちに言っても、提供内容は運営会社によって異なります。主なサービスの種類と、選び方のポイントは以下の通りです:
| サービス項目 | 選び方のポイント |
| 住所提供・登記対応 | 法人登記可能か/建物名付きか/都心か |
| 郵便物転送 | 転送頻度(週1/毎日)・手数料の有無 |
| 電話番号・代行 | 03番号取得可能か/有人対応か |
| 会議室利用 | 予約制/無料or有料/立地と清潔感 |
| 法人口座開設実績 | 登記住所の信頼性・口座審査通過実績の有無 |
「使わない機能を外す/必要な機能を確実に押さえる」ことが、コスト最適化と失敗防止のカギになります。
バーチャルオフィスを利用する上での注意点
コストや手軽さが魅力のバーチャルオフィスですが、利用にあたってはいくつか注意すべき点もあります:
・業種によっては登記が制限される場合がある(金融・風俗など一部業種)
・銀行口座の開設審査が通りにくいことがある(登記住所の印象による)
・住所を共有する他事業者とのトラブル(同一住所の信用問題)
・運営会社が倒産した場合、急な住所変更を迫られるリスク
これらを防ぐためにも、契約前には運営会社の信頼性や、利用実績、過去の事例などをしっかり確認することが重要です。
スタートアップにバーチャルオフィスが選ばれる理由
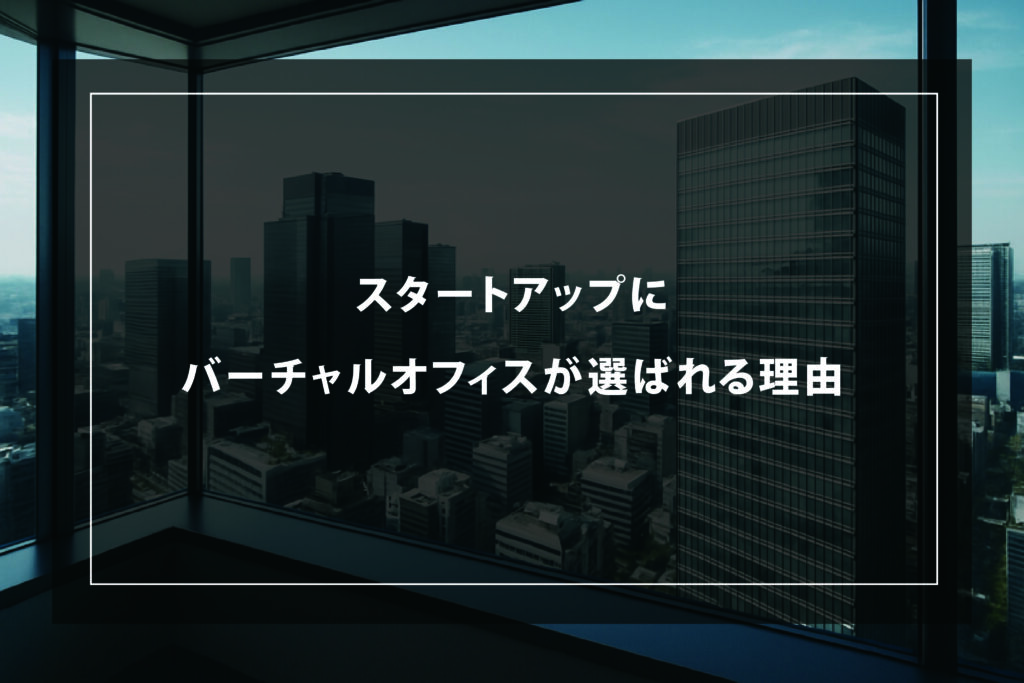
限られたリソースの中でスピーディに事業を立ち上げたいスタートアップにとって、バーチャルオフィスは理想的な選択肢の一つです。ここでは、スタートアップがバーチャルオフィスを導入する具体的な理由やメリットを紹介します。
コスト削減と柔軟な運用が可能
スタートアップが直面する最大の課題のひとつが「資金の制約」です。バーチャルオフィスであれば、敷金・礼金・原状回復費などの初期費用を大幅にカットでき、月額数千円〜で利用可能なプランも多数あります。
また、「登記だけしたい」「郵便転送だけ利用したい」など、必要なサービスだけを選べる柔軟性も大きな魅力。事業フェーズに応じて見直しやすく、スモールスタートにぴったりです。
信頼感を高める住所選びができる
法人登記する住所は、名刺・会社案内・ホームページなどに記載されるため、取引先や金融機関に与える印象に直結します。バーチャルオフィスでは、銀座・新宿・青山・日本橋など、都心一等地の住所をコストを抑えて利用できるため、実体のあるオフィスがなくても「きちんとした会社」という印象を与えることができます。
これは、まだ実績の少ないスタートアップにとって大きな武器になります。
スタートアップ向けの支援サービスが豊富
近年のバーチャルオフィスは、単なる住所貸しにとどまらず、スタートアップ支援に特化したサービスを提供するところも増えています。
例としては:
・会社設立や登記サポート
・会計・税務の初期相談
・スタートアップ向けセミナーや交流会
・インキュベーション型シェアオフィスとの連携
こうした支援を活用することで、ノウハウやネットワークをスピーディに得られる点もメリットです。
リモートワーク体制の構築がしやすい
バーチャルオフィスは、物理的な出社を前提としない働き方と非常に相性が良いです。メンバーが自宅や全国各地からリモートで働く場合でも、法人登記や郵便・電話の取りまとめはバーチャルオフィス側に任せることができます。
また、必要に応じて会議室やスポット利用できるワークスペースが併設されている物件も多く、ハイブリッドな働き方の拠点としても活用できます。
拠点を持たずに事業を広げられる
バーチャルオフィスを活用すれば、実際に人員を常駐させずに“東京支店”や“大阪オフィス”を開設することも可能です。これにより、営業エリアの拡大や取引先からの信頼獲得、求人時の印象アップにもつながります。
複数拠点展開が簡単にできるため、地方在住で都市部のアドレスを活用したいスタートアップや、将来の拠点拡大を見据える企業にも最適です。
バーチャルオフィス利用例
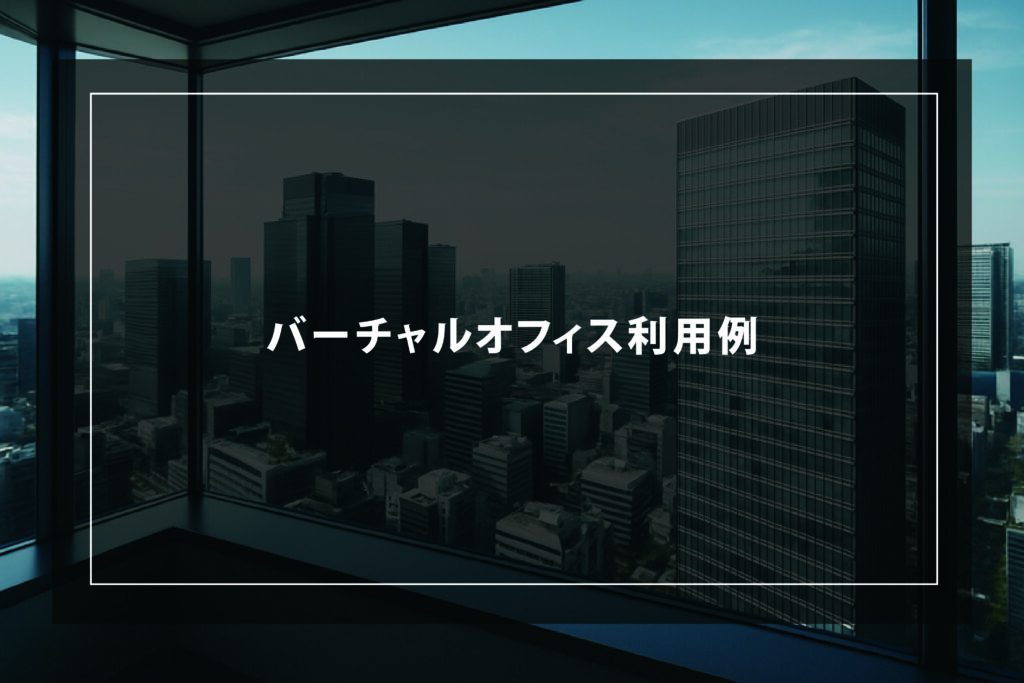
バーチャルオフィスは業種や企業規模を問わず、多様な形で活用されています。ここでは、実際にスタートアップや小規模企業がどのようにバーチャルオフィスを導入し、コストを抑えつつビジネスチャンスを広げたかという具体例をご紹介します。
ケース1)IT系企業のスタートアップ事例
30代のエンジニア2名が立ち上げたSaaS系スタートアップは、開業当初は完全リモートで業務を行っていました。当初は登記と法人銀行口座開設のために、都心のバーチャルオフィスを利用。名刺やWebサイトに銀座アドレスを掲載したことで、大手企業からの問い合わせや提携の打診が増加しました。後に人員が増えたタイミングで、同一運営会社が提供するレンタルオフィスへスムーズに移行できた点も大きなメリットだったといいます。
ケース2)コンサル系起業のスタートアップ事例
人事コンサルとして独立した40代の男性は、打ち合わせは基本的に訪問型・オンライン対応が中心。そのため、固定の事務所は必要ないと判断し、法人登記と郵便転送サービス付きのバーチャルオフィスを選択しました。信頼感のある港区アドレスを利用することで、初期の法人顧客との契約もスムーズに進み、オフィスコストを抑えながらも“ちゃんとした会社”という印象を与えられたと語っています。
ケース3)海外展開を見据えた使い方
海外市場向けにECサービスを展開しているスタートアップは、日本側の法人登記のためにバーチャルオフィスを利用。都内の拠点で登記し、郵便物や法務関連書類の受け取りを現地スタッフに一任する形で運用しています。現地にオフィスや人材を置かずに、法人格や信用だけを確保できるバーチャルオフィスは、海外チーム主体のスタートアップにとって非常に相性が良い手段です。
ケース4)小規模企業のスケールアップ事例
数名でスタートしたマーケティング会社では、バーチャルオフィスで法人登記しながら、実務はリモート・訪問型で対応。数年後、クライアントが増えたタイミングで、同じ運営会社のレンタルオフィスに拡張移転。電話応対・来客対応・会議室利用を加えることで、“成長段階に合ったオフィス運用”を実現しました。
「成長フェーズに合わせて、段階的にオフィス機能を追加できる点が、他の形態にはない強みだった」と代表は語っています。
このように、バーチャルオフィスは「住所だけ借りる」だけでなく、事業成長・信頼獲得・拡張性を支える柔軟な選択肢として活用できます。
バーチャルオフィスの選び方と導入方法
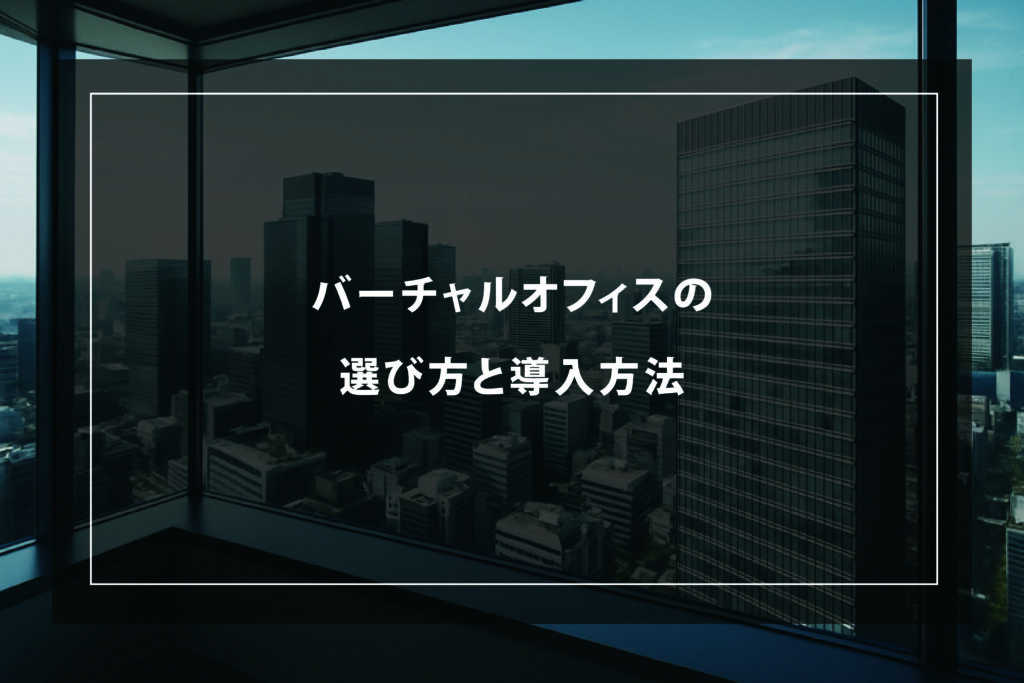
バーチャルオフィスは便利な反面、「なんとなく安いから選んだ」では後悔するケースも。サービス内容や運営会社の信頼性、コスト構造などを見極めて選ぶことが、長期的に安心して活用できるポイントです。ここでは、選び方の基本と導入〜運用の流れまでを解説します。
ニーズに合ったサービスの選び方
バーチャルオフィスは、利用目的に応じて選ぶべきサービスが変わります。以下を明確にしておくと、失敗が防げます。
| 利用目的 | 必要な機能(例) |
| 法人登記したい | 登記可能な住所、建物名付きアドレス |
| 郵便物を受け取りたい | 郵便転送、保管、メール通知 |
| 電話受付も頼みたい | 固定電話番号、電話転送、電話秘書サービス |
| 来客や会議がある | 会議室利用、フロント受付サービス |
“なんとなく一番安いプラン”ではなく、「必要なサービスだけが含まれているか」を基準に選ぶのが賢い選び方です。
契約前に確認すべきポイント
契約前には、以下のような点を運営会社にしっかり確認することが重要です:
・登記が本当に可能か(業種や法人格による制限がある場合あり)
・郵便物の取り扱い:即時通知、転送頻度、手数料の有無
・法人口座の開設実績がある住所か
・表札や社名掲出の対応可否(必要な場合)
・途中解約やプラン変更の条件(柔軟性があるか)
特に、起業直後は住所の信頼性が銀行や取引先とのやり取りに直結するため、信用力のある立地や建物かも確認しましょう。
初めてバーチャルオフィスを利用する際の手続き
多くのバーチャルオフィスでは、以下のようなシンプルな流れで契約できます。
1)サービス内容・料金プランを比較検討
2)オンライン or 店舗で申し込み
3)本人確認書類・登記書類等の提出
4)利用審査(1〜3営業日ほど)
5)審査通過後、契約手続き・初期費用支払い
6)登記や名刺などへの住所反映、郵便対応スタート
オンライン完結可能なサービスも多く、1週間以内に利用開始できるケースも多数あります。
バーチャルオフィス導入後の運用方法
契約後は、バーチャルオフィスを単なる「住所」ではなく、“事業インフラのひとつ”としてうまく活用する意識が大切です。
| 郵便物の管理 | 転送ルールを確認し、重要書類の取り漏れを防ぐ |
| 会議室利用 | 必要なときに予約できるようにアカウント登録を済ませておく |
| 電話対応 | 電話代行を活用して不在時の対応品質を保つ |
| 住所活用 | Web・名刺・提案書などに積極的に記載し、信頼性を向上 |
また、利用状況に応じて、将来的に「レンタルオフィス」や「支店追加」に切り替えることも視野に入れておくと、事業拡大がスムーズです。
コストの見積もりと予算管理方法
バーチャルオフィスは一見すると「月額3,000円〜」など安く見えますが、オプション料金や初期費用が発生する場合も多いため、総コストで比較することが大切です。
| 月額基本料 | 登記・住所利用含む |
| 初期費用 | 入会金・登録料など |
| 郵便転送手数料 | 頻度・方法によって変動 |
| 電話番号・電話代行オプション | |
| 会議室や設備利用料 | 従量課金型 |
事業開始前に、「初期費用+3ヶ月分の運用費」を目安に見積もると、急な出費に困らず安心です。
他の選択肢との比較
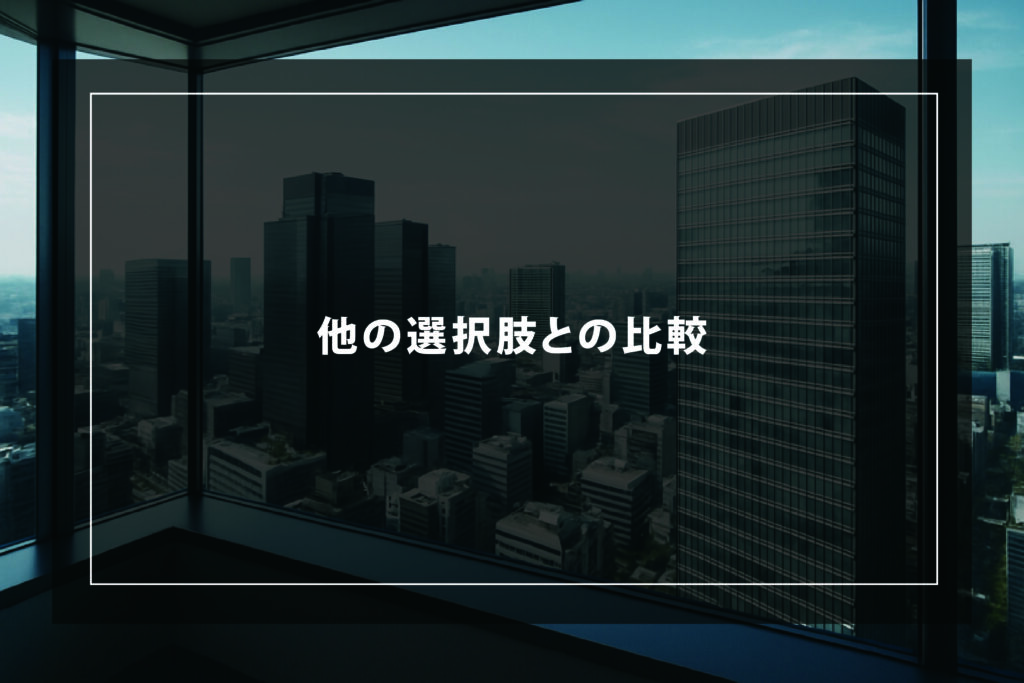
バーチャルオフィスは便利でコスト効率の高い選択肢ですが、他にも「レンタルオフィス」「コワーキングスペース」「自宅オフィス」などさまざまなワークプレイスの形があります。
ここでは、それぞれの違いやメリット・デメリットを比較し、どんな働き方・フェーズのスタートアップに合うのかを整理します。
| 比較項目 | バーチャルオフィス | レンタルオフィス |
| 拠点の有無 | 住所のみ利用(物理的空間なし) | 専用スペース(個室・ブースなど)あり |
| 登記対応 | 可能(プランにより異なる) | ほぼすべて対応 |
| 利用目的 | 信頼性のある住所確保、コスト削減 | 実働スペース確保、打ち合わせ・作業に最適 |
| 月額費用の目安 | 3,000〜8,000円程度 | 2万〜10万円以上(規模・立地による) |
登記や郵便のみで十分な場合はバーチャルオフィス、業務の中心をオフィスに置きたい場合はレンタルオフィスが適しています。
コワーキングスペースとの比較
コワーキングスペースは、共用デスクを時間単位・日単位・月単位で利用できる自由度の高いオフィス形態です。一方、バーチャルオフィスはあくまで住所・登記・郵便などの「機能」を借りる形。
| 比較項目 | バーチャルオフィス | コワーキングスペース |
| 作業スペース | なし | あり(フリー席 or 固定席) |
| 登記対応 | 対応プランあり | 運営会社によって異なる |
| 利用目的 | 住所・登記・郵便機能 | 作業・打ち合わせ・交流 |
実務スペースが不要なスタートアップならバーチャルオフィス、作業場所も確保したいならコワーキングスペースの月額プランがおすすめです。
自宅オフィスとどう違う?
在宅ワークが当たり前になった今、「自宅住所で登記すればいいのでは?」と思う方も多いでしょう。しかし、自宅住所で法人登記を行う場合には以下のリスク・懸念があります。
・名刺やホームページにプライベート住所が公開される
・郵便・宅配などの受け取り体制が不十分
・賃貸物件では登記NGのケースもある
・金融機関・取引先からの信用に不安が残る
バーチャルオフィスを使えば、これらの問題を解決しつつ、コストを最小限に抑えて「信頼される事業住所」が得られます。
出社頻度に応じた選択肢の考え方
事業形態や働き方によって、オフィスに「どれだけ通うか?」は大きく変わります。
出社頻度別に適したオフィス形態をまとめると以下の通りです:
| 出社頻度 | 最適なオフィス形態 |
| ほぼ出社しない | バーチャルオフィス |
| 週1〜2日程度 | コワーキングスペース+登記オプション |
| 毎日出社する | レンタルオフィス(個室推奨) |
「毎日通う必要があるか?」を基準に、必要なコストと利便性を天秤にかけて選ぶことが成功のカギです。
スタートアップに合ったオフィス形態とは
スタートアップの初期フェーズでは、事業内容や資金状況、働き方に応じて最適なオフィス形態が異なります。
・コストを最小限に抑えたい → バーチャルオフィス
・実務も都内で行いたい → レンタルオフィス
・少人数のチームで柔軟に働きたい → コワーキングスペース
・将来の拡張を視野に入れたい → バーチャルオフィス+必要に応じて実オフィスへ移行
まずは今の事業フェーズに合った最小構成で始め、スケールに応じて拡張できる運用が理想的です。
まとめ|バーチャルオフィスはスタートアップに最適な“第一歩”
バーチャルオフィスは、コストを抑えながら信頼性の高いビジネス拠点を持てるという点で、スタートアップにとって非常に有効な選択肢です。登記・郵便・電話といった“最低限必要な機能”を備えつつ、物理的な制約がないことで、柔軟な働き方や全国・海外への展開にも対応できます。
また、事業の成長にあわせて、レンタルオフィスやコワーキングスペースに切り替えたり、拠点を追加したりすることもできるため、スモールスタートと拡張性を両立できるのも大きな魅力です。
「開業したいけど、いきなり高いオフィスは不安」「自宅住所は出したくない」
そんな方は、まずは信頼できるバーチャルオフィスから一歩を踏み出してみてください。
THE HUBでは、スタートアップに最適な登記対応のバーチャルオフィスを多数ご用意しています。
内覧不要・ネットで申込をするだけ(審査あり)で利用できますので、まずはご希望のエリアを検索してみてください。

writing by:nex株式会社 事業企画室
nexでは、レンタルオフィス・コワーキングスペース・バーチャルオフィスに関する情報を、コラム記事を通じてわかりやすく発信しています。
自社サービスに限らず、これから働き方を見直したい方・新しい拠点を検討している方に役立つ業界情報をお届けしていきます。

writing by:nex株式会社 事業企画室
nexでは、レンタルオフィス・コワーキングスペース・バーチャルオフィスに関する情報を、コラム記事を通じてわかりやすく発信しています。
自社サービスに限らず、これから働き方を見直したい方・新しい拠点を検討している方に役立つ業界情報をお届けしていきます。