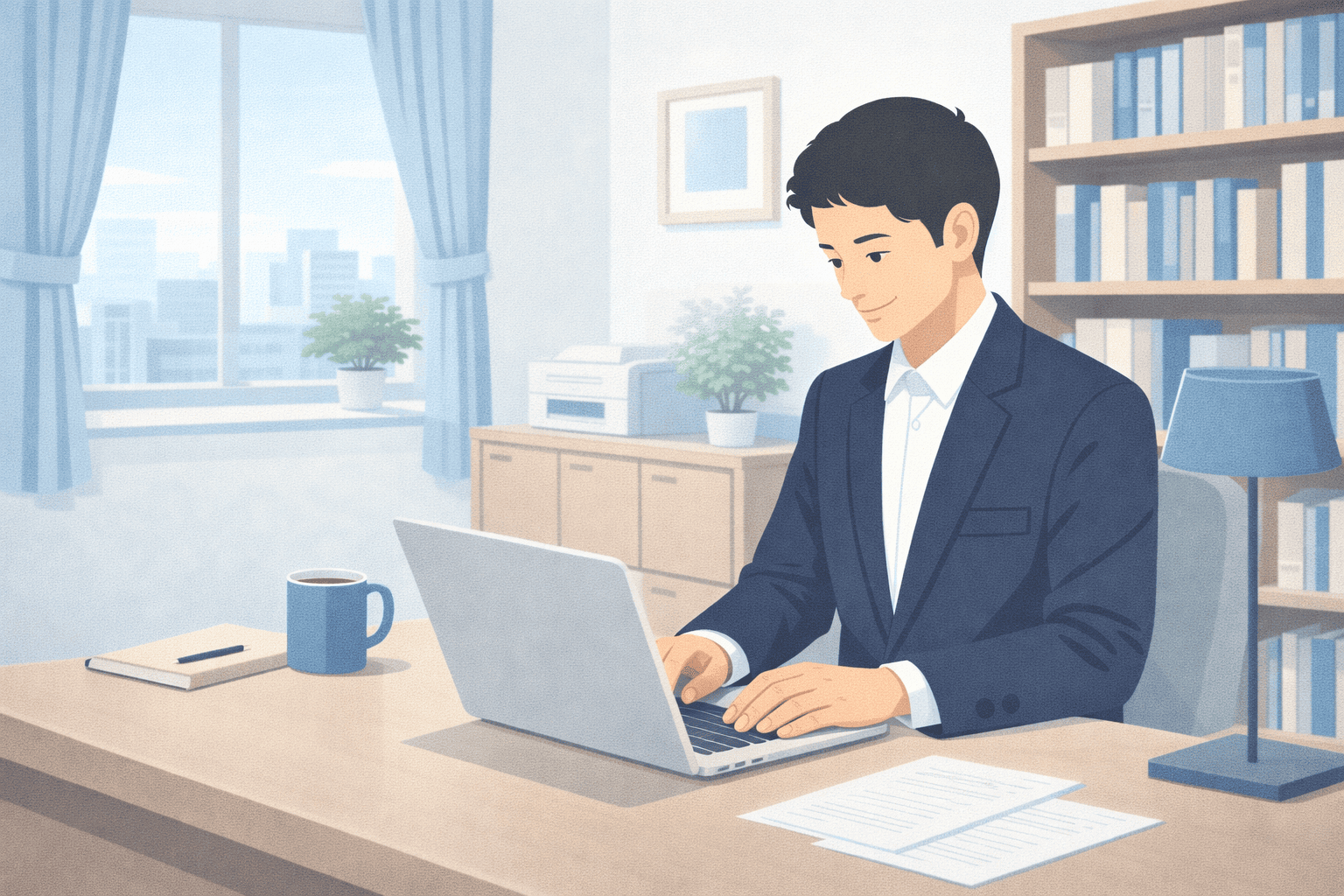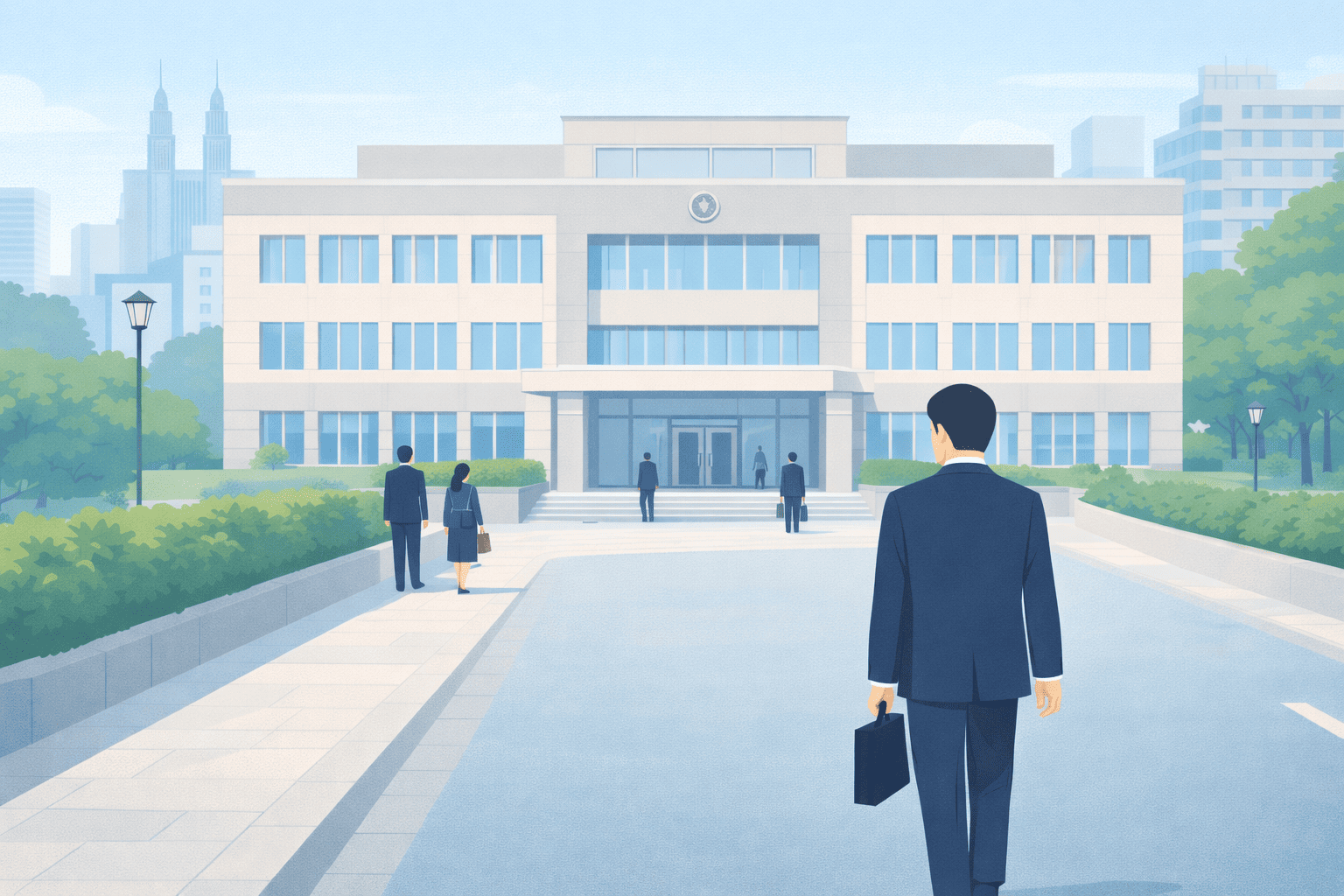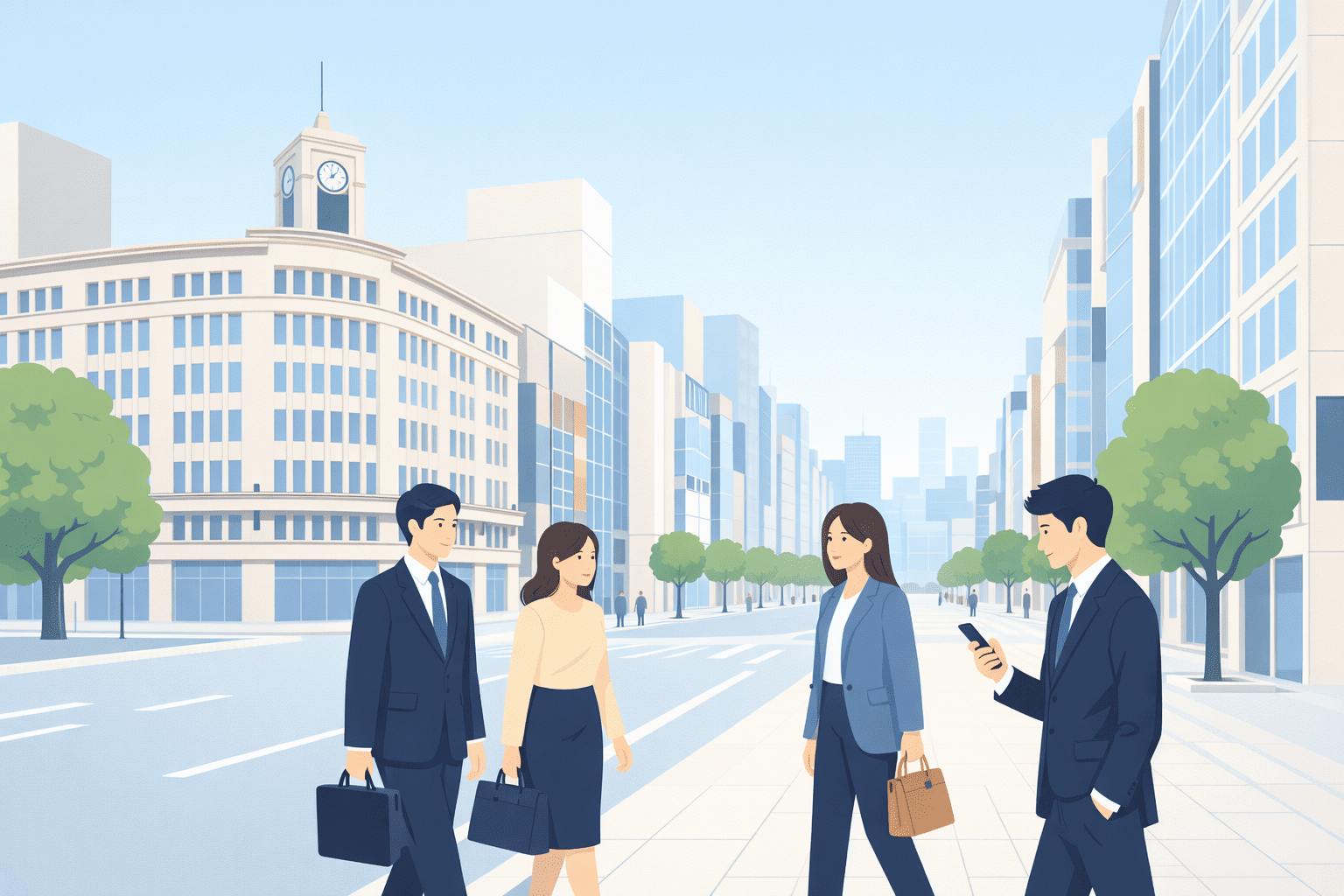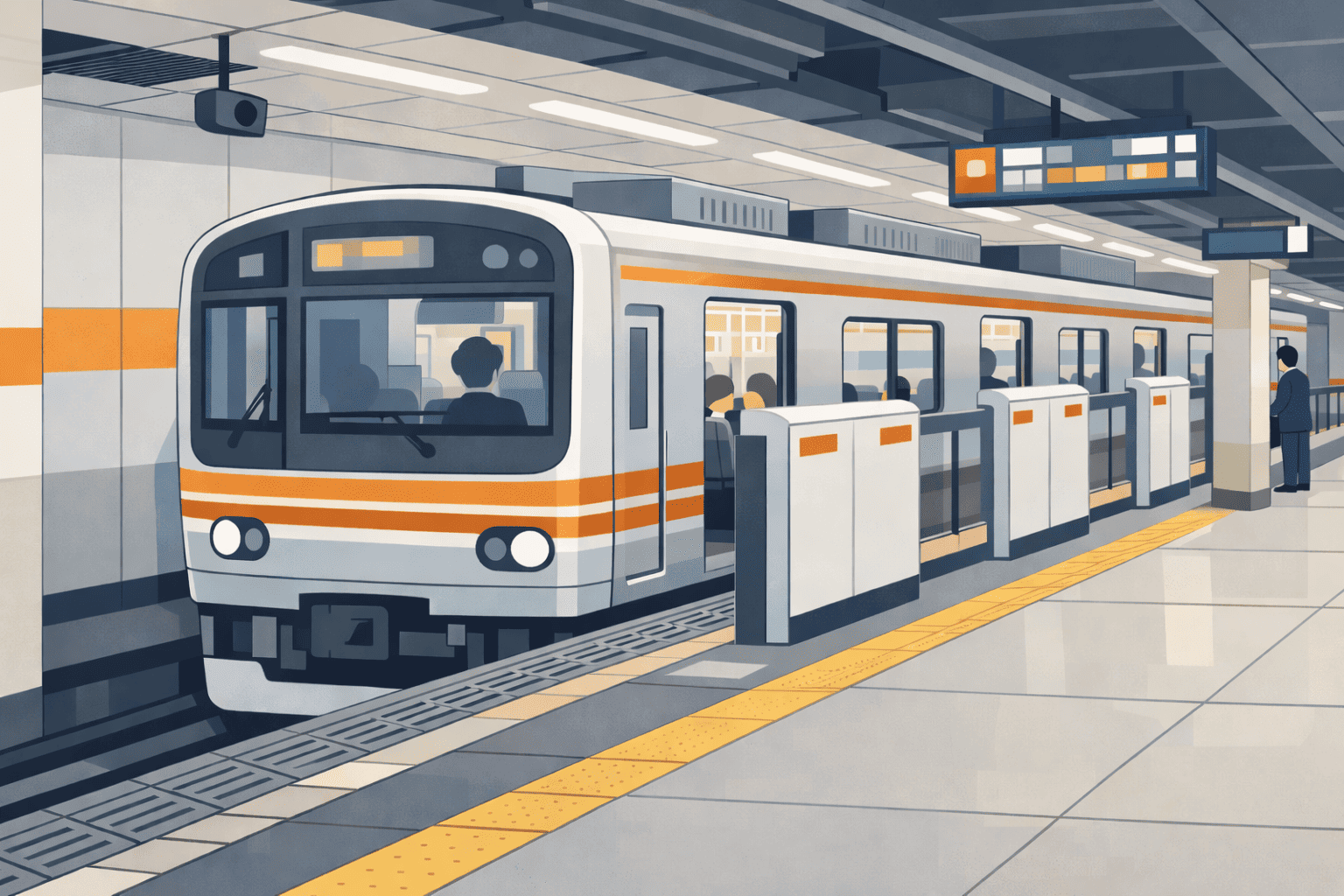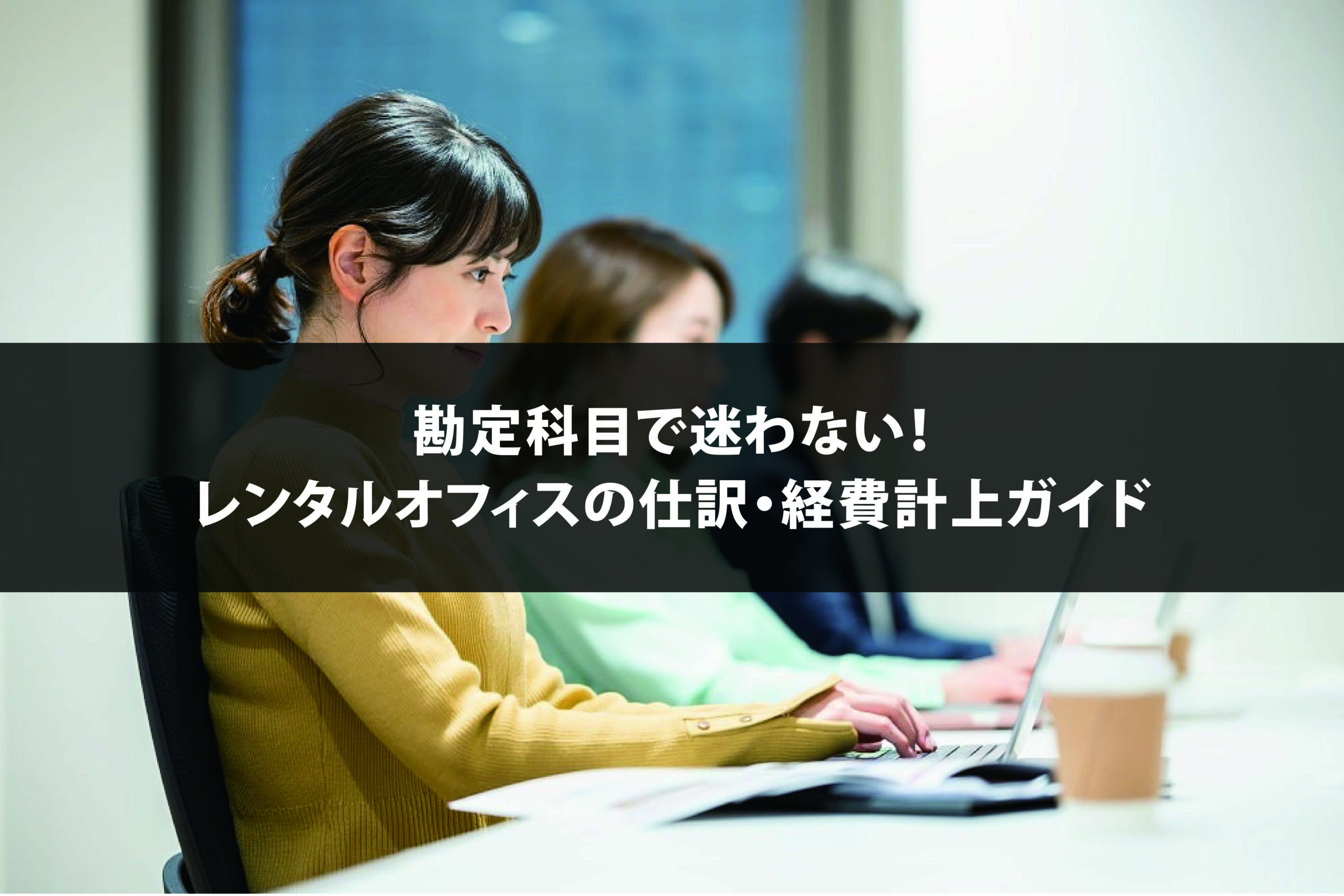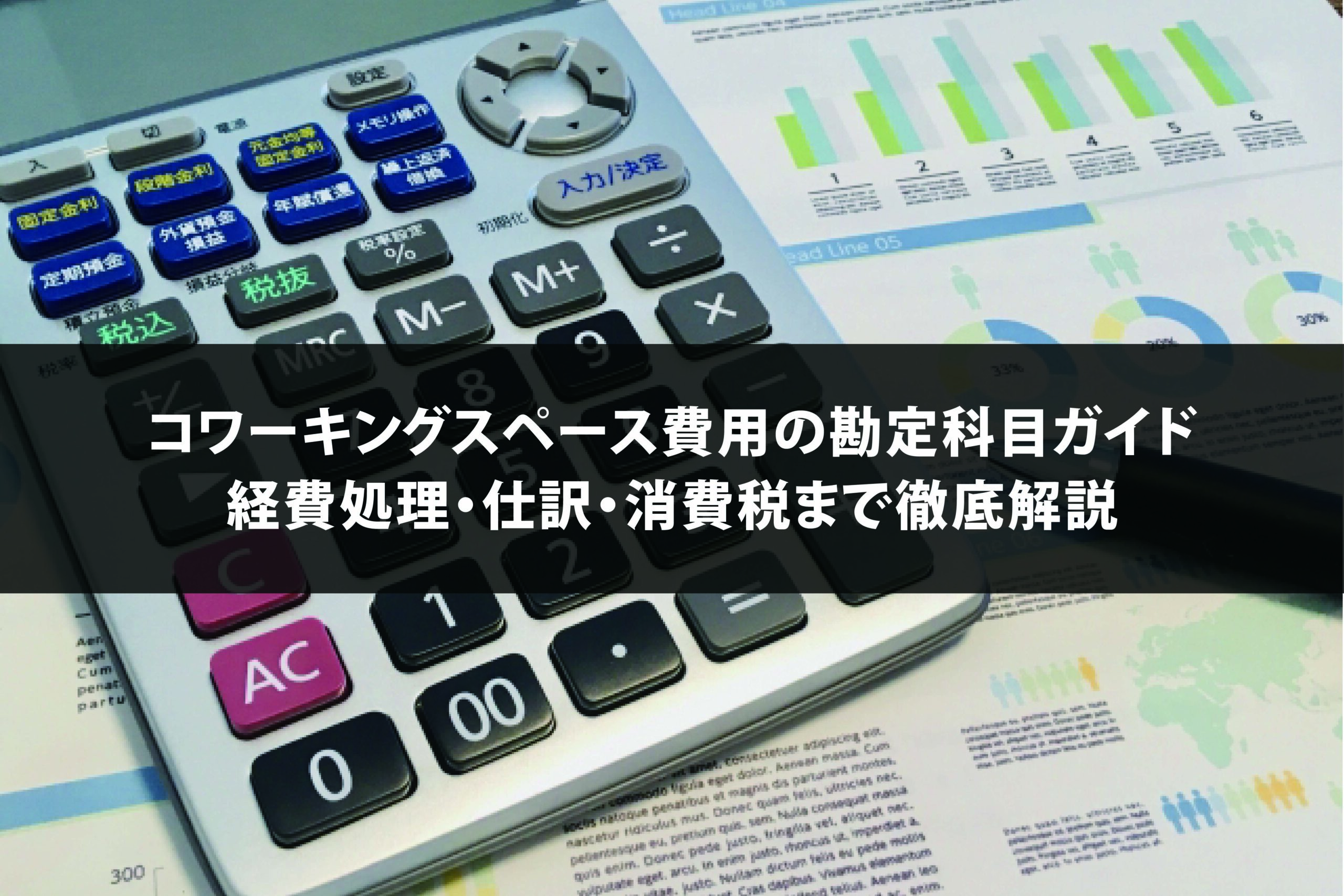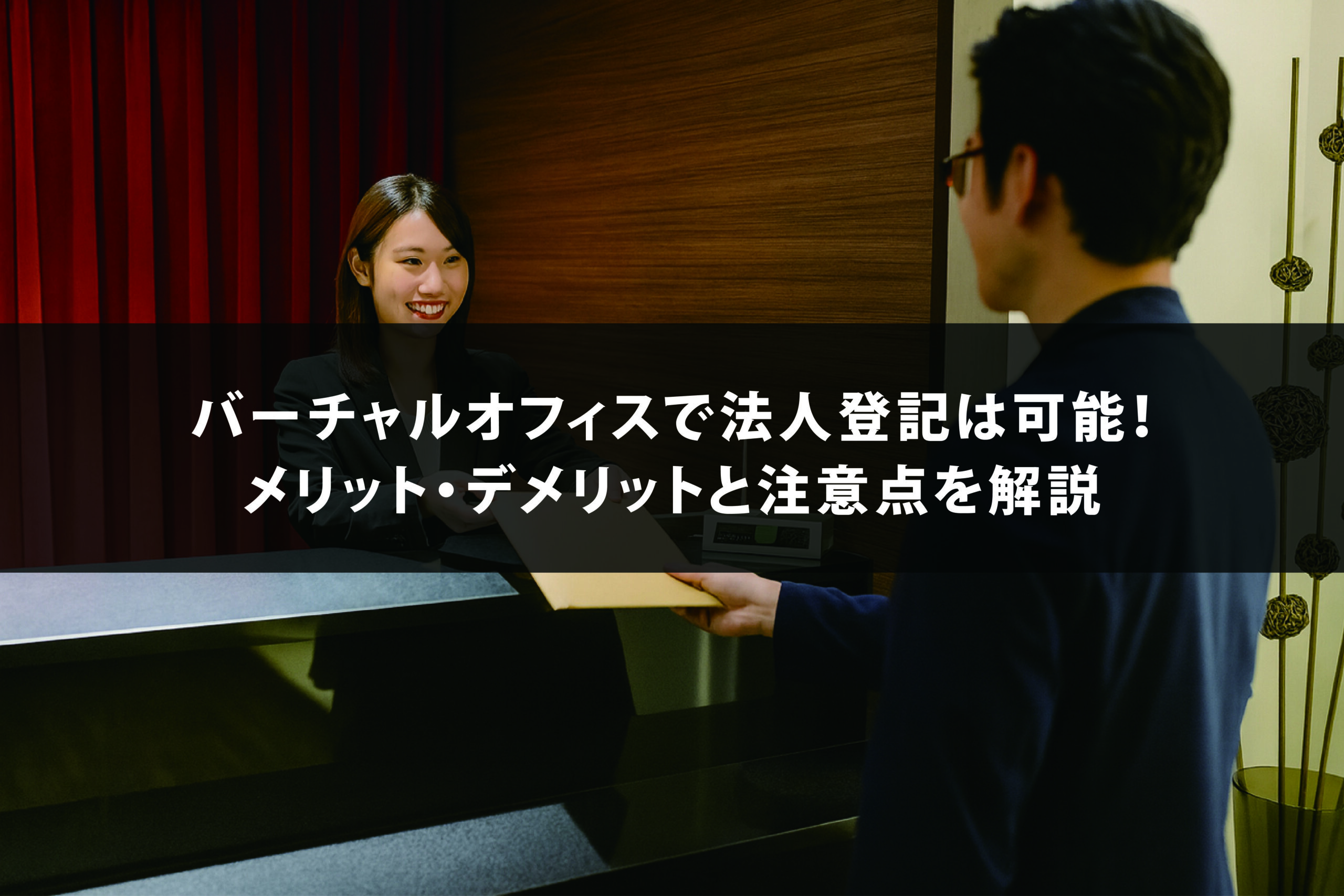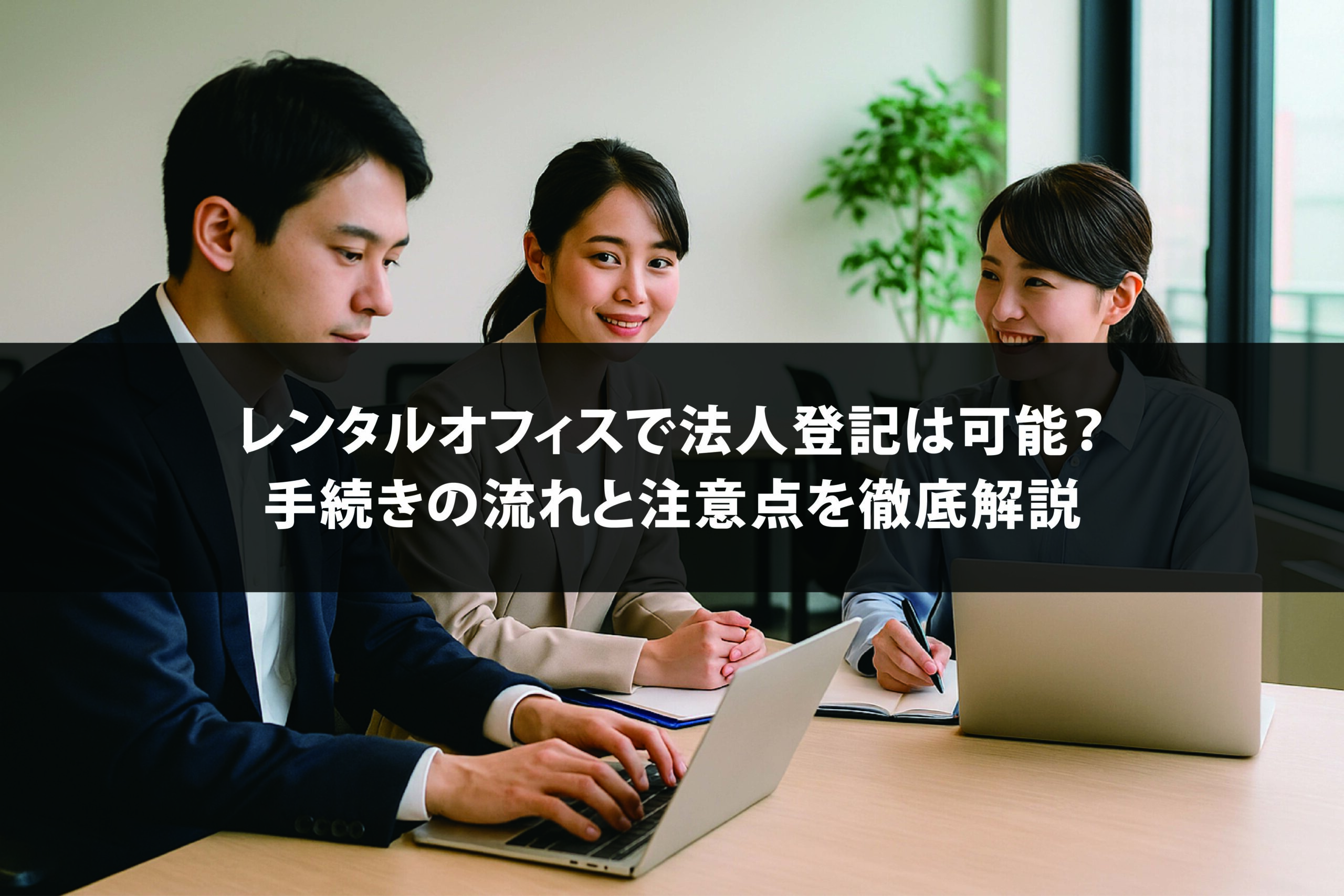【初心者向け】バーチャルオフィスで会社設立は大丈夫?不安を解消する完全ガイド
2025年10月23日
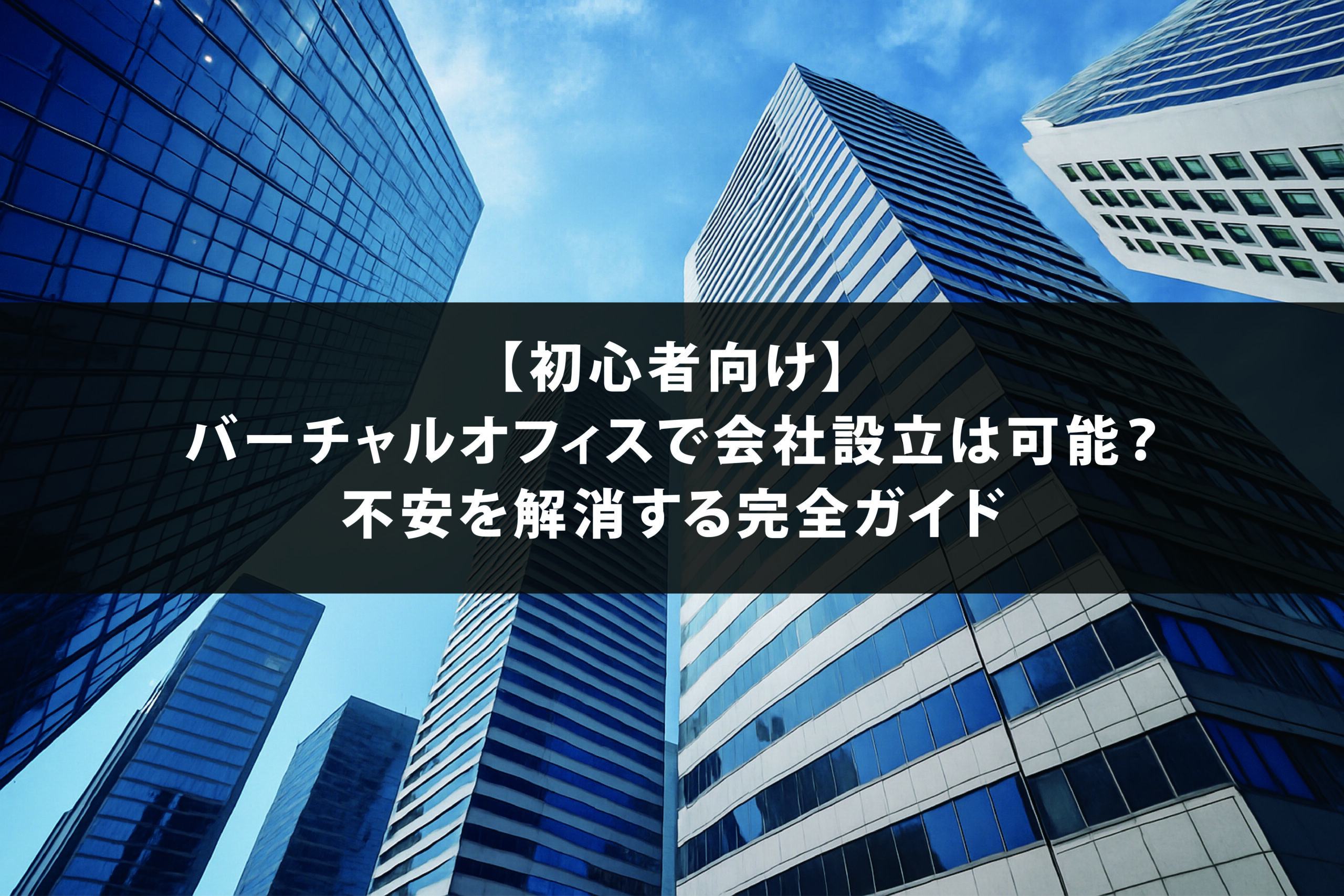
会社を設立したいけれど、「バーチャルオフィスで登記しても本当に大丈夫?」「あとでトラブルにならない?」と不安に感じていませんか? 実際、バーチャルオフィスでの会社設立は年々増加しています。
コストを抑えつつ信頼性のある住所を利用できる一方で、登記・契約・法律面の知識がないまま進めると、思わぬトラブルになるケースもあります。
本記事では、「バーチャルオフィスで会社設立するのは大丈夫?」という不安をすべて解消できる完全ガイドとして、メリット・設立手順・注意点・選び方まで初心者にもわかりやすく解説します。
バーチャルオフィスで会社設立するメリットとは?
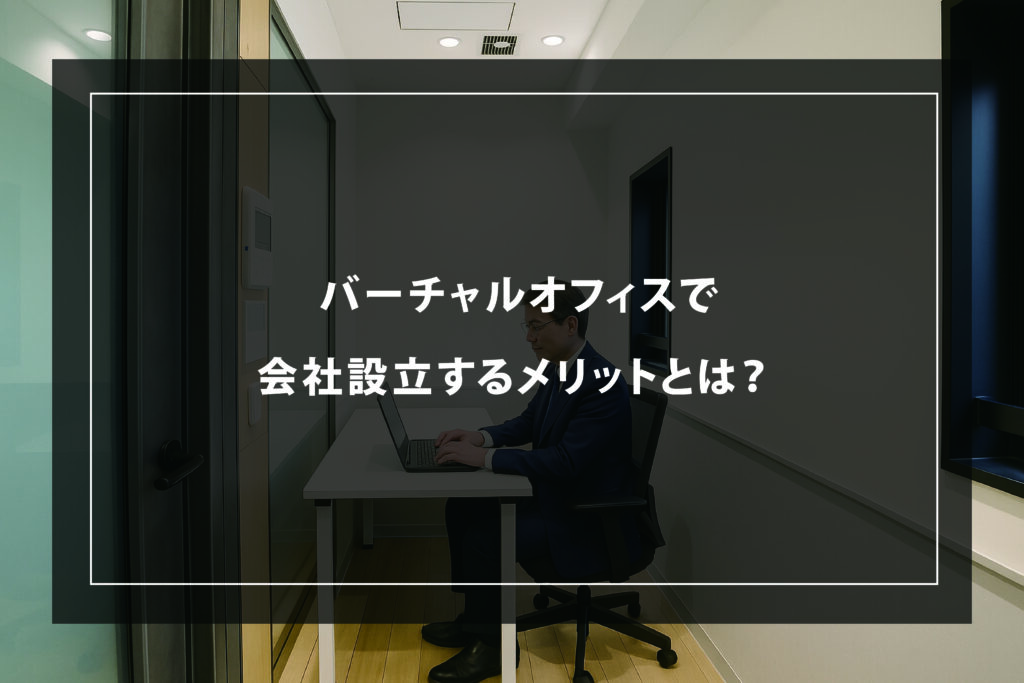
バーチャルオフィスは「住所だけを借りて登記・郵便・電話対応などを行えるサービス」です。実際にオフィスを構えなくても事業の拠点を設けることができ、コストを抑えながら信頼性のある事業住所を利用できます。
ここでは、バーチャルオフィスを利用して会社設立する主なメリットを紹介します。
コスト削減の理由
バーチャルオフィスを活用する最大の利点は初期費用と固定費の削減です。
一般的な賃貸オフィスでは、敷金・礼金・光熱費・通信費など、初期費用だけで数十万円かかることもあります。
一方で、バーチャルオフィスなら月額数千円〜1万円台から利用でき、「事務所を借りる=資金を縛られる」という課題を大きく軽減できます。創業初期の起業家や個人事業主にとって、限られた資金を事業成長やマーケティングに回せるのは大きなメリットです。
柔軟な働き方の実現
バーチャルオフィスは、場所に縛られない働き方を可能にします。
自宅・カフェ・出張先など、どこからでも仕事ができるため、フルリモートのチーム運営にも最適です。
特に近年では、全国どこからでも郵便転送やオンライン受付を利用できるため、地方在住でも「東京都内の住所で登記」することが容易になりました。
所在地選択の自由度
バーチャルオフィスを使えば、実際にその場所にオフィスを構えなくても、都心の一等地住所(例:東京都港区・中央区など)で登記が可能です。これにより、取引先や顧客に対して信頼感を与えることができ、「個人事業」ではなく「法人」としての社会的信用を得やすくなります。
また、スタートアップや士業が「ブランディングの一環」としてバーチャルオフィスの住所を活用するケースも増えています。
プライバシー保護の利点
自宅で法人登記を行うと、登記簿謄本やWeb上に自宅住所が公開されることになります。これに抵抗を感じる起業家も少なくありません。バーチャルオフィスを利用すれば、自宅住所を公開せずに登記が可能なため、プライバシー保護の観点でも安心です。
特に女性起業家や副業会社員にとっては、安心してビジネスを始められる大きな利点となります。
外出先からでもどこでも仕事が可能
多くのバーチャルオフィスは、郵便物のスキャン・転送や電話代行などをオンラインで完結できます。これにより、全国どこにいても本社業務を滞りなく行える点もメリットのひとつです。また、レンタル会議室を併設している拠点も多く、商談や面談時だけ実際のオフィススペースを利用するなど、柔軟な働き方が可能です。
このように、バーチャルオフィスは「コスト削減」「信頼性の確保」「プライバシー保護」を同時に叶える便利なサービスです。次の章では、実際に会社を設立する際の具体的な手順と流れを解説します。
バーチャルオフィスでの会社設立の流れ
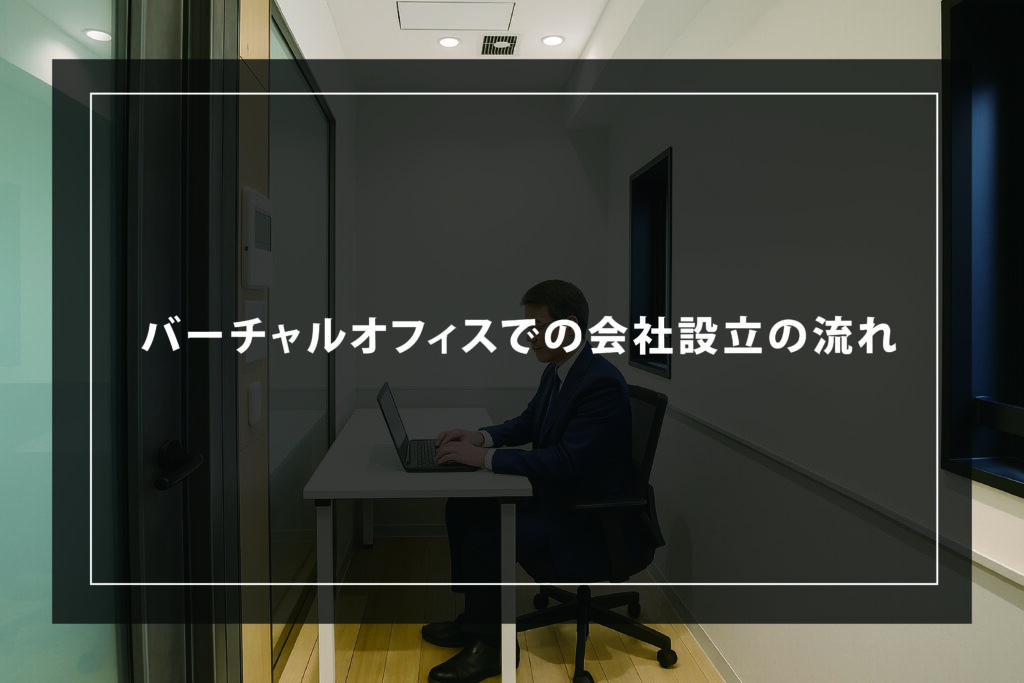
バーチャルオフィスで会社を設立する手続きは、基本的には一般的な法人設立と同じ流れです。ただし、「登記に使える住所かどうか」など、バーチャルオフィスならではの注意点もあります。ここでは、会社設立の具体的な手順をステップごとに解説します。
1)必要書類の準備
会社を設立する際は、まず必要書類をそろえることから始めます。法人の種類(株式会社・合同会社など)によって多少異なりますが、代表的な書類は以下のとおりです。
・定款(ていかん):会社の基本ルールをまとめた書類(電子定款の場合は印紙代4万円が不要)
・登記申請書
・発起人・取締役の印鑑証明書
・出資金の払込証明書(通帳のコピーなど)
・会社の実印(法人印)
・登記に使用する住所の証明書(バーチャルオフィスの契約書など)
特に、バーチャルオフィスの住所を使用する場合は、登記可能な契約であることを証明できる書類が必要です。契約前に「登記可」と明示されているか、必ず確認しましょう。
2)書類提出の手順
必要書類がそろったら、以下の流れで登記申請を行います。
| 1.定款を作成・認証 | 株式会社の場合は、公証役場で定款の認証を受けます(電子認証ならオンライン可)。 |
| 2.出資金の払い込み | 発起人の個人口座に資本金を振り込み、通帳コピーを作成します。 |
| 3.登記申請 | 法務局に登記申請書を提出(オンライン登記システムも利用可)。 |
| 4.登記完了後、法人番号が付与 | 法人番号公表サイトで会社情報が確認できるようになります。 |
バーチャルオフィスを利用する場合、住所に関する書類が不備だと登記が受理されないケースもあるため、契約書や利用証明書の添付を忘れないようにしましょう。
3)登録完了までの期間
書類の内容に問題がなければ、登記申請からおおよそ5〜7営業日で法人登記が完了します。電子申請を利用すれば郵送よりも早く処理される傾向があります。
また、バーチャルオフィス側で登記関連のサポート(契約書の発行・書類テンプレート提供)を行っている場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
4)税務・労務手続きについて
法人登記が完了したら、次は税務署や社会保険関係の届出を行います。主な手続きは以下のとおりです。
・税務署への届出:「法人設立届出書」「青色申告承認申請書」などを提出
・都税事務所・県税事務所への届出
・社会保険・雇用保険の手続き(従業員がいる場合)
これらの手続きも、バーチャルオフィス住所で問題なく行えます。ただし、郵送やオンラインでの提出を希望する場合は、バーチャルオフィスで郵便物が受け取れるかどうかを確認しておきましょう。
5)サポートを受ける方法
初めて会社を設立する場合、「登記書類をどこに出すのか」「電子定款ってどう作るの?」と戸惑う方も多いでしょう。そんなときは、以下のようなサポートを活用するのがおすすめです。
| 行政書士・司法書士の会社設立サポート | 書類作成や登記代行を依頼できる |
| バーチャルオフィス運営会社のサポート | 登記に関する書類テンプレートや顧問士業の紹介 |
| 起業支援サービス(例:スタートアップ支援パッケージ) | 補助金申請や銀行口座開設の相談も可能 |
バーチャルオフィスと法律面の注意点
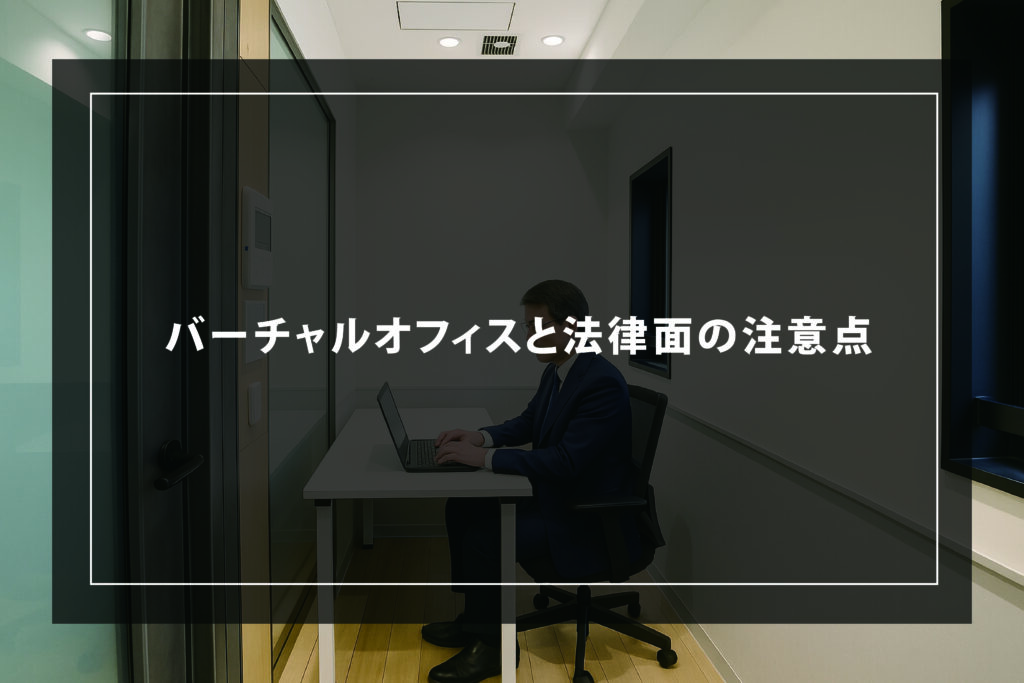
バーチャルオフィスで会社を設立する際には、法律的に問題がないかを心配する方も多いでしょう。実際、法的にはバーチャルオフィス住所での登記が認められていますが、運用上の注意点や契約条件を理解していないと、トラブルにつながることがあります。ここでは、登記や契約の際に押さえておきたい法律面のポイントを整理します。
虚偽住所の使用リスク
バーチャルオフィスを利用する上で最も重要なのが、「実在性のある住所かどうか」です。虚偽の住所を使用して登記を行うと、会社法違反にあたり、罰則(過料)や登記抹消の対象になる可能性があります。
たとえば、登記用住所として契約していない物件や、登記不可の住所を使って登記を申請するのはNGです。
必ず「登記可能」と明記されたバーチャルオフィスを選び、契約書に利用目的として“法人登記”が含まれているかを確認しましょう。
利用契約の確認ポイント
登記をスムーズに進めるためには、契約内容の確認が欠かせません。
契約時には以下の点をチェックしましょう。
・契約書に「登記利用可」と明記されているか
・郵便物の受け取り・転送が対応しているか
・解約後に住所利用ができなくなる旨が記載されているか
・契約者名義が法人名または代表者名で契約可能か
特に、解約後も住所を使用していると無断使用扱いになる可能性があるため、契約終了時の取り扱い(登記住所の変更期限など)も確認しておきましょう。
法人登記での注意事項
バーチャルオフィスは、法務局により登記可能な住所として認められています。
ただし、以下のケースでは申請がスムーズに進まないことがあるため注意が必要です。
・法務局側が「共有住所(複数社が同一住所)」を不審と判断する場合
・反社会的勢力対策や詐欺防止の観点から、確認書類の追加提出を求められる場合
・契約書や利用証明書の原本が不足している場合
これらを防ぐためには、登記前に運営会社が過去に登記実績を持っているかどうかを確認するのがおすすめです。実績が多い会社であれば、登記用書類の準備や法務局対応もスムーズに行えます。
業種による制約や例外
業種によっては、バーチャルオフィスでの登記が制限されるケースもあります。
たとえば、以下のような業種は「実際の事務所スペース」や「特定設備」が必要になる場合があります。
| 不動産業 | 宅建業免許を取得する場合 |
| 建設業 | 建設業許可を申請する場合 |
| 古物商 | 警察署への届出が必要 |
| 士業 | 弁護士・行政書士など、事務所要件がある業種 |
これらの業種では、「営業所」や「管理事務所」などの実体拠点が必要になるため、バーチャルオフィスのみでの登録は難しい場合があります。自分の事業がどの区分に該当するかを、事前に行政書士や許認可専門家に相談しておくと安心です。
トラブルを未然に防ぐ方法
バーチャルオフィスを安全に利用するためには、次の3つを意識することが大切です。
| 1)契約書の内容を必ず確認する | 「登記可」「郵便転送可」「住所使用範囲」などの文言が明記されているか確認 |
| 2)契約書・請求書を保管しておく | 法務局や税務署に提出を求められる場合に備える |
| 3)信頼できる運営会社を選ぶ | 実績・口コミ・サポート体制を確認。法人口座開設の実績がある会社ならより安心 |
バーチャルオフィスの利用は、法的に認められた方法です。正しい手続きと信頼できる運営会社を選べば、登記拒否や契約トラブルの心配なく、安心して会社設立が可能です。
バーチャルオフィスの選び方
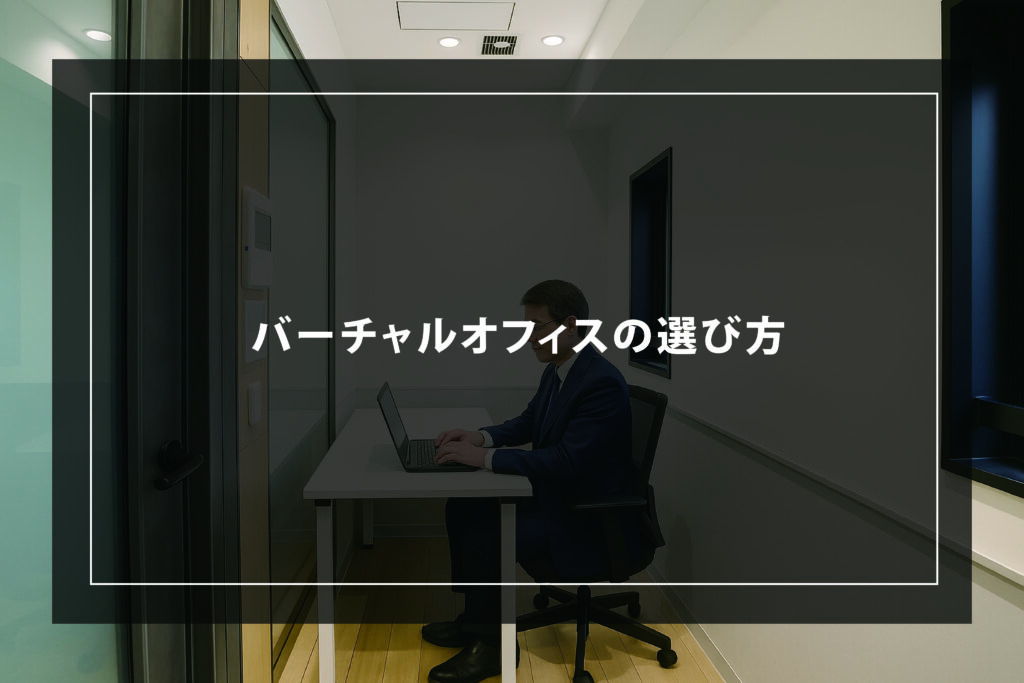
バーチャルオフィスは、運営会社やプラン内容によってサービスの質が大きく異なります。登記対応が可能であることはもちろん、サポート体制や住所の信頼性、料金体系などを総合的に判断することが大切です。
ここでは、安心して利用できるバーチャルオフィスを選ぶためのポイントを紹介します。
信頼性のある運営会社の特定
まずは、運営実績のある信頼できる会社を選ぶことが最も重要です。登記実績が多い会社や、長期間サービスを提供している会社であれば、法務局・金融機関・税務署への対応もスムーズです。
選ぶ際は以下を確認しましょう。
・法人登記実績があるか
・企業の運営年数・拠点数
・公式サイトで住所・会社概要が明確に記載されているか
・サポート対応(電話・メールなど)が丁寧か
信頼性の低い運営会社を選ぶと、「登記不可」や「契約トラブル」などのリスクがあるため注意が必要です。
提供されるサービスの種類
バーチャルオフィスには、基本の住所貸与サービス以外にもさまざまなオプションがあります。自分の事業に必要な機能がそろっているかを確認しましょう。
代表的なサービス内容は以下の通りです。
・郵便物の受け取り・転送
・電話番号の貸与・電話代行サービス
・会議室・コワーキングスペースの利用
・登記対応(法人口座開設サポートを含む)
・税務・会社設立のサポート
サービス内容が豊富なほど費用は高くなりますが、事業規模や利用目的に合わせてコストと利便性のバランスを考えることが大切です。
コスト比較のポイント
料金の安さだけで判断すると、後で「必要なサービスが別料金だった」というケースもあります。月額料金に何が含まれているかを必ず確認しましょう。
チェックすべき項目:
・月額基本料金に含まれるサービス(郵便転送・登記利用など)
・初期費用・保証金の有無
・オプション料金(会議室や電話転送の追加費用など)
・解約時の手数料や最低契約期間
「料金の安さ」=「コストパフォーマンスが良い」とは限りません。
トータルで見て、必要な機能を無理なく使えるプランを選ぶのがおすすめです。
契約前に確認すべき条件
契約前には、必ず契約内容を細かく確認しましょう。特に次の4点はトラブルを防ぐうえで非常に重要です。
| 1)登記利用が明記されているか | 「登記可」と記載があることを必ず確認 |
| 2)郵便物や電話の対応ルール | 保管期間・転送頻度・対応方法をチェック |
| 3)解約後の住所使用停止ルール | 住所を使い続けてしまうと契約違反になる場合も |
| 4)契約者本人確認の有無 | 信頼できる運営会社は、本人確認を徹底しています |
これらの条件を確認しておくことで、安心して長期利用が可能になります。
利用者の口コミや評判の活用方法
実際に利用した人の口コミやレビューをチェックすることで、サービス内容や運営対応の「実態」を把握できます。公式サイトの情報だけでは分からないリアルな声を確認するのがポイントです。
口コミチェックのコツ:
✅ GoogleマップやSNSでのレビューを確認
✅ 法人登記の実績やサポート体験談を探す
✅ 良い口コミだけでなく、悪い口コミの内容もチェック
特に「郵便対応のスピード」「スタッフ対応の丁寧さ」「トラブル対応の早さ」は、実際の満足度を大きく左右する重要なポイントです。
バーチャルオフィス選びのチェックリスト
最後に、契約前に確認しておきたいポイントを簡単にまとめました。
✅ 登記利用が可能であること
✅ 郵便・電話対応がスムーズに行えること
✅ 解約時のルールが明確であること
✅ 法人登記・口座開設の実績があること
✅ サポート体制・口コミ評価が高いこと
これらを満たすバーチャルオフィスを選べば、会社設立後も安心して長く利用できます。
バーチャルオフィス利用者の声・成功事例
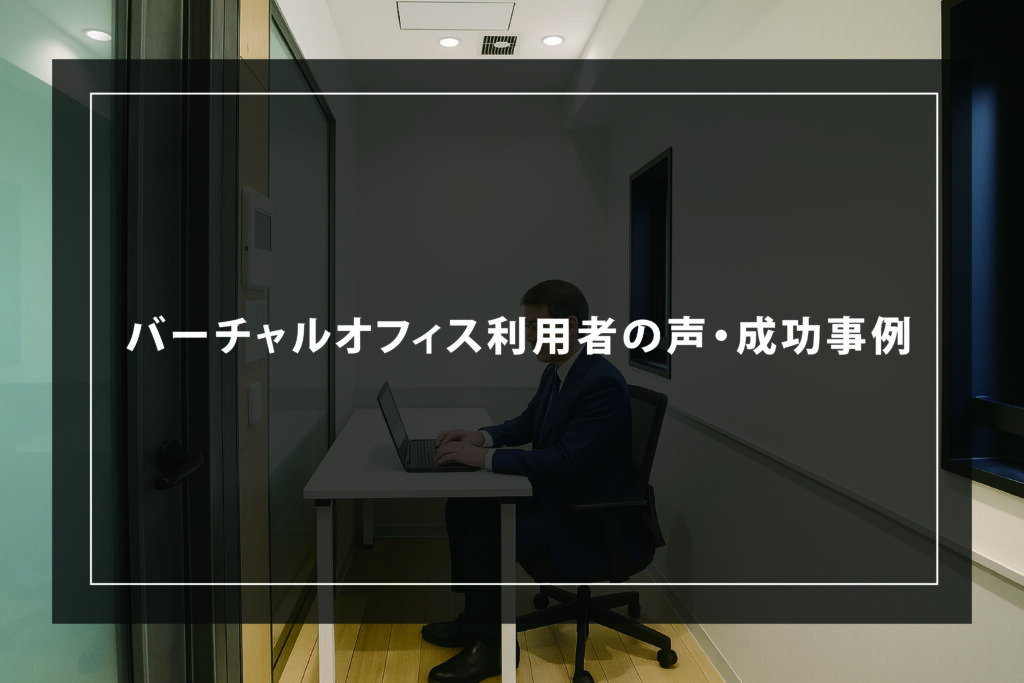
「バーチャルオフィスで会社を設立して本当に大丈夫?」という不安は、多くの起業家が抱える疑問です。
しかし、実際に利用した人の声を聞いてみると、コスト面・柔軟性・信頼性の面で大きなメリットを感じているケースが多数あります。
ここでは、バーチャルオフィスを活用して会社を設立・運営している利用者の実例を紹介します。
起業家の成功体験談
▶ 事例①:初期費用を抑えてスタートアップを立ち上げ
都内でITスタートアップを立ち上げたAさんは、最初から大きなオフィスを借りることに不安を感じていました。
そこで、登記対応のバーチャルオフィスを選択。
「実際に借りるよりも初期コストを80%以上削減できたうえに、港区住所を登記できたことで取引先からの印象も良くなりました。資金を開発費に回せたのが大きかったです。」
現在は事業が拡大し、同じ運営会社のレンタルオフィスへ移転。
バーチャル→リアルオフィスへのスムーズなステップアップも成功の一因となっています。
▶ 事例②:副業から法人化へスムーズに移行
フリーランスとして活動していたBさんは、仕事が増えたタイミングで法人化を検討。しかし、自宅住所で登記することに抵抗があり、バーチャルオフィスを利用しました。
「郵便転送や電話代行もあって、外出中でも業務が止まらないのが便利。自宅住所を公開せずに登記できたので、プライバシー面でも安心です。」
Bさんのように、副業・個人事業主から自然に法人化へステップアップする例も増えています。
▶ 事例③:士業として信頼性を高めるために活用
行政書士として独立したCさんは、クライアント対応を考慮して都内一等地の住所を選びました。
「自分一人の事務所でも、青山住所を使えることで信頼性が上がりました。
相談時に名刺を渡すと『都内で活動されているんですね』と言われることが多いです。」Cさんはコストを抑えながらも、ブランディングと信用力の両立を実現しています。
スモールビジネスの事例
バーチャルオフィスはスタートアップや個人事業主だけでなく、地方企業が東京に拠点を設ける「サテライト利用」にも活用されています。
たとえば、地方のデザイン会社が東京住所を利用して営業拠点を設置することで、都内の取引先とスムーズにやり取りできるようになったケースも。
「東京の住所で会社案内やWebサイトを整えたことで、全国のクライアントからの問い合わせが増えました。」
このように、地方企業が首都圏ビジネスを展開する“第2の拠点”としても需要が高まっています。
領域別の活用法
業種や事業内容によって、バーチャルオフィスの活用方法や得られるメリットは異なります。ここでは、代表的な業種ごとにどのような目的で活用されているのか、そして実際にどんな効果があるのかを具体的にまとめました。
| 業種 | 活用の目的 | メリット |
| IT・Web系 | リモートワーク・オンライン商談中心 | コスト削減・全国対応 |
| コンサル・士業 | 信頼性・ブランド向上 | 一等地住所の利用・印象UP |
| デザイン・制作業 | 顧客対応・郵便受取 | 柔軟な働き方・集中環境 |
| 地方企業 | 東京営業拠点 | 都内取引先との信頼構築 |
利用の実際のメリットとデメリット
メリット
・初期費用・維持費を抑えられる
・信頼感のある住所で登記できる
・郵便転送・電話対応などで効率UP
・プライバシーを守りながら活動できる
デメリット
・実際の執務スペースがない
・会議室などを利用する場合は別料金になることも
・実績の少ない運営会社を選ぶと登記が通らない可能性
デメリットも理解した上で、自分の事業スタイルに合った利用方法を選ぶことが成功のカギです。
コミュニティとネットワーク構築の機会
最近では、バーチャルオフィス契約者同士のコミュニティを運営している会社もあります。THE HUBのように、コワーキングスペースやイベントを通じて他の起業家と交流できる仕組みを設けているところもあり、新たなビジネスチャンスやコラボレーションのきっかけになることも。
「登記だけの利用かと思っていたけど、交流イベントでパートナー企業が見つかった」
といった声も多く、バーチャルオフィスは単なる“住所貸し”にとどまらない価値を持っています。
まとめ
バーチャルオフィスを活用すれば、コストを抑えながらも信頼性の高い事業拠点を持つことができます。特に、これから起業を考えている方や、法人化を検討中の個人事業主にとって、安心してビジネスを始められる実践的な選択肢です。
THE HUBでは、東京都内を中心に全国各地で登記対応可能な拠点を展開しています。郵便転送・会議室利用・法人登記など、起業初期に必要な機能をすべて備えたプランで、あなたの新しいスタートをサポートします。

writing by:nex株式会社 事業企画室
nexでは、レンタルオフィス・コワーキングスペース・バーチャルオフィスに関する情報を、コラム記事を通じてわかりやすく発信しています。
自社サービスに限らず、これから働き方を見直したい方・新しい拠点を検討している方に役立つ業界情報をお届けしていきます。

writing by:nex株式会社 事業企画室
nexでは、レンタルオフィス・コワーキングスペース・バーチャルオフィスに関する情報を、コラム記事を通じてわかりやすく発信しています。
自社サービスに限らず、これから働き方を見直したい方・新しい拠点を検討している方に役立つ業界情報をお届けしていきます。