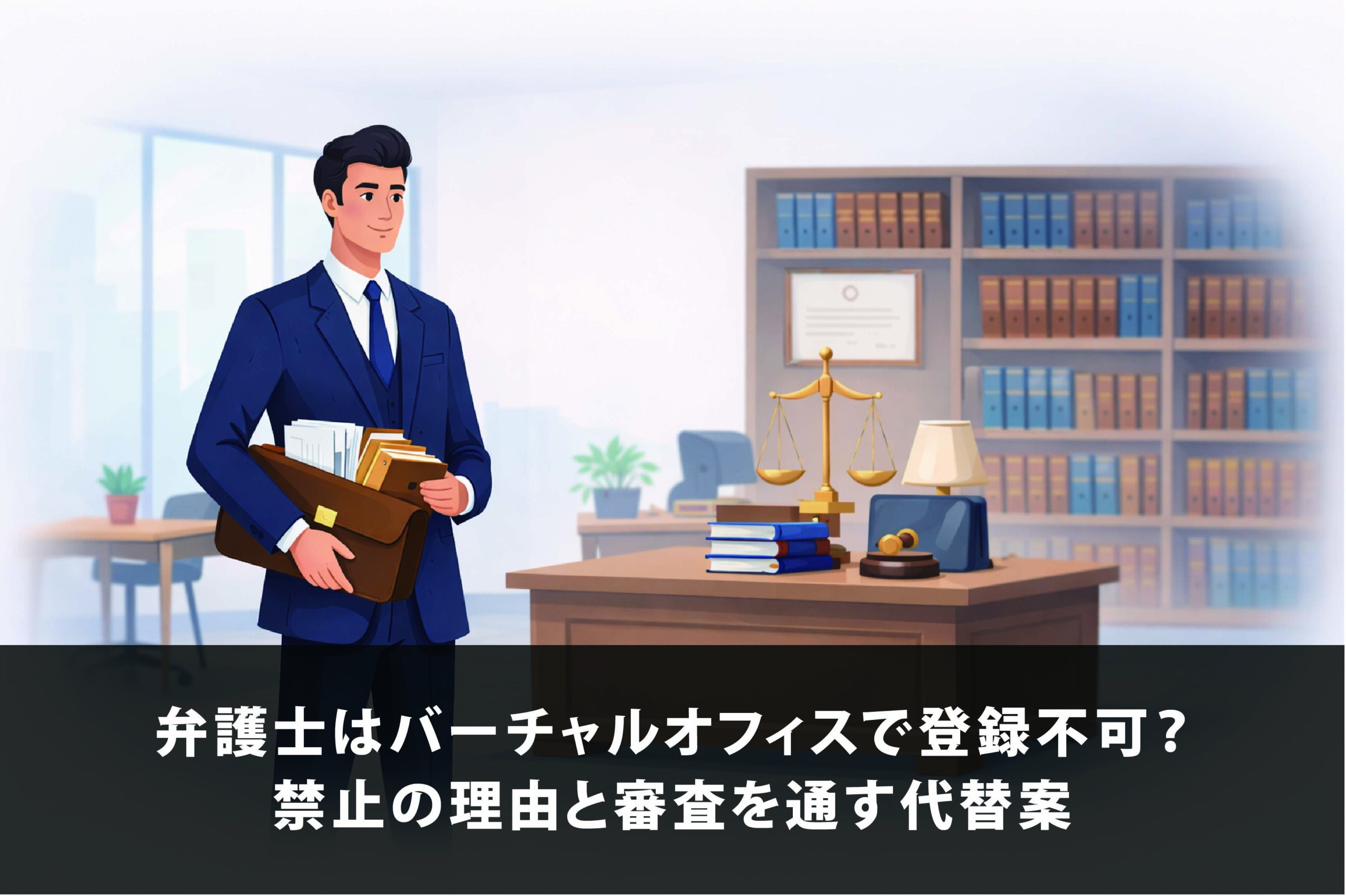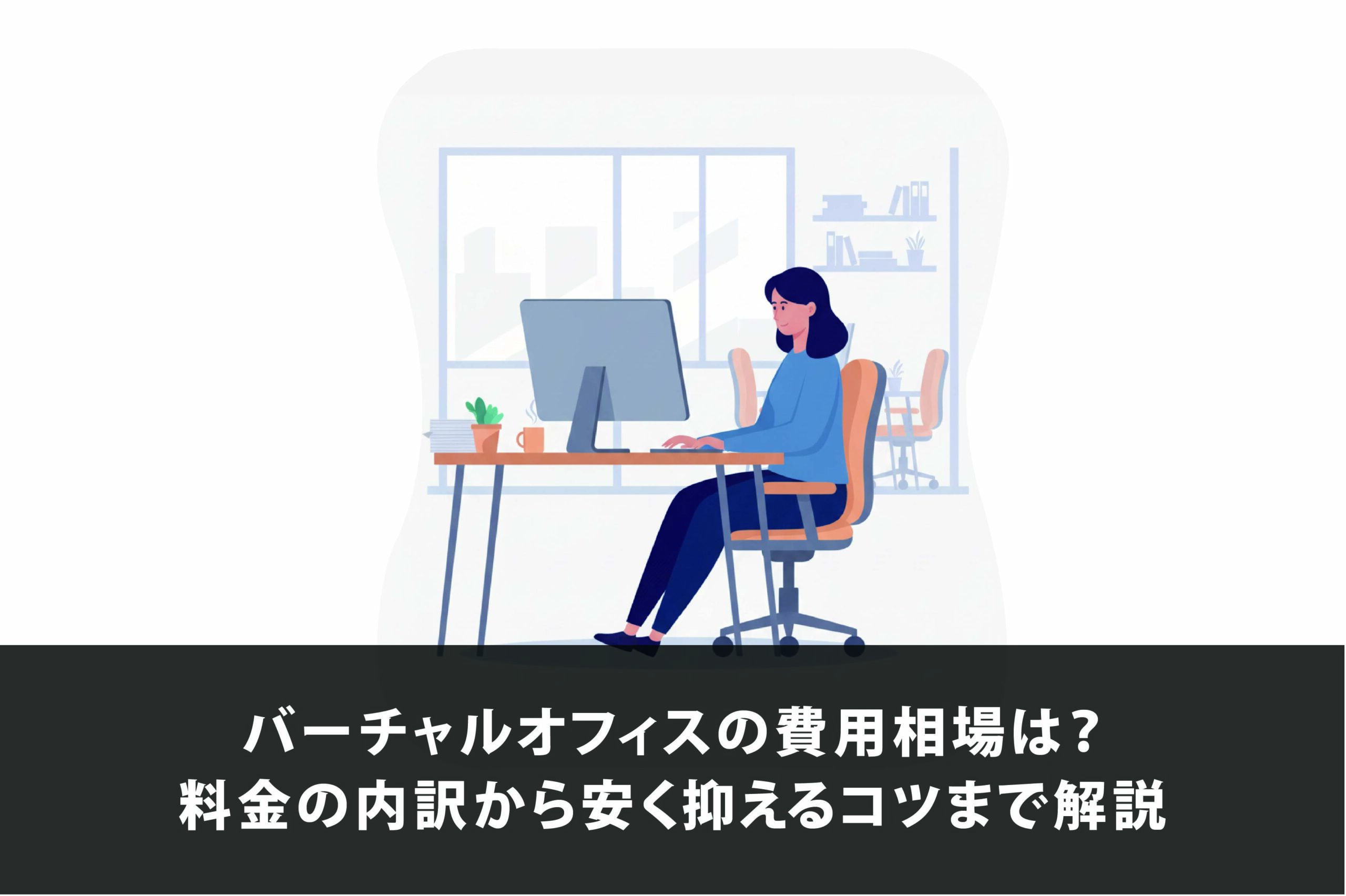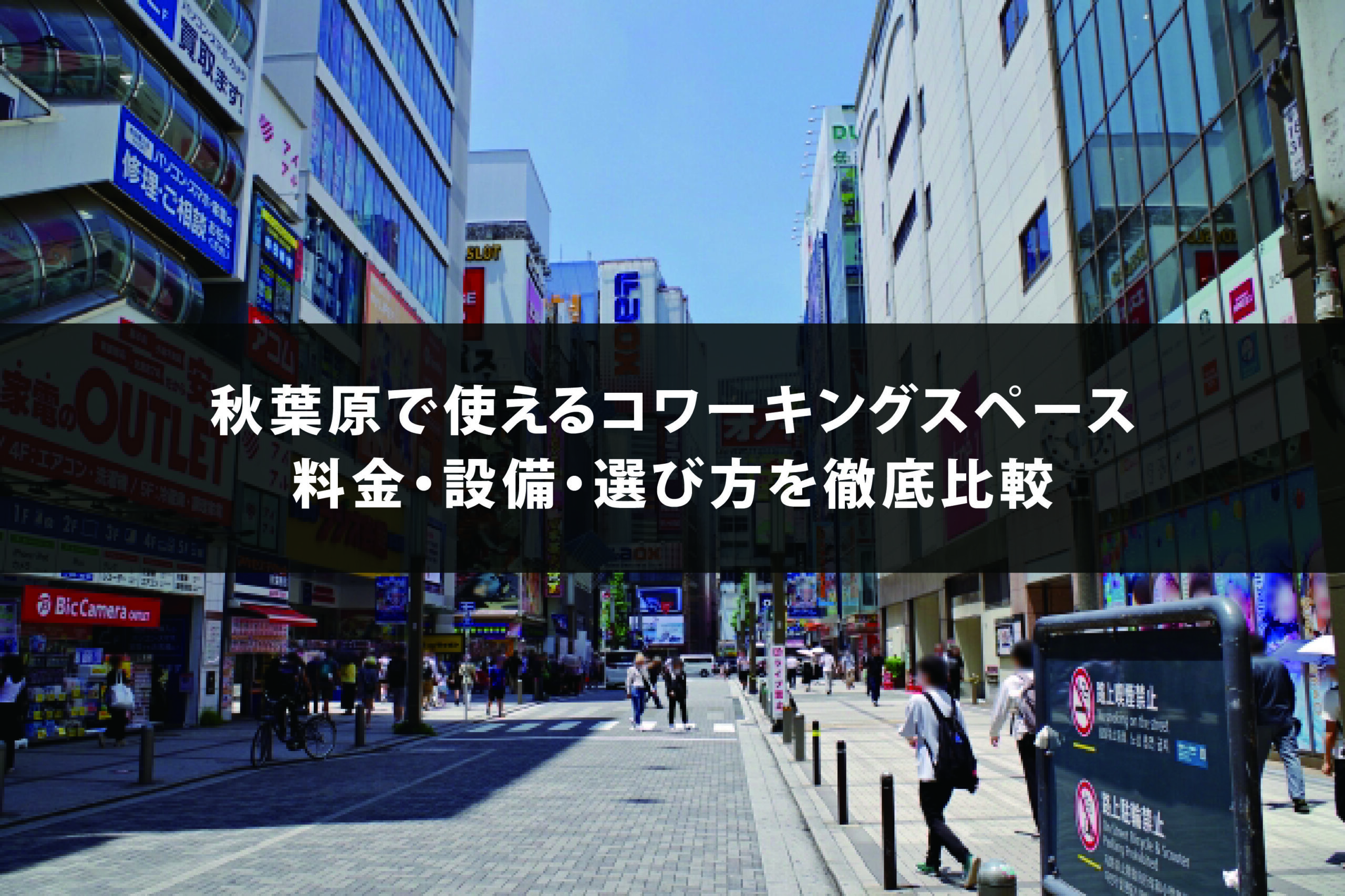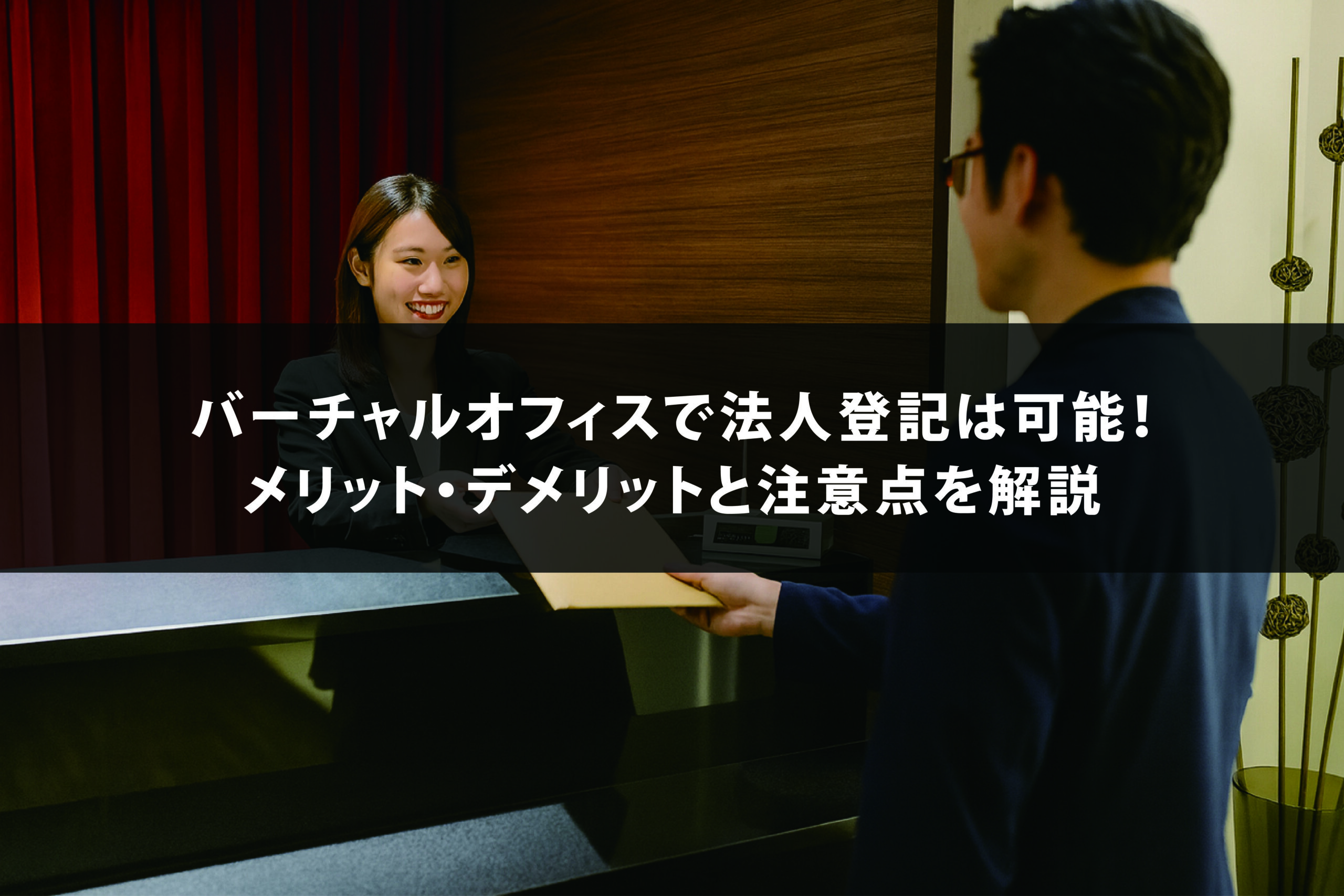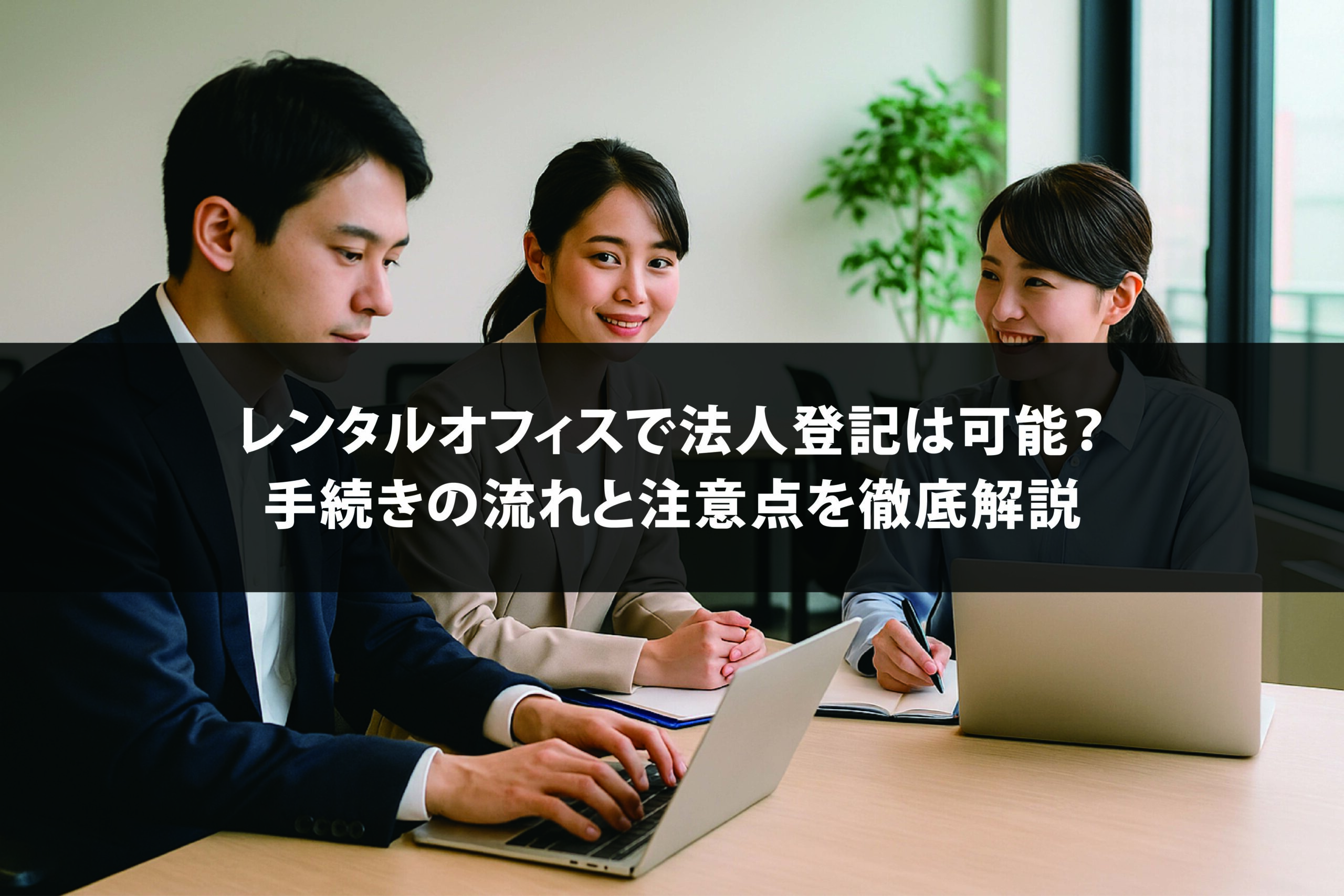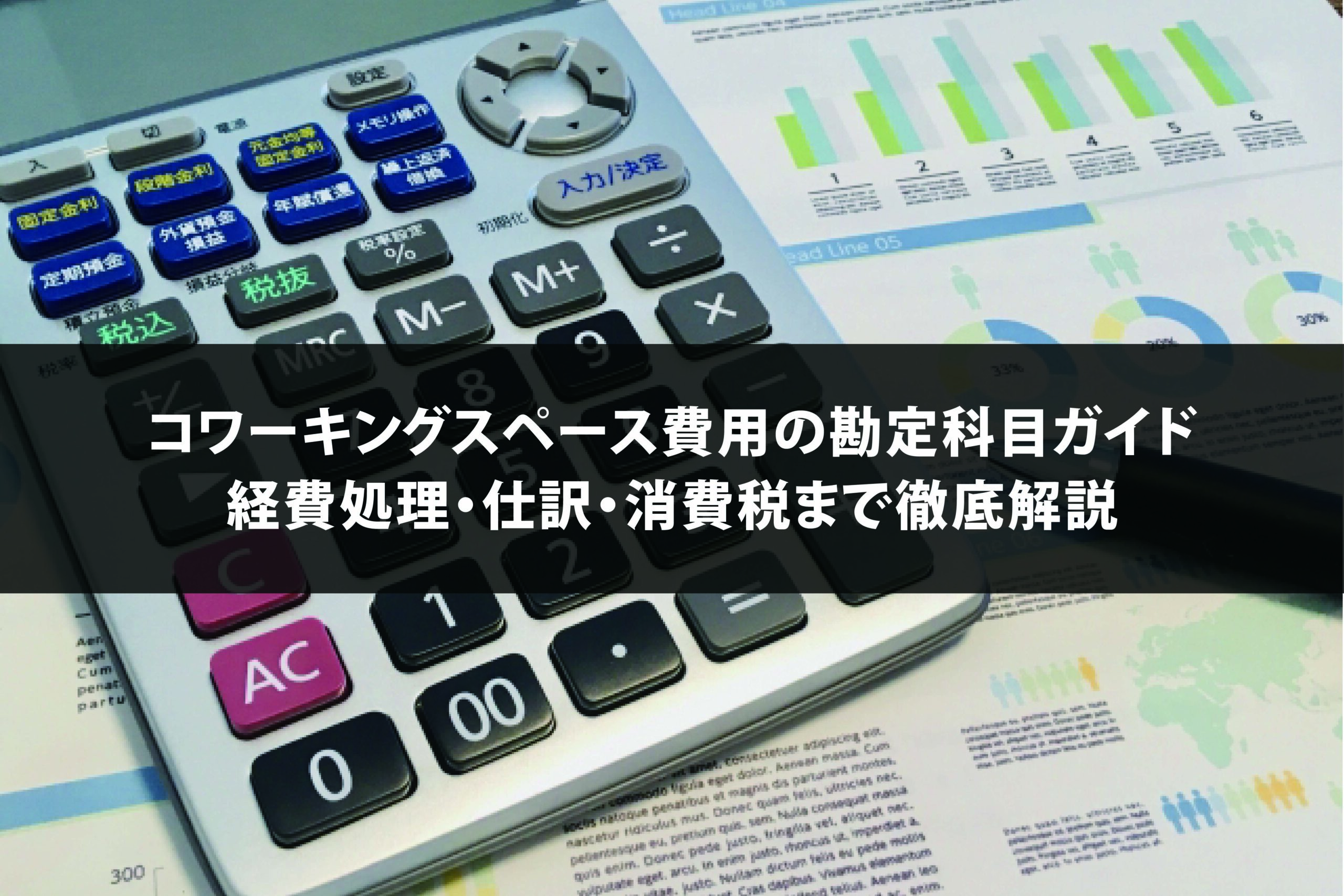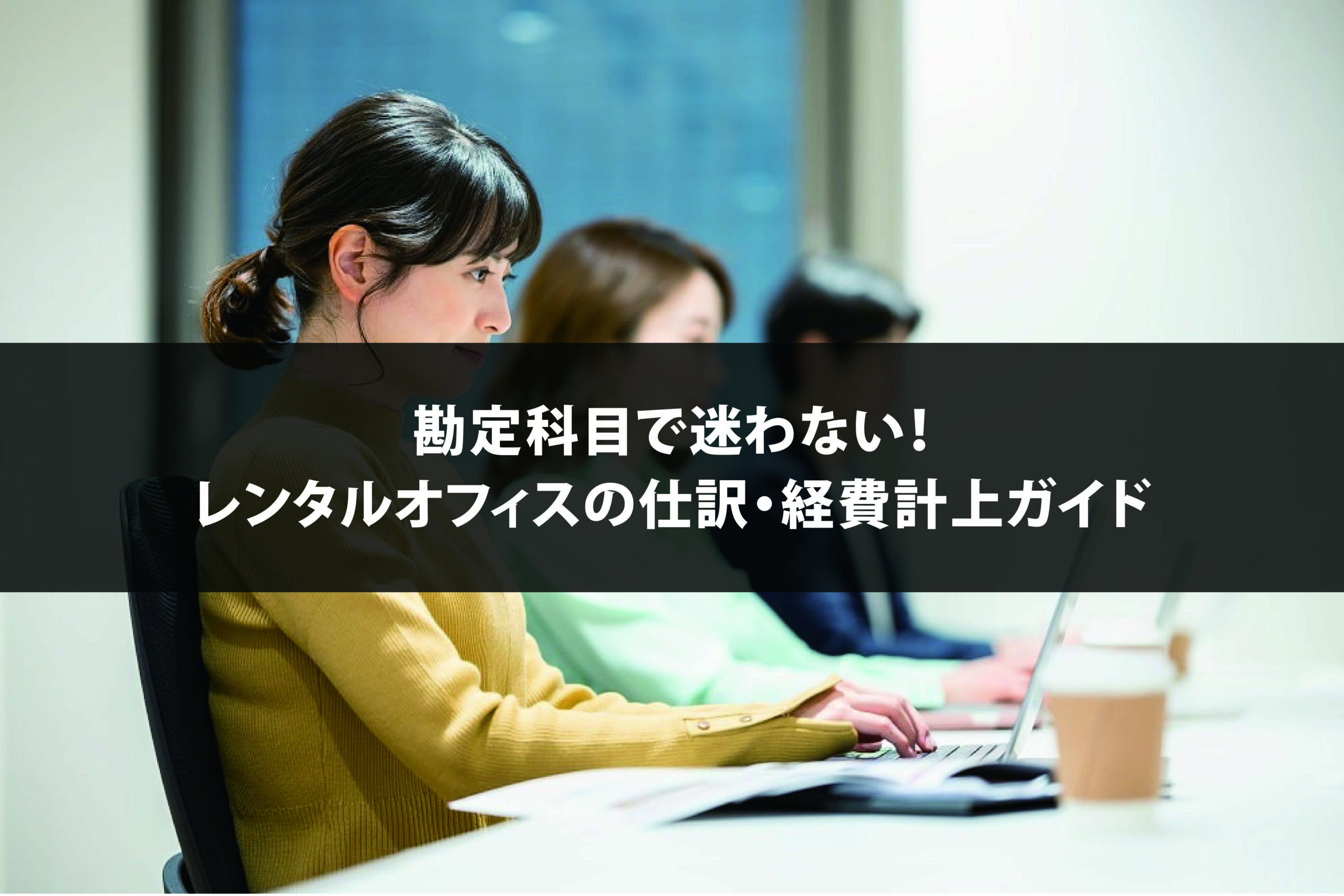バーチャルオフィスの選び方で失敗しない!7つの比較ポイントと注意点を解説
2025年9月4日

近年、働き方の多様化に伴い、物理的なオフィスを持たずに事業を運営するスタイルが広まっています。しかし、事業を始めるには法人登記やWebサイトへの表示のために、信頼できる「住所」が不可欠です。そこで注目されているのが「バーチャルオフィス」です。低コストで事業用住所を確保できる魅力的なサービスですが、多くの選択肢があるため「どう選べば良いのか分からない」と悩む方も少なくありません。
この記事では、バーチャルオフィスの基本的なサービスから、メリット・注意点、そして最も重要な「失敗しない選び方」まで、7つの比較ポイントに沿って詳しく解説します。あなたのビジネスに最適なバーチャルオフィスを見つけ、事業を成功へと導くための一歩を踏み出しましょう。
目次
バーチャルオフィスとは?基本的なサービスを解説
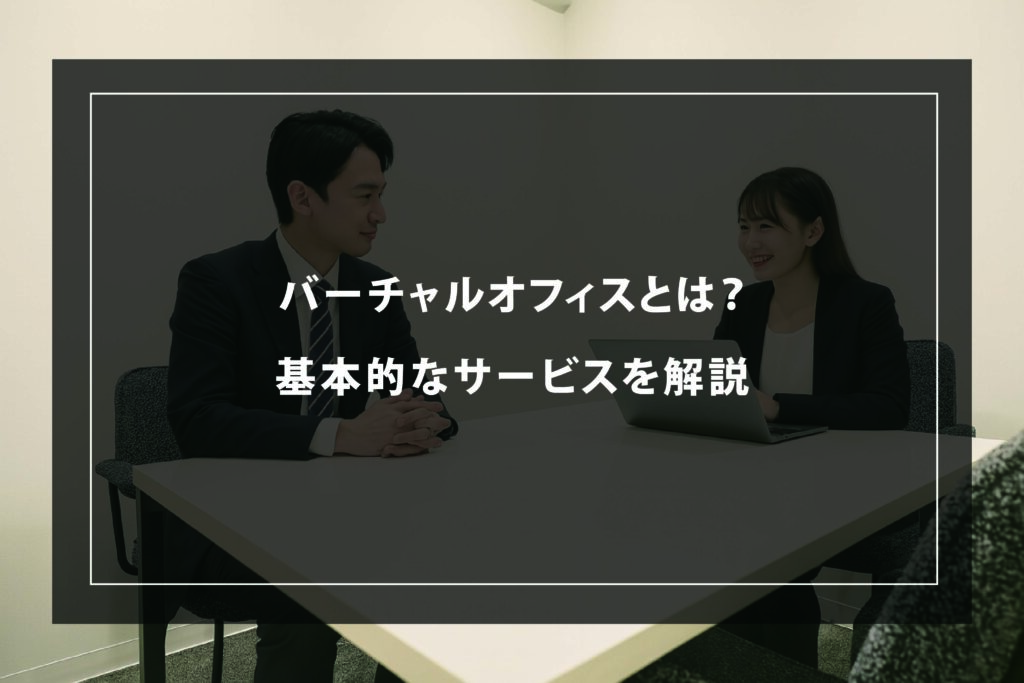
バーチャルオフィスとは、物理的な執務スペースを借りることなく、事業に必要な住所や電話番号などの機能のみをレンタルできるサービスです。 実際のオフィスを構えるよりも大幅にコストを抑えられるため、多くの起業家やフリーランスに活用されています。まずは、バーチャルオフィスが提供する基本的なサービス内容を理解しましょう。
住所貸しサービス
バーチャルオフィスの最も基本的なサービスが、事業用住所のレンタルです。 この住所は、法人登記の際の本店所在地として利用できるほか、名刺やWebサイト、パンフレットなどにも記載できます。特に、都心の一等地の住所を利用できるプランは、企業のブランドイメージや信頼性の向上に繋がります。 自宅の住所を公開せずに済むため、プライバシー保護の観点からも非常に有効です。
郵便物関連サービス
レンタルした住所に届く郵便物や宅配便を受け取り、指定の住所へ転送してくれるサービスも、ほとんどのバーチャルオフィスで提供されています。 転送の頻度(週1回、月1回など)や料金体系は運営会社によって異なるため、自社の郵便物の量に合わせてプランを選ぶことが重要です。 オプションで、郵便物の到着を通知してくれたり、直接受け取りに訪れることもできるサービスもあります。
電話関連サービス
多くのバーチャルオフィスでは、固定電話番号の貸し出しや、かかってきた電話を指定の携帯電話などへ転送するサービスを提供しています。 Webサイトや名刺に市外局番から始まる固定電話番号を記載できると、携帯電話番号のみの場合に比べて顧客や取引先からの信頼性が高まります。さらに、オペレーターが社名で電話応対をしてくれる電話秘書代行サービスを利用すれば、一人で事業を運営していても、しっかりとした組織であるという印象を与えることが可能です。
バーチャルオフィスを利用する5つのメリット
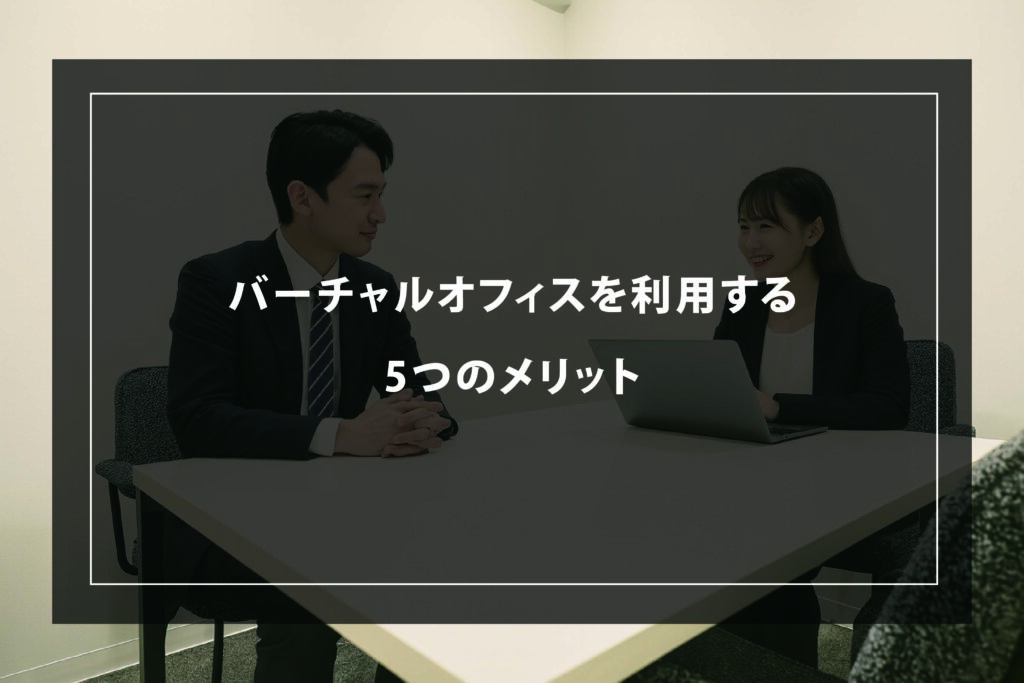
バーチャルオフィスは、コスト削減以外にも多くのメリットを事業者に提供します。ここでは、主な5つのメリットを紹介します。
1)大幅なコスト削減を実現できる
最大のメリットは、オフィスに関わる費用を大幅に削減できる点です。 実際に事務所を賃貸契約すると、高額な保証金や敷金、礼金、毎月の家賃、光熱費などが発生します。バーチャルオフィスであれば、これらの費用が不要になり、月額数千円程度からという低コストで事業に必要な住所を確保できます。これにより、事業の運転資金を他の重要な投資に回すことが可能です。
2)都心の一等地の住所で信頼性を高める
都心の一等地や有名なビジネス街の住所は、それだけで高い信頼性やブランドイメージに繋がります。 物理的にオフィスを構えるのが難しいような場所の住所でも、バーチャルオフィスなら手頃な価格で利用可能です。これにより、顧客や金融機関、取引先に対して、しっかりとした基盤を持つ企業であるという印象を与え、ビジネスを有利に進めることができます。
3)プライバシーを保護できる
フリーランスやネットショップ運営者が自宅で事業を行う場合、特定商取引法などによりWebサイトに住所を公開する必要があります。 自宅住所を公開することに抵抗がある方は多いでしょう。バーチャルオフィスを利用すれば、自宅の住所を公開することなく事業運営が可能となり、プライバシーをしっかりと保護できます。
4)スムーズに事業を開始できる
物理的なオフィスを契約する場合、物件探しから内装工事、インフラ整備まで多くの時間と手間がかかります。一方、バーチャルオフィスは申し込みから審査、契約までの手続きがオンラインで完結することが多く、最短即日で利用を開始できる場合もあります。 これにより、事業の立ち上げをスピーディーに行うことが可能です。
5)豊富なオプションサービスを利用できる
バーチャルオフィスは住所貸しだけでなく、ビジネスを円滑に進めるための多様なオプションを提供しています。 前述の郵便物転送や電話関連サービスのほか、会社設立の代行サポート、法人口座の開設支援、経理代行など、事業運営に必要な業務をサポートしてくれるサービスもあります。
契約前に知っておきたいバーチャルオフィスの注意点
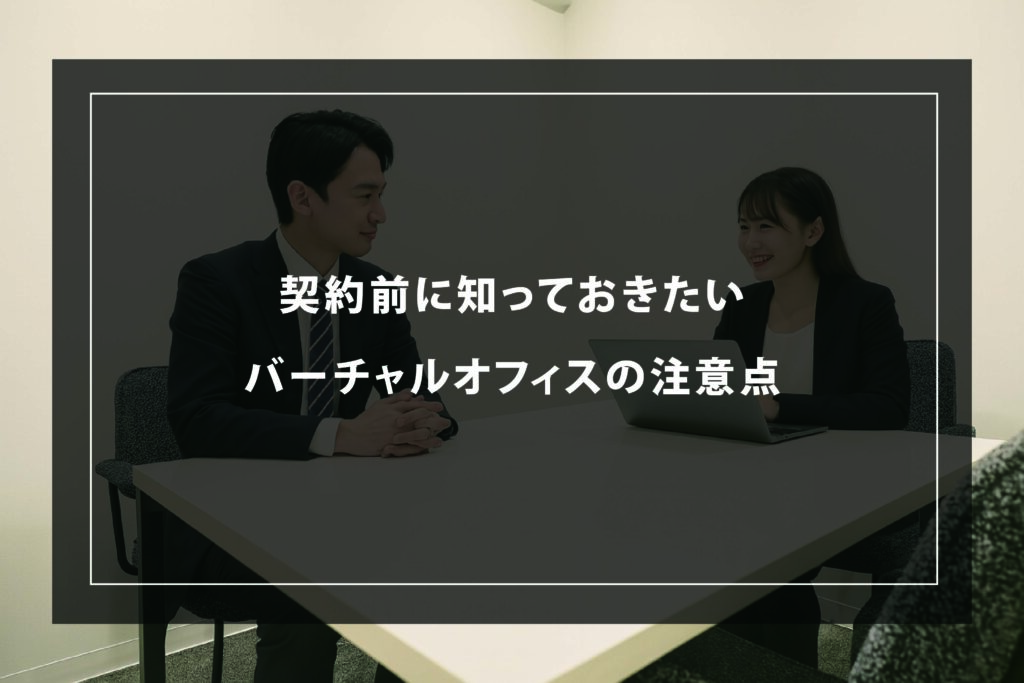
多くのメリットがある一方で、バーチャルオフィスには契約前に知っておくべき注意点も存在します。後々のトラブルを避けるためにも、以下の点を必ず確認してください。
事業内容によっては利用・登記ができない
すべての業種でバーチャルオフィスが利用できるわけではありません。例えば、弁護士や税理士などの士業、職業紹介業、人材派遣業、建設業、不動産業、古物商などは、事業所の面積要件や独立した区画が必要となるため、バーチャルオフィスでの許認可取得や登記が認められない場合があります。 自社の事業がバーチャルオフィスで運営可能か、事前に許認可の要件を確認することが不可欠です。
銀行の法人口座開設で審査が厳しくなる場合がある
バーチャルオフィスを利用していると、一部の金融機関では法人口座の開設審査が厳しくなる傾向があります。これは、過去にバーチャルオフィスが犯罪に利用されたケースがあるため、事業実態の確認を慎重に行う必要があるからです。対策として、事業計画書やWebサイトをしっかりと作り込み、事業の実態を明確に説明できるように準備しておくことが重要になります。また、法人口座開設の実績が豊富なバーチャルオフィスを選ぶのも一つの手です。
運営会社の倒産リスクがある
万が一、契約しているバーチャルオフィスの運営会社が倒産・廃業してしまった場合、その住所は利用できなくなります。そうなると、本店所在地の変更登記が必要となり、登録免許税(3万円)や専門家への依頼費用、名刺やWebサイトの修正費用など、予期せぬコストと手間が発生します。 こうしたリスクを避けるためにも、運営会社の経営状況や運営実績を事前に確認することが大切です。
失敗しないバーチャルオフィスの選び方!7つの比較ポイント
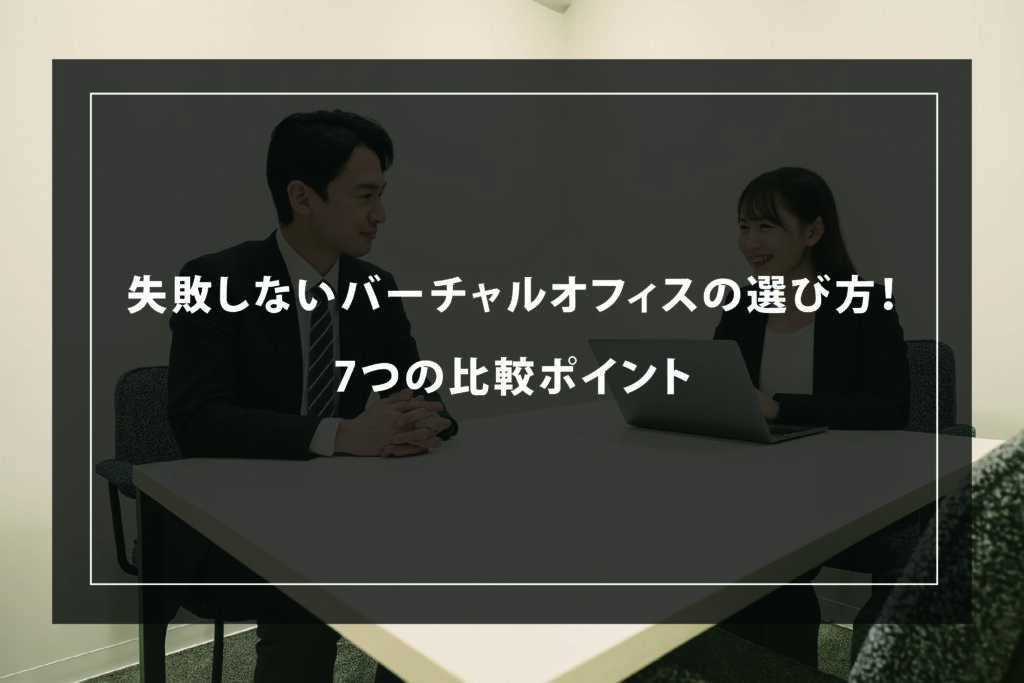
数多くのバーチャルオフィスの中から、自社に最適なサービスを見つけるための7つの比較ポイントを解説します。これらのポイントを一つずつチェックし、後悔のない選択をしましょう。
ポイント1:初期費用と月額料金の妥当性を確認する
料金は最も重要な比較ポイントの一つですが、単に月額料金の安さだけで選ぶのは危険です。入会金や保証金などの初期費用、基本料金に含まれるサービス内容、そして追加で発生する可能性のあるオプション料金を全て含めた「総額」で比較検討することが重要です。
| 料金項目 | チェックポイント |
| 初期費用 | 入会金、保証金、事務手数料はいくらか |
| 月額基本料金 | どのサービスが基本料金に含まれているか (住所利用、郵便物転送の回数など) |
| オプション料金 | 郵便物の即時転送、電話秘書代行、会議室利用など、 利用したいサービスの料金はいくらか |
| その他 | 契約更新料や解約金は発生するか |
特に郵便物転送は、基本料金に含まれる回数を超えると都度料金が発生することが多いので、自社の郵便物の量を見越してプランを選ぶ必要があります。
ポイント2:事業イメージに合う住所・立地を選ぶ
バーチャルオフィスの住所は、あなたの会社の「顔」となります。IT系なら渋谷、ファッション系なら青山や表参道、信頼性が重視されるなら丸の内や銀座など、自社の事業内容やブランドイメージに合った住所を選ぶことで、ビジネスにプラスの効果をもたらします。 また、郵便物の受け取りや会議室の利用で実際に訪れる可能性がある場合は、自宅や主要な取引先からのアクセスが良い場所を選ぶと便利です。
ポイント3:自社に必要なサービス内容が揃っているか確認する
住所貸し以外にどのようなサービスが必要かを明確にし、それが基本プランに含まれているか、あるいはオプションで利用可能かを確認しましょう。 例えば、郵便物が多いなら転送頻度の高いプラン、顧客からの電話対応が重要なら電話秘書代行サ、打ち合わせが多いなら会議室利用が必須となります。不要なサービスが多く含まれる高額なプランは避け、自社の事業フェーズに合わせて過不足のないサービスを選びましょう。
ポイント4:法人登記が可能かしっかりと確認する
会社設立を目的としてバーチャルオフィスを利用する場合は、その住所で法人登記が可能かどうかを必ず確認してください。 運営会社や料金プランによっては、法人登記が認められていない場合があります。Webサイトに「法人登記可」と明記されているか、契約前に問い合わせて確実な情報を得ることが重要です。
ポイント5:会議室などの物理的スペースの利用可否を確認する
普段はリモートワークでも、取引先との商談やチームでのミーティングなど、対面での打ち合わせが必要になる場面はあります。 そのような場合に備え、会議室やワークスペースをレンタルできるバーチャルオフィスは非常に便利です。 利用料金、部屋の広さや設備、予約のしやすさなどを事前に確認しておきましょう。契約前に内見が可能であれば、オフィスの雰囲気や清潔感を実際に確かめておくことをお勧めします。
ポイント6:運営会社の実績と信頼性を確認する
前述の倒産リスクを避けるため、運営会社の実績と信頼性は入念にチェックしましょう。 運営歴が長いか(5年以上が目安)、資本金は十分か、利用者数や拠点数は多いか、といった点は安定性を判断する材料になります。 また、入会審査を厳格に行っているかも重要なポイントです。審査が甘いと、犯罪目的の業者が同じ住所を利用するリスクが高まり、住所のブランド価値が下がる恐れがあるためです。
ポイント7:契約期間や解約条件を確認する
契約後のトラブルを避けるために、最低契約期間や解約手続きの方法、解約金の有無といった契約条件も事前に確認しておきましょう。 特に、「解約は何ヶ月前までに申し出る必要があるか」という点は重要です。事業の状況変化に柔軟に対応できるよう、契約内容をしっかりと理解した上で契約に進みましょう。
バーチャルオフィス契約までの基本的な流れ
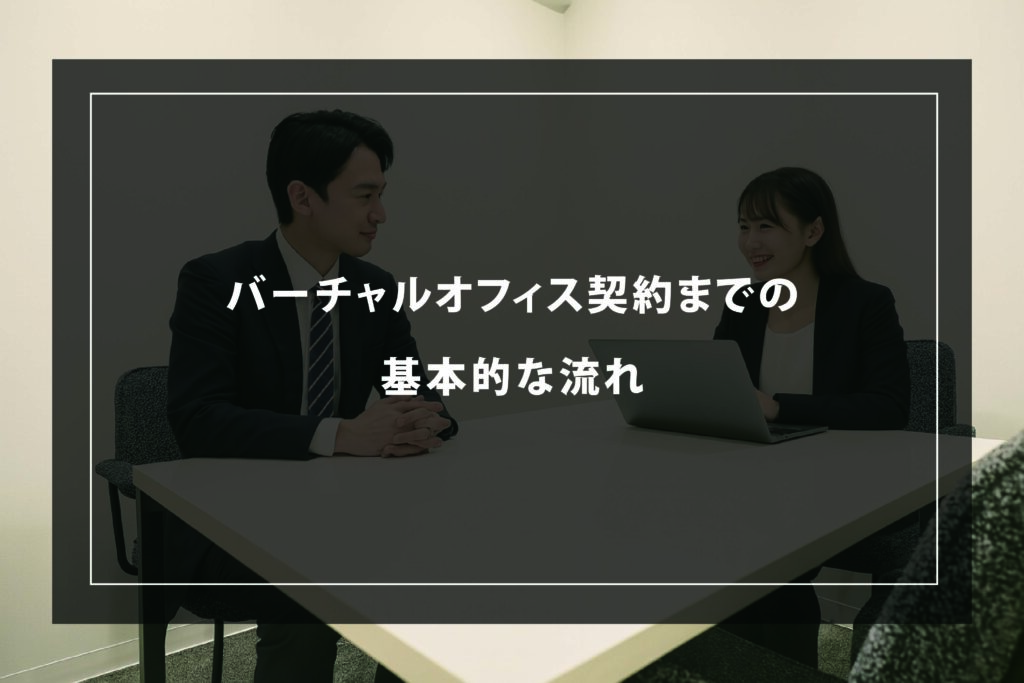
自分に合ったバーチャルオフィスを見つけたら、契約に進みます。ここでは、一般的な契約までの流れを解説します。
手順1:利用したいサービスを明確にする
まずは、自社の事業に「何が必要で、何が不要か」を整理します。 法人登記は必要か、郵便物は月に何通くらい届く見込みか、電話対応は必要か、会議室は利用するかなどをリストアップし、サービスの優先順位をつけましょう。
手順2:複数の運営会社を比較検討する
手順1で明確にした要件をもとに、複数のバーチャルオフィス運営会社を比較します。料金、住所、サービス内容、運営会社の信頼性など、先ほど解説した7つのポイントに沿って検討し、候補を2~3社に絞り込みます。
手順3:申し込みと審査
利用したいバーチャルオフィスが決まったら、公式Webサイトの申し込みフォームから手続きを行います。その後、運営会社による入会審査が行われます。審査では、申込者の本人確認書類や、法人の場合は登記簿謄本などの提出が必要です。この審査は、犯罪収益移転防止法に基づくものであり、信頼できる運営会社の証でもあります。
手順4:契約と利用開始
審査に通過すると、契約手続きと初期費用の支払いへと進みます。これらが完了すれば、正式にバーチャルオフィスの利用を開始できます。多くのサービスでは、契約後すぐに住所を利用して法人登記の手続きなどを進めることが可能です。
よくある質問
Q. バーチャルオフィスは違法ではないですか?
A. 結論から言うと、バーチャルオフィスの利用自体は合法であり、違法ではありません。 ただし、前述の通り、特定の許認可が必要な業種では利用が認められない場合があります。また、違法な事業目的で住所を利用することは固く禁じられています。信頼できる運営会社を選び、正当な事業目的で利用する限り、法的な問題はありません。
Q. 契約前に内見はできますか?
A. 運営会社によりますが、会議室やワークスペースを併設しているバーチャルオフィスでは、内見に対応している場合があります。 内見が可能な場合は、オフィスの雰囲気、受付スタッフの対応、建物のグレードなどを直接確認できる絶好の機会です。 不安な点があれば、積極的に内見を申し込むことをお勧めします。
Q. 地方在住でも都心のバーチャルオフィスを契約できますか?
A. はい、問題なく契約できます。バーチャルオフィスは物理的なオフィスに通う必要がないため、居住地に関わらず、どの地域の住所でも利用することが可能です。 地方に住みながら都心の一等地にビジネス拠点を持ち、都市部の企業と取引を行うといった活用方法も一般的です。
まとめ
バーチャルオフィスは、低コストで事業の信頼性を高め、プライバシーを守ることができる、現代のビジネス環境に適した非常に便利なサービスです。しかし、その価値を最大限に引き出すためには、自社の事業内容や目的に合ったサービスを慎重に選ぶ必要があります。
本記事で解説した「7つの比較ポイント」を参考に、料金、住所、サービス内容、運営会社の信頼性などを総合的に比較検討し、あなたのビジネスにとって最適なパートナーとなるバーチャルオフィスを見つけてください。
▶全国60拠点以上から選べる「THE HUB」のバーチャルオフィスでは、信頼性の高い法人登記住所・郵便転送・コストパフォーマンスに優れたプランを提供しています。のバーチャルオフィスでは、信頼性の高い法人登記住所・郵便転送・コストパフォーマンスに優れたプランを提供しています。
スタートアップや個人事業主の第一歩に、安心と実用性を両立した環境をお探しの方は、ぜひ一度ご覧ください。

writing by:nex株式会社 事業企画室
nexでは、レンタルオフィス・コワーキングスペース・バーチャルオフィスに関する情報を、コラム記事を通じてわかりやすく発信しています。
自社サービスに限らず、これから働き方を見直したい方・新しい拠点を検討している方に役立つ業界情報をお届けしていきます。