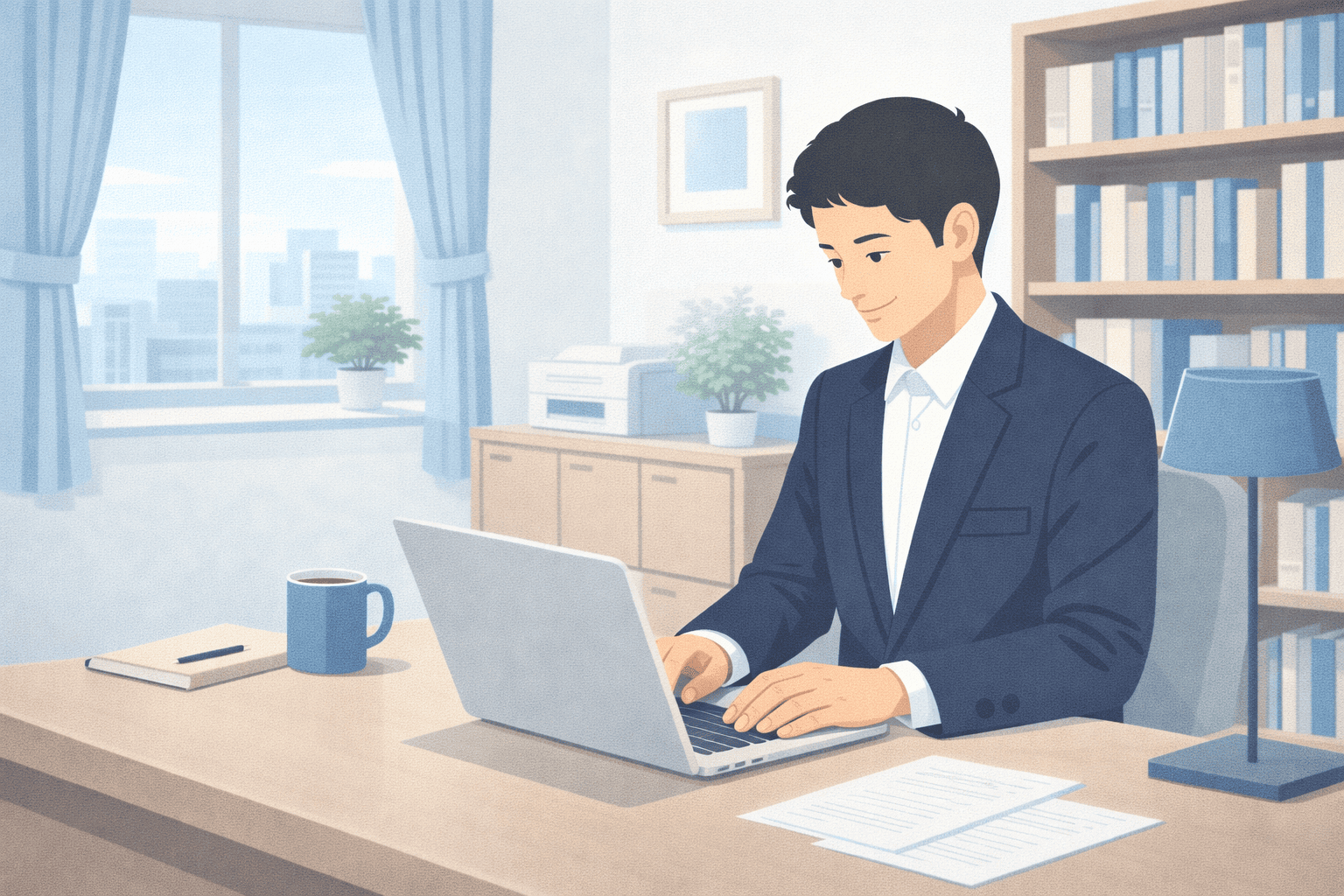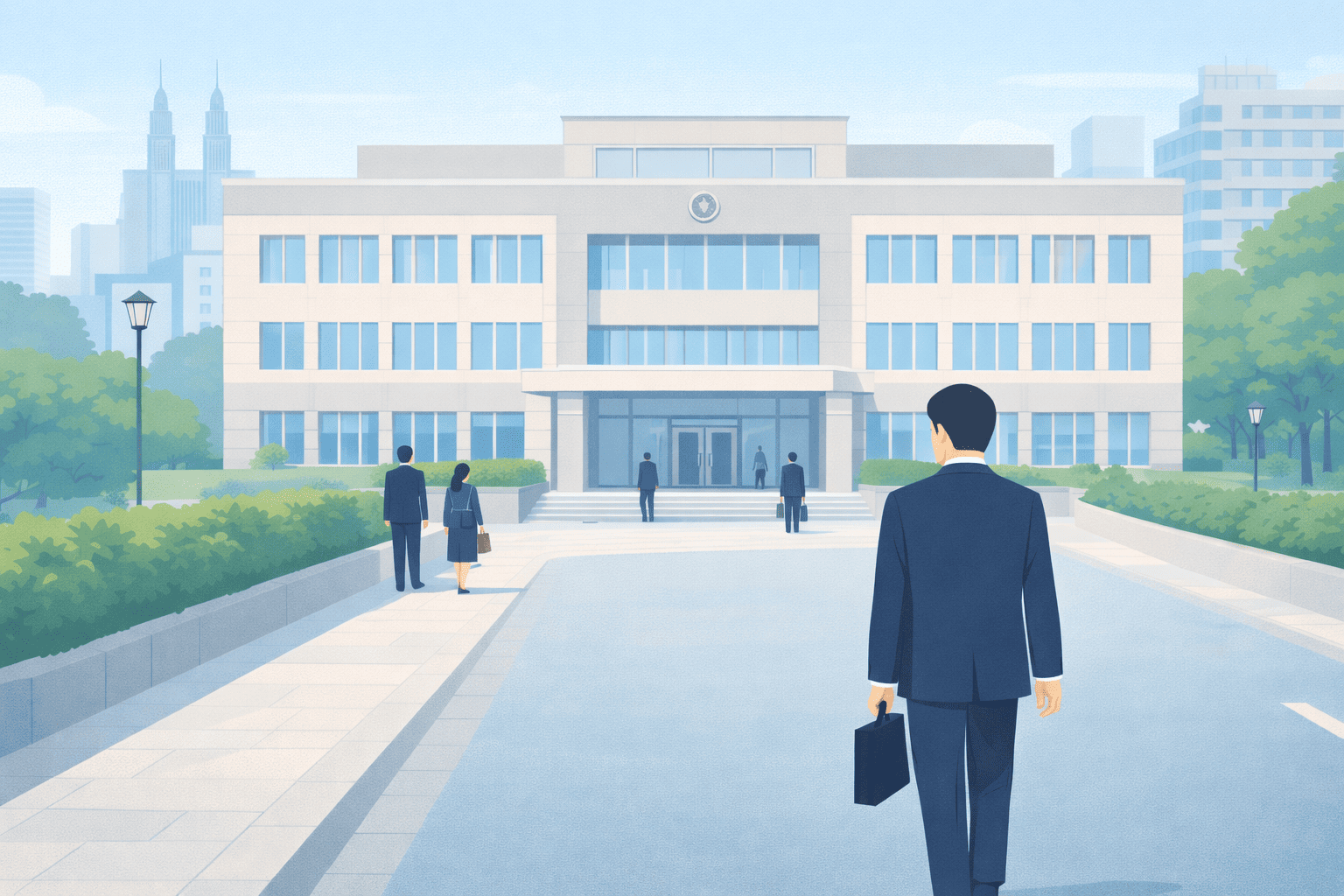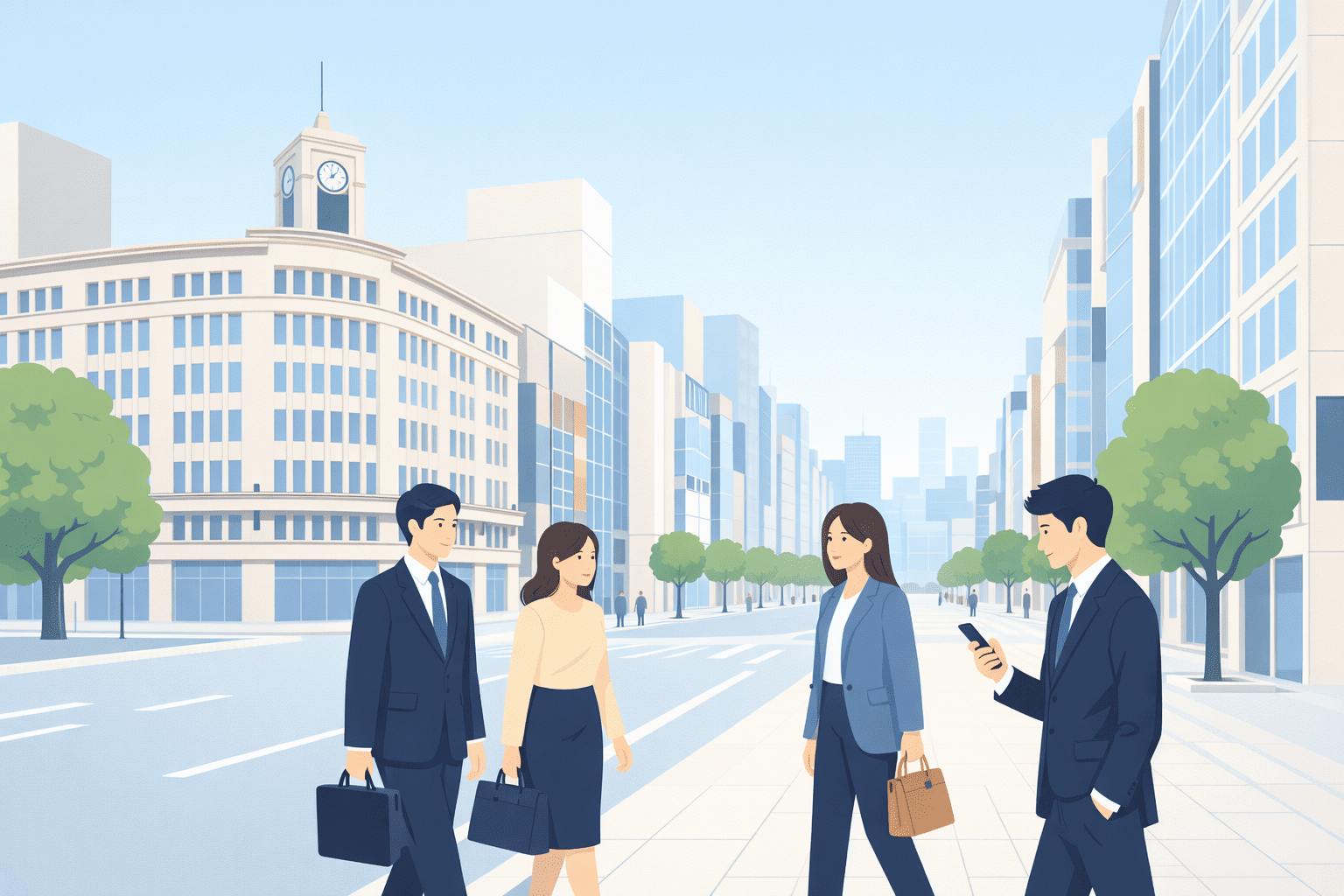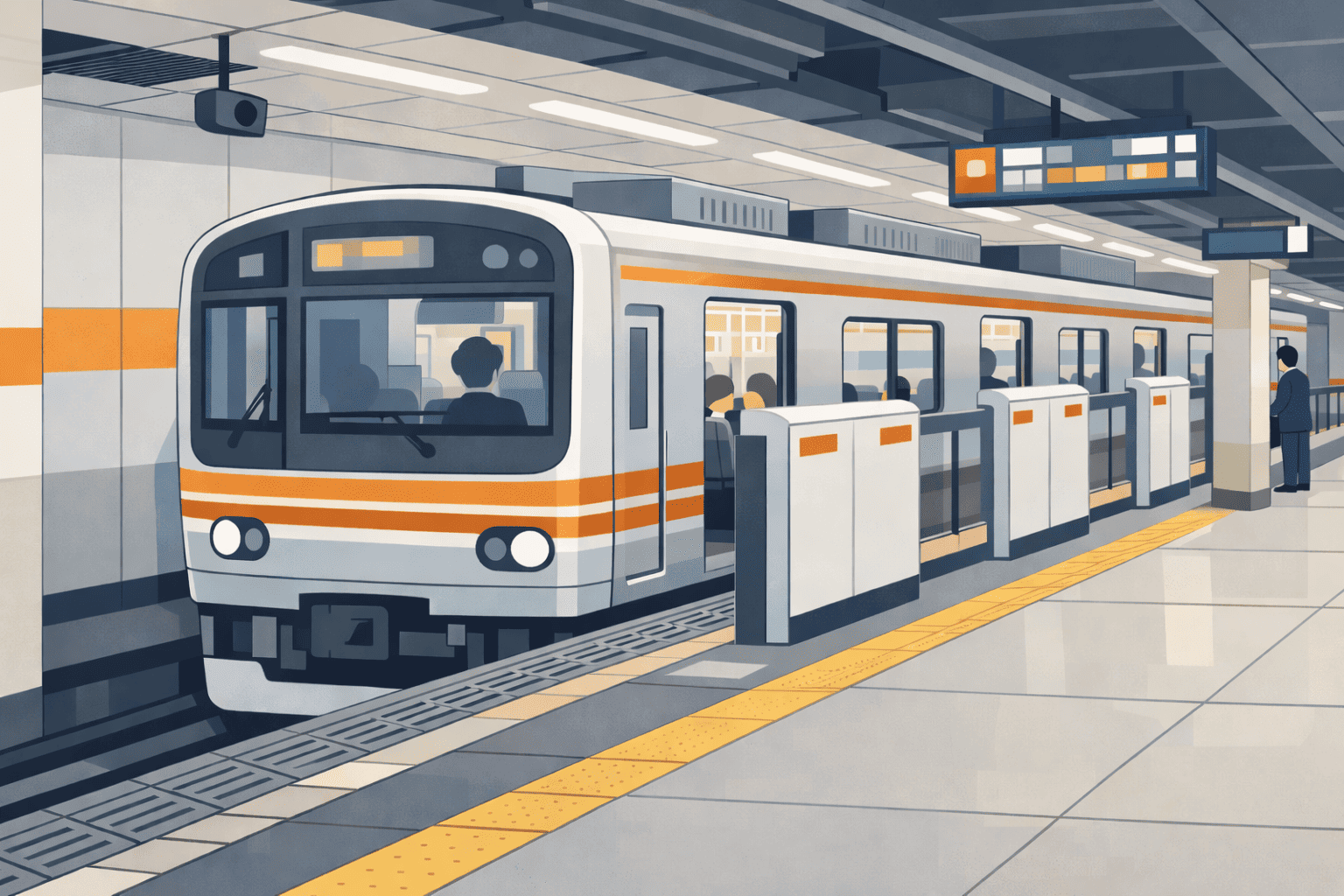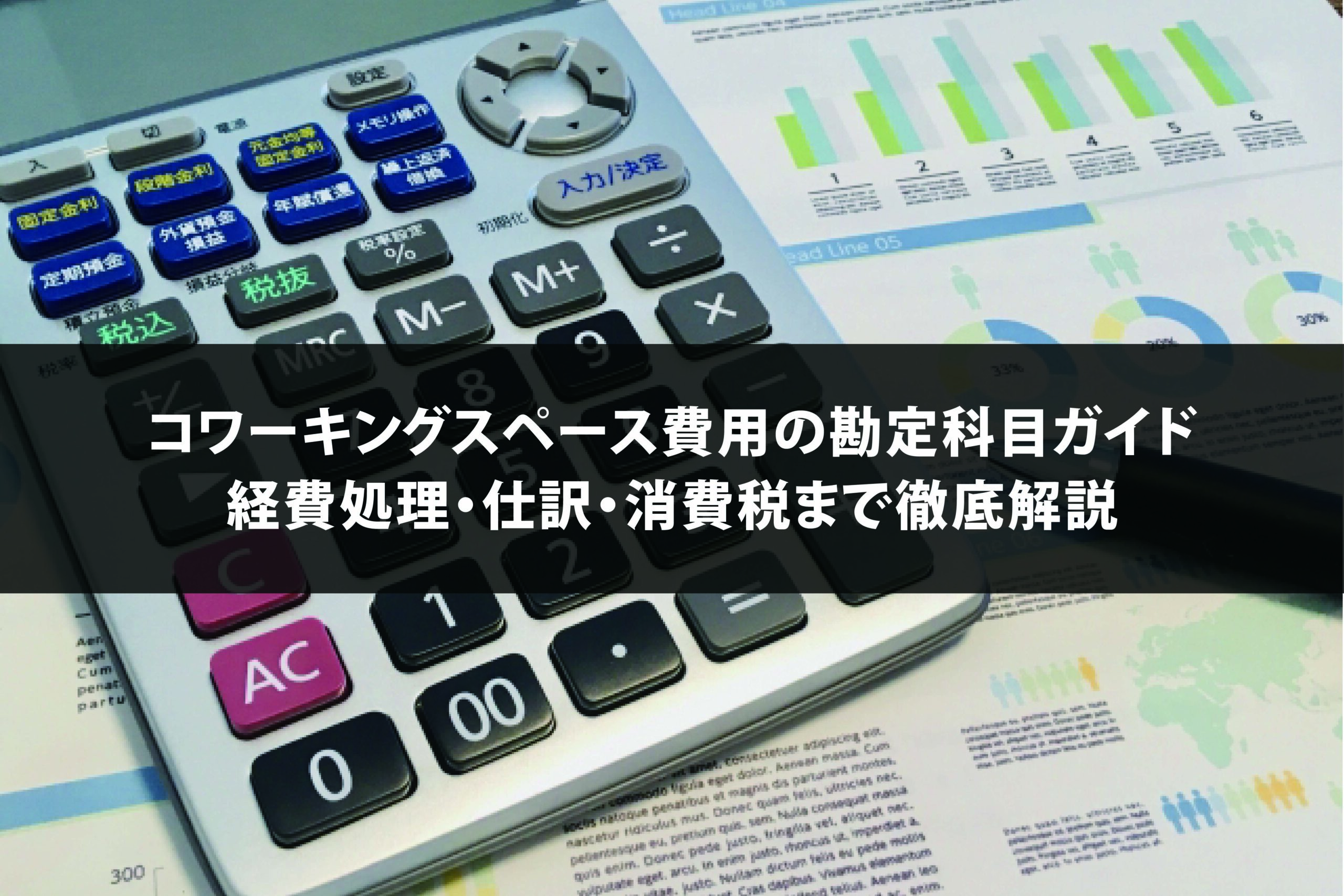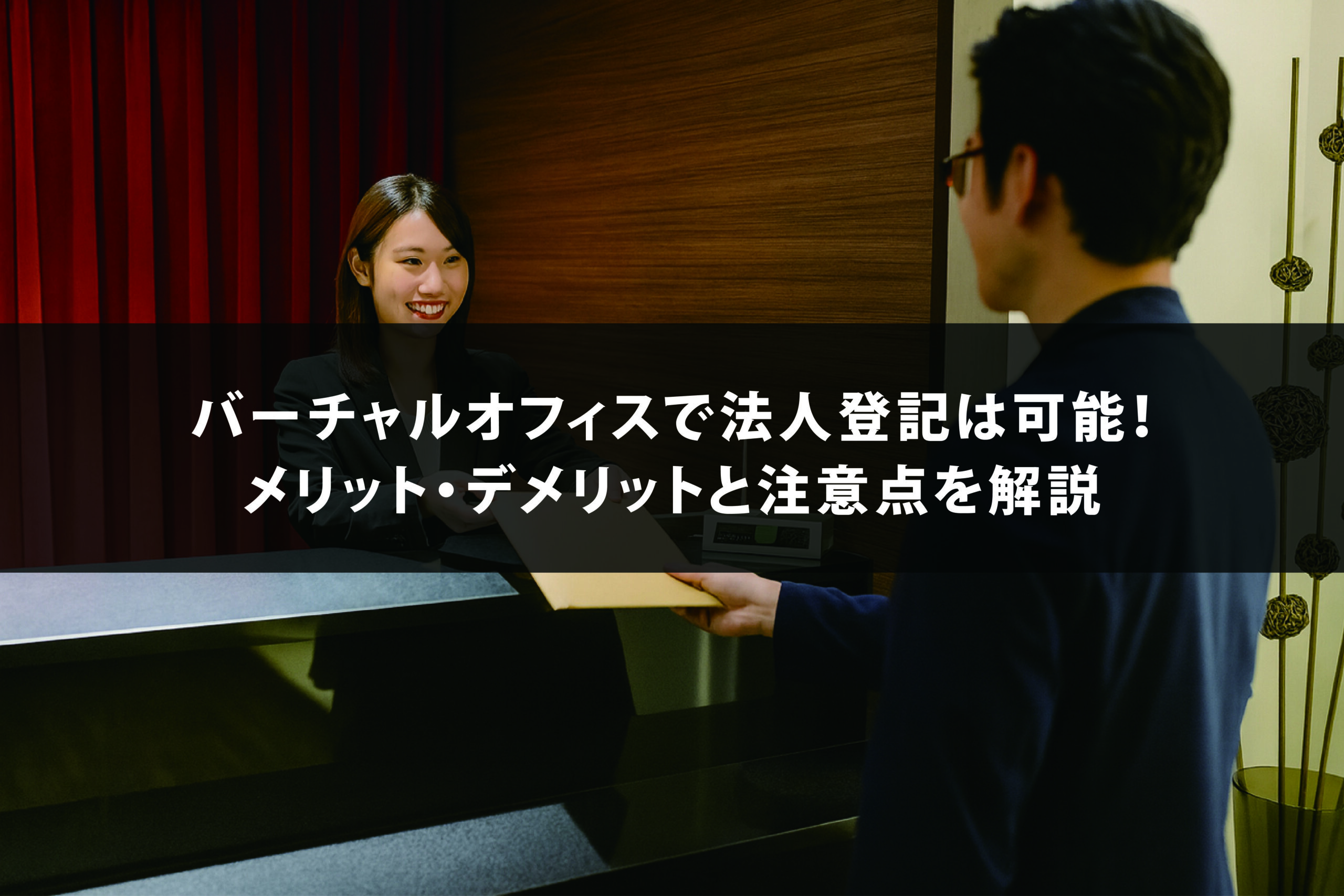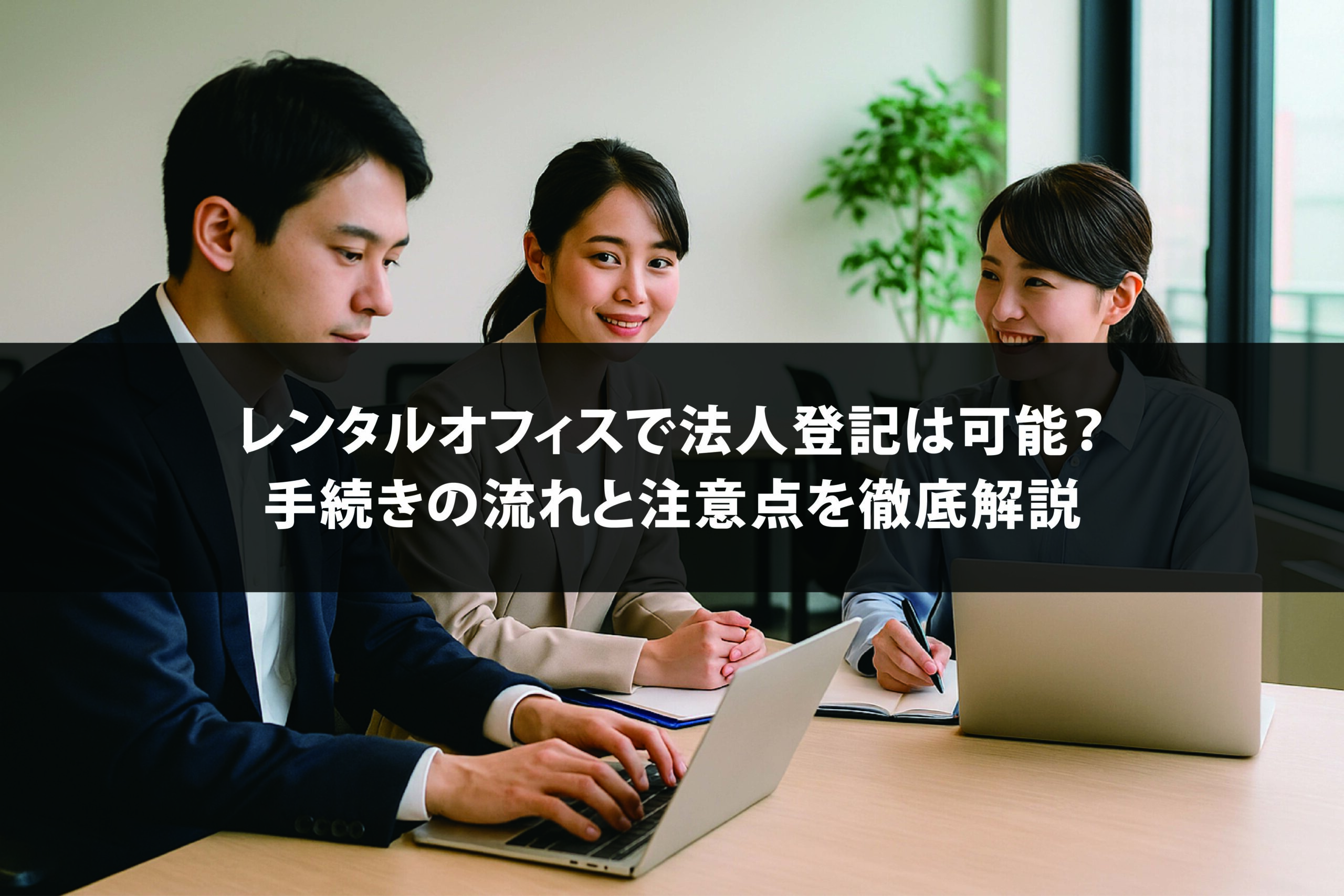勘定科目で迷わない!レンタルオフィスの仕訳・経費計上ガイド
2025年7月25日
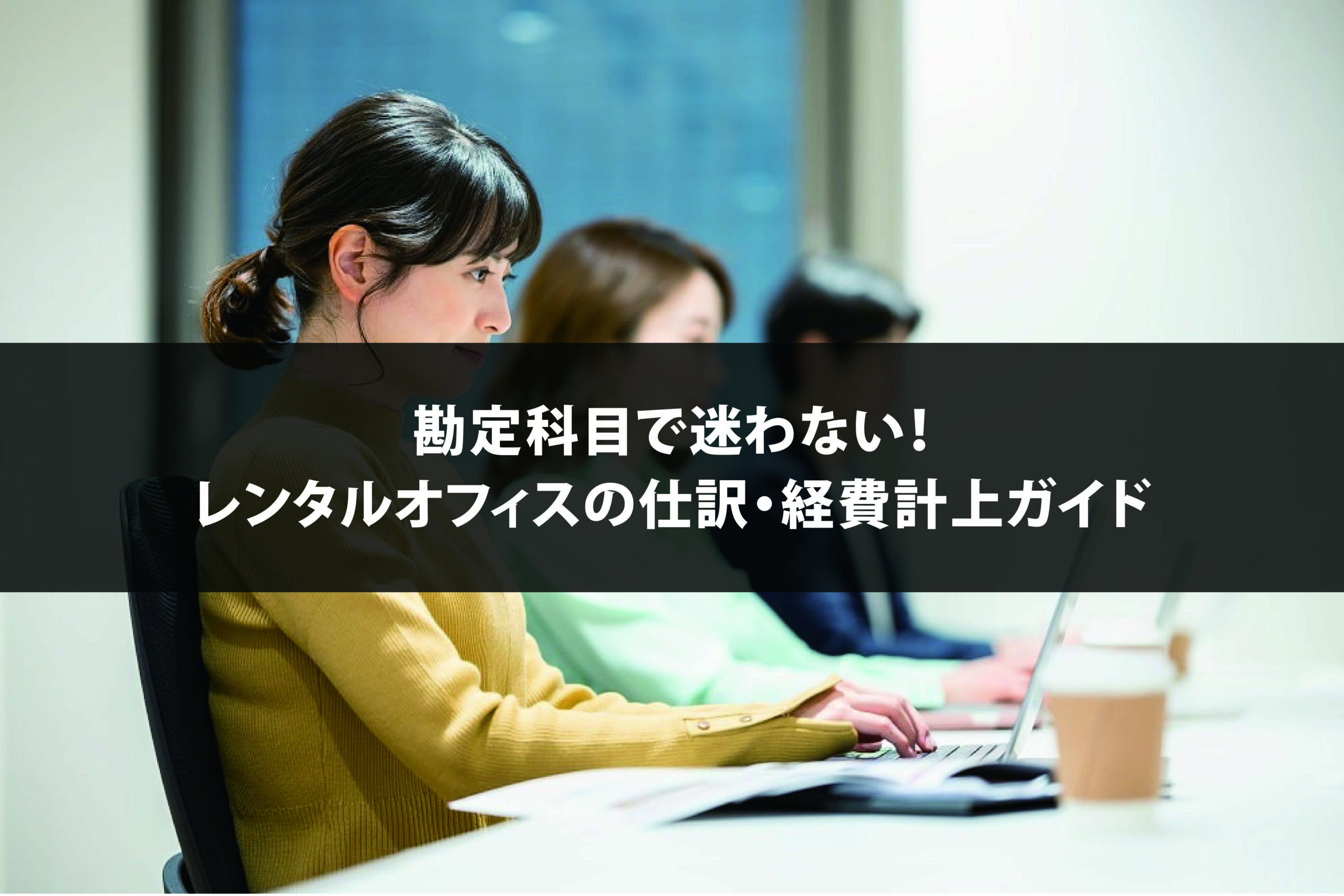
レンタルオフィスを利用しているけれど、「この費用、どう処理すればいいの?」と悩む経理担当者や個人事業主は少なくありません。特にTHE HUBのように、家具・ネット・登記サービスなどが一体化した料金体系の場合、会計処理の判断に迷うことがあるかもしれません。家具付き、ネット完備、登記可能など便利なサービスがセットになっているため、勘定科目の判断に迷うことも多いはずです。
本記事では、そんな悩みを解決するために、THE HUBのようなサービスを想定しながら、レンタルオフィスの費用に関する適切な勘定科目の選び方や仕訳例、注意点をわかりやすく解説します
目次
レンタルオフィスの勘定科目は「賃借料」か「地代家賃」が基本
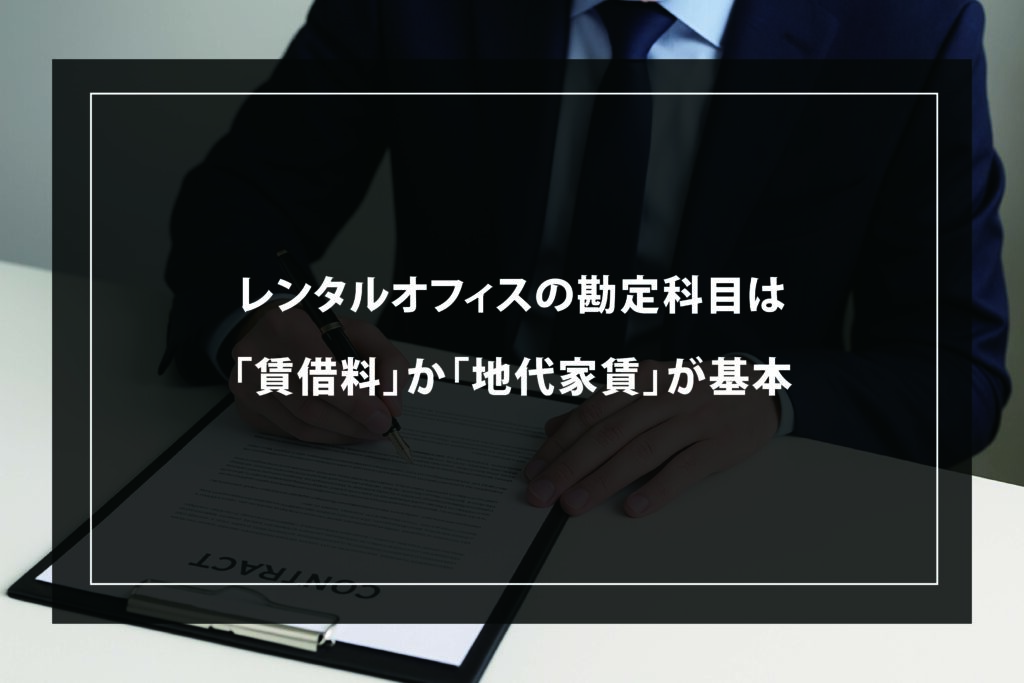
レンタルオフィスの月額利用料などを経費として計上する際、基本となる勘定科目は「賃借料(ちんしゃくりょう)」または「地代家賃(じだいやちん)」です。どちらも費用を支払って何かを借りる際に使用する勘定科目ですが、その性質に違いがあります。どちらで処理しても税務上の問題は起こりにくいですが、一度決めた勘定科目は継続して使用することが大切です。
「賃借料」として処理するケース
「賃借料」は、土地や建物といった不動産以外のものをレンタルした際に使用する勘定科目です。 例えば、コピー機やパソコン、車両などが該当します。レンタルオフィスは、単なるスペースではなく、デスクや椅子、インターネット回線、複合機といった設備やサービスを含めた利用契約と捉えることができます。 このように、オフィス空間と付帯サービスを一体のパッケージとして借りていると考える場合、「賃借料」で処理するのが適切です。 多くのレンタルオフィスでは、この考え方が採用されています。
「地代家賃」として処理するケース
「地代家賃」は、事務所や店舗、駐車場といった土地や建物を借りた際の家賃を処理するための勘定科目です。 レンタルオフィスであっても、特定の個室を占有して利用する契約形態の場合、事務所という「不動産」を借りている側面が強いと解釈できます。この場合、「地代家賃」として計上することが考えられます。
どちらを選ぶべきかの判断基準
「賃借料」と「地代家賃」のどちらを選ぶべきか、明確なルールはありませんが、契約の実態に合わせて判断するのが良いでしょう。
| 勘定科目 | 判断基準 | 具体例 |
| 賃借料 | 設備やサービスを含めたパッケージ利用と捉える場合。 | コワーキングスペース、家具付きのサービスオフィス |
| 地代家賃 | 特定の空間(不動産)を借りるという側面が強い場合。 | 個室タイプのレンタルオフィス |
実務上は、レンタルオフィス側から勘定科目について指定がある場合や、請求書に「賃借料」と明記されているケースも多いです。その場合は、請求書の表記に従って処理するのがスムーズでしょう。重要なのは、自社のルールとしてどちらかに統一し、継続的に同じ科目で処理することです。
【費用別】レンタルオフィス関連費用の勘定科目と仕訳例
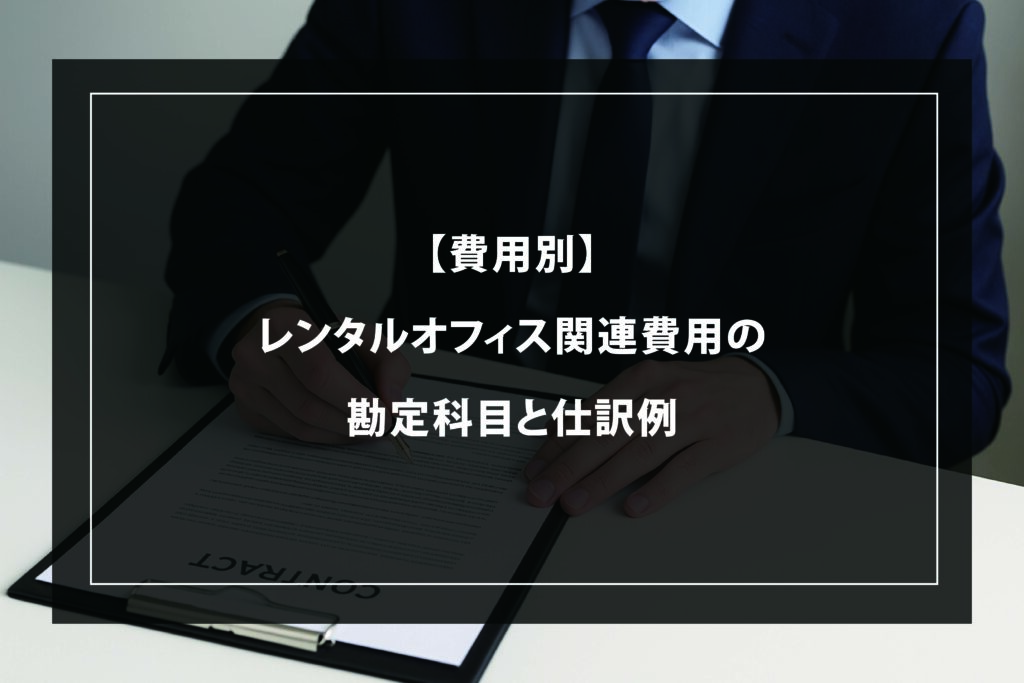
レンタルオフィスでは、月額の基本料金以外にも様々な費用が発生します。ここでは、費用項目ごとに適した勘定科目と具体的な仕訳例を解説します。
入会金や契約金などの初期費用
入会金や契約金は、返還されない一時的な費用であり、その効果が1年以上に及ぶ場合は「長期前払費用」として資産計上し、契約期間にわたって減価償却します。しかし、金額が20万円未満の場合は「支払手数料」などの勘定科目を使って、支払時に一括で費用計上することが一般的です。
【仕訳例】入会金50,000円を現金で支払った
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 支払い手数料 | 50,000円 | 現金 | 50,000円 |
保証金や敷金
保証金や敷金は、退去時に返還される予定の預け金です。そのため、経費ではなく「差入保証金」や「敷金」といった資産の勘定科目で処理します。退去時に返還された際には、この資産を取り崩す仕訳を行います。もし返還されない部分(償却費)があれば、その分は「支払手数料」などの費用として処理します。
【仕訳例】保証金100,000円を普通預金から振り込んだ
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 差入保証金 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
月額利用料
前述の通り、月々の基本料金は「賃借料」または「地代家賃」として処理します。
【仕訳例】月額利用料80,000円が普通預金から引き落とされた
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 賃借料 | 80,000円 | 普通預金 | 80,000円 |
共益費や光熱費
共益費や水道光熱費が月額利用料に含まれている場合は、まとめて「賃借料」や「地代家賃」として処理して問題ありません。もし請求書上でこれらの項目が別々に記載されている場合は、「水道光熱費」という勘定科目を使って別途計上することも可能です。
コピー機や会議室などの付帯サービス利用料
レンタルオフィスでは、基本料金以外に様々なオプションサービスがあります。 これらはサービス内容に応じて適切な勘定科目で処理する必要があります。
| サービス内容 | 勘定科目例 |
| コピー機、プリンター利用 | 消耗品費 |
| 会議室利用 | 会議費 |
| インターネット、電話回線利用 | 通信費 |
| 電話代行、郵便物転送 | 支払手数料 |
| 法人登記サービス | 支払手数料 |
これらの費用も、月額利用料と合算して「賃借料」として処理することが許容される場合もありますが、費用管理を明確にするためには、サービス内容に応じて勘定科目を分けることが推奨されます。
レンタルオフィスの会計処理で注意すべき3つのポイント
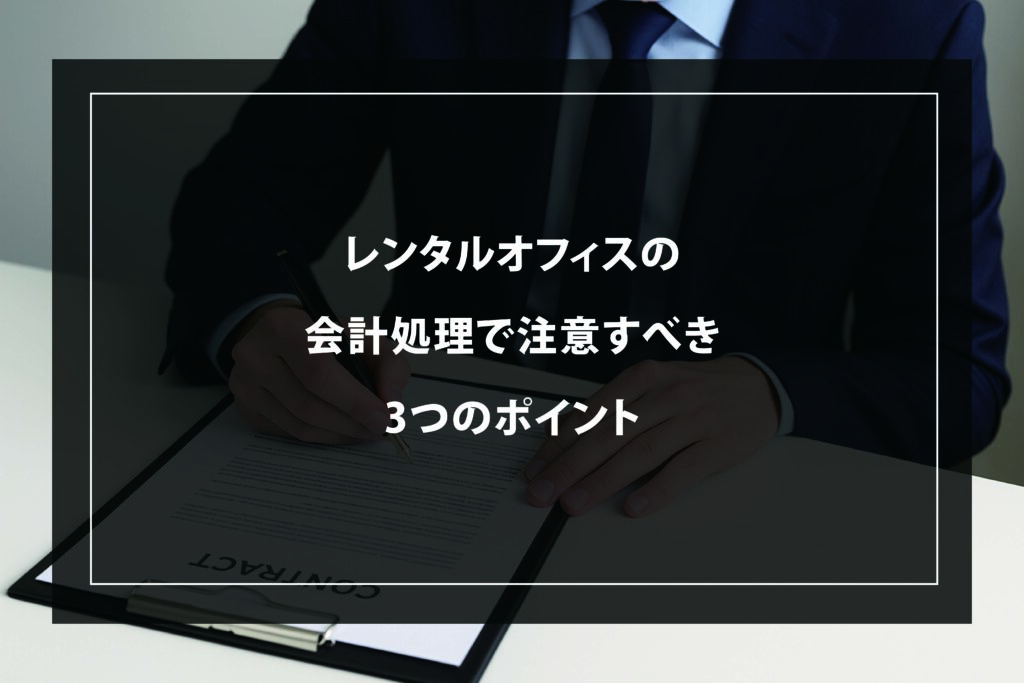
レンタルオフィスの費用を経費計上する際には、いくつか注意すべき点があります。正しい会計処理のために、以下のポイントを押さえておきましょう。
1. 契約内容を確認する
会計処理の基本は、契約内容を正しく把握することです。契約書には、どの費用が月額料金に含まれ、何がオプションサービスなのか、また保証金の返還条件などが記載されています。特に、費用の内訳は勘定科目を判断する上で重要な情報源となりますので、契約時に必ず確認しましょう。
2. 消費税の課税・非課税の判定
勘定科目の選択と同様に、消費税の扱いも重要です。「地代家賃」として処理する場合、居住用の家賃は非課税ですが、事業用の事務所家賃は課税対象です。レンタルオフィスは事業用なので、基本的には課税対象となります。ただし、保証金や敷金は預け金であり、資産の移動にすぎないため消費税の課税対象外(不課税)です。請求書をよく確認し、正しく処理することが求められます。
3. 個人事業主は家事按分に注意
個人事業主がレンタルオフィスを事業だけでなくプライベートでも利用している場合、家事按分(かじあんぶん)が必要になる可能性があります。例えば、事業での利用が70%、プライベートでの利用が30%であれば、支払った費用のうち70%のみを経費として計上します。事業利用の実態に合わせて、合理的な割合で按分計算を行う必要があります。
勘定科目の判断に迷った際の相談先
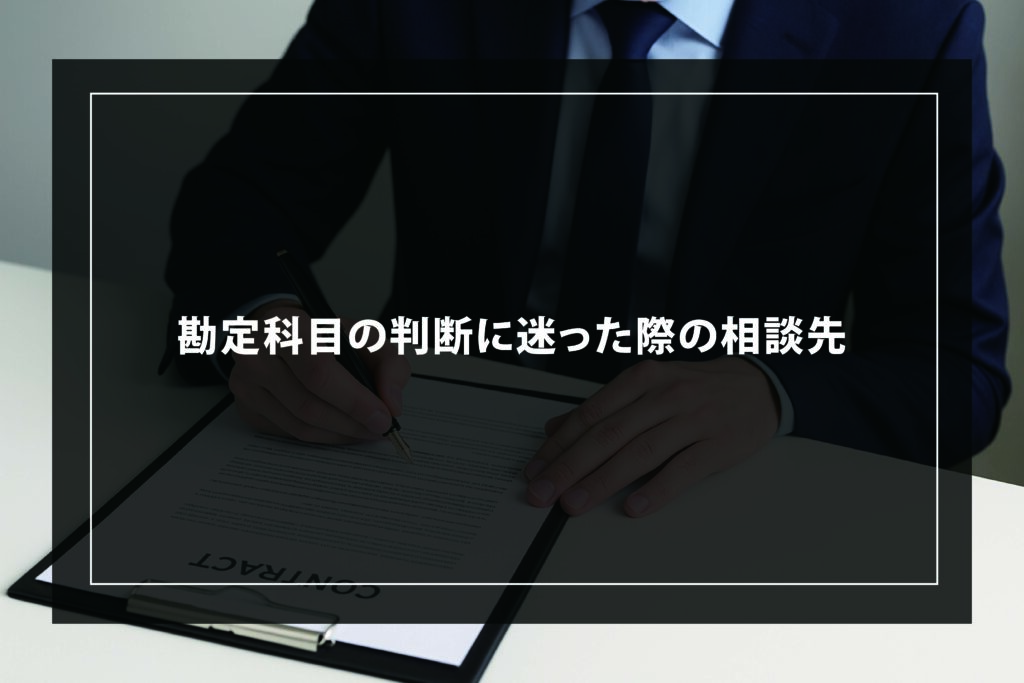
会計処理は専門的な知識を要するため、どうしても判断に迷う場面が出てきます。そのような場合は、専門家に相談するのが最も確実で安心な方法です。
顧問税理士に相談する
企業の会計や税務をサポートしてくれる顧問税理士は、最も頼りになる相談相手です。契約内容や企業の状況を総合的に判断し、最適な会計処理方法をアドバイスしてくれます。仕訳方法だけでなく、節税対策についても相談できるでしょう。
所轄の税務署に問い合わせる
顧問税理士がいない場合は、管轄の税務署に電話などで問い合わせて確認することもできます。匿名での相談も可能で、具体的な取引内容を伝えれば、一般的な処理方法について教えてもらうことができます。ただし、最終的な判断は自己の責任となる点には注意が必要です。
まとめ
レンタルオフィスの勘定科目は、契約内容に応じて「賃借料」や「地代家賃」を基本とし、付帯サービスについては「支払手数料」や「通信費」など適切な科目で処理します。 最も重要なのは、一度採用した処理方法を継続し、一貫性のある帳簿を作成することです。
本記事で解説した内容を参考に、契約書をよく確認し、適切な会計処理を行ってください。判断に迷った際は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

writing by:nex株式会社 事業企画室
nexでは、レンタルオフィス・コワーキングスペース・バーチャルオフィスに関する情報を、コラム記事を通じてわかりやすく発信しています。
自社サービスに限らず、これから働き方を見直したい方・新しい拠点を検討している方に役立つ業界情報をお届けしていきます。